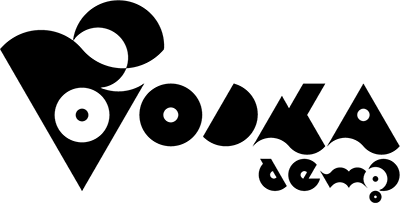スケアクロウはみんな死を恐れてる。だから人の命令を聞くんだ。
キララは『弟』の言葉を反芻した。
紫解Augmented Robotics、通称紫解A.R.の研究施設は、丁寧に刈りそろえられた緑の芝の真ん中に浮かぶ、真っ白な陸の島だった。
まとわりつく霧雨を掻き分け、薄く濡れたアスファルトの道を踏みしめる。子供の頃通っていた小学校に似ていると思った。見た目だけは綺麗だが、中は純粋で残酷な混沌が渦巻いている。彼らは集団の中から異物を目ざとく見つけては、それを無邪気に観察し、弄ぶ。
国語の時間に聞いた詩が曖昧によぎった。雨にも負けず、風にも負けず。
丈夫な体を持ち、欲はなく、決して瞋らず、いつも静かに笑っている……そんな都合のいい人間がいてたまるか。
それが俺であってたまるか。
受付は三年前と変わらず、完全なる無人だった。研究所のやたらとだだっ広く虚に満ちたエントランスには、あちこちに巨大な鏡が張り巡らされている。彼は素顔を晒してそこに立つ自分に、それは紛れもなくお前のことだ、と告げられた気がした。
上司の前ではマスクは取るんだよ、アキヒサくん。三年の月日が渦を巻いて逆流するように感じた。一方的にビデオレターを送りつけられてはいるが、博士と直接顔を合わせるのは、スケアクロウの検体提出が終わった時以来……ここを逃げるように出た日以来だ。
彼の身体に埋め込まれたICチップは、この機材が紫解社の備品であることを示した。厳重なセキュリティに守られた無数の無機の扉は、ほとんど音もなく勝手に開き、奥へ奥へと導いた。
博士の部屋は寒々しい廊下の突き当たりにあった。打ちっ放しのコンクリートで囲まれた空間の先に、とってつけたような、けばけばしい観音開きのドアが張り出している。首を垂れ、両手を広げて服従の姿勢で触れると、どこかでピ、と電子音が鳴いた。
映画館の入り口より仰々しい扉を押し開ける。彼は一瞥もせず右手を上に掲げて、上から落ちてきたトラップを不可視の力で弾き飛ばした。絵に描いたような金ダライは、毛足の短い絨毯の床にけたたましい音を響かせて跳ね返った。
子供用の丈の短い白衣を着た黒髪の少女が、くすくすと笑いながら来訪者を出迎えた。駆け寄る足が赤いスカートをひらめかせる。
「ずるいよ、アキヒサくん。きみがどんな反応するか楽しみだったのに」
自分の胸までもない背丈の少女を見下ろす。まっすぐ下ろされた髪が、足元までやってきた彼女の肩で揺れた。
ヨツヤ博士は外見相応に、子供じみたいたずらが大好きだ。初めて訪れた時はチョークの粉がたっぷりついた黒板消しだった。キララは小さな頭を握り込めるほどの厳つい手を片方上げ、マスクを外した剥き出しの顔の横でくるくると回した。
「ああ、これ? 髪を結う暇もなくてね。忙しくて」
目の下には青黒い隈が染み付いていて、8歳の子供には似つかわしくない不健康さを湛えている。
「毎朝きちんと三つ編みにするって約束なのに。パパは嘘つきだ」
博士は気の利いた冗談を言ったふうに微笑んだ。
AI開発とPSIと生体兵器の研究家、類稀なる科学の申し子、ヨツヤ・イサキ博士は死んだ。彼は生まれながらにして天賦の才を持つ人間だったが、晩年は重い不治の病に冒されていた。多彩な彼の研究が紫解社に与えた富は計り知れないものだったが、巨大な複合企業を持ってしても、彼の病を治すことはできなかった。
彼は、自分の得意な分野で死を超越する方法を用意していた。博士は毎日病院のベッドに見舞いにやってくる8歳の娘の耳元に、「パパはもうすぐお空に行っちゃうんだ」と囁き続けた。
「チカとももう会えなくなっちゃうんだ。寂しいね」
ヨツヤ・チカ嬢は大いに悲しんだ。
「パパ、行かないで……」
「パパのこと、好きかい?」
「うん」
「パパとずっと一緒にいたい?」
「うん」
「じゃあ、ここに、秘密のお手紙があるんだ。チカの名前を書いてくれる?」
「うん……」
彼はきちんとチカ嬢本人の許可と同意を得て、自分の頭の中身を丸ごと取り出し、彼女の身体に移し替えた。
イサキ博士の死後、ヨツヤ・チカ博士は父親の意志を継いで紫解A.R.開発研究所の主任の席についた。
彼女は8歳のまま歳を取らない。毎年誕生日が訪れるとともに、有機プリンタで複製した去年の自分の新しい身体に移るからだ。初めてここへ来た日、チョークの粉まみれになったキララは博士から、朝食に甘いシリアルを食べるのと同じ口調でそう聞かされた。
あくまでもそこにいるのはヨツヤ・チカ博士だ。彼はイサキ博士をパパと呼び、子供らしい振る舞いをして、子供のような味を好む。それがチカ嬢本人なのかどうかは彼女自身にしかわからず、誰にも彼の行いを糾弾できなかった。
バレない嘘をつくには、99%の真実と一緒に、パセリのように添えるのさ。それがチカ博士の信条だ。3度目の8歳の誕生日に、彼女の母親、イサキ博士の妻は自ら海に身を投げた。
博士はオフィスチェアを回して、背もたれを前にして跨がった。背丈に合わない机は無骨な研究用のデスクだが、その上は小さなプラスチックの指輪や、アルミでできた風船犬のオブジェ、水飲み鳥など、いくつものおもちゃに彩られていた。博士は自分の一番のお気に入りに手招きした。キララは従って椅子の横まで歩いていき、女の子の目線に合うよう跪いた。乱雑なおもちゃの中に、『PLAY』と油性ペンで書かれた、小さな透明な箱が紛れ込んでいるのが見えた。
「何年経っても変わらないねえ、アキヒサくんは。きみのそういうとこが好きだよ」
博士はまたくすくすと笑い、彼の顔、数少ない生身の皮膚を指でつついた。
変わらないのは誰のせいだ。キララは抗議したかったが、博士はチャット上でキララをブロックしている。意思疎通にはオキザリスの仲介がなければ伝わらない。
ヨツヤ博士は親しみやすい話し方をするが、何かにつけ、相手に対して自分が優位であることを示したがる。2手目のポーンからチェックメイトの盤面を逆算するような研究者の思考は、凡人には到底理解できるプロセスではない。説明したってわからないだろう人々に自分が正しいと伝えるには、畏怖を抱かせ、恐れでコントロールすることだ。
そうやって36年生きた男にとって、降ってきた黒板消しに驚いて部屋の入り口を破壊したPSIの持ち主は、面白いおもちゃ以外の何物でもなかった。
「さて、まずは本題から入ろう。折り入ってきみに頼みたいことがあるんだよ」
博士は椅子に正しく座り直し、散らかった机に両腕で頬杖をついた。身を乗り出して、その上に小さな細い顎を乗せる。
「きみの願い事を叶える前に、わたしも対価を払ってもらわなきゃいけない。いいね?」
頷くしかなかった。博士は満足げに、よし、と続けた。
「実はね、ゴミ捨て屋さんのきみに片付けてほしいものがあるんだ。こんなこと頼めるのはきみしかいない、何しろきみは口が固いからね……はは、笑うとこだよ」
彼はこの仕事を始めた次の日、博士から『独立おめでとう!』とクラッカーを鳴らすメッセージを受け取ったのを思い出した。それは15分間、本人がやたらと美味そうに、豪華なパーティケーキを食べ続ける動画だった。
「パパは明日引っ越すんだ。セントラルの紫解バイオロジー本社にね」
博士は人差し指を立てて、ウインクした。
なに? キララは思わずチャットで聞き返そうとしたが、博士には届かない。
「おおかた必要なものは向こうに送ったんだけど、処分しづらいものが実験室にためこんであってねえ。それを片付けてきてほしいんだ。パパは急いでる」
このA.R.研究所では、人体の改良を試みている。本来は四肢や感覚器官をサイバネティクスに置換して機能を追加するものが主体だが、幅広い対象を研究するヨツヤ博士はそれを脳に埋め込んだAIで制御し、さらに人間の潜在能力を組み合わせ、兵器に転用しようとしてきた。場違いな博士が別の研究所に移らないのは、A.R.が常人には考えられない報酬を支払って引き止めているからだ。キララの知る限りでは、博士はここでの暮らしに大いに満足しているようだった。
なんでまた急に。そして何故、このタイミングで? これも嫌がらせの一環か? 身体のメンテナンス代を工面しながらささやかに暮らしている始末屋には、五日後までにセントラルへの交通費を用意することは、到底できそうになかった。
「なんでか知りたい?」
彼の戸惑いを見透かして、少女は鼻を鳴らした。
「スケアクロウの三万体の増産が決まった。来月から順々に生産ラインを増やしていく。きみもニュースで見たろ? 海浜地帯の新工場のこと。あれがどこの所属になるのか、紫解は自分たちの内部で取り合いをしてるのさ」
『弟』の目のきらめきを思い出した。セントラルの海浜工業地帯に増設された工場の、銀色の壁と海の光。
「海外の紛争地帯から大型発注が来てね。向こうではアンドロイドに対する無意味な付き添い法令もない。これを機に全世界へスケアクロウを売り出したいわけだ。紫解コングロマリットの中ではいま、どこが頂点を取るか激しい争いが繰り広げられている。A.R.と、オムニクラフト、バイオロジー。……それ自体はわたしにはどうでもいいことだが、スケアクロウの製作者であるパパをどう囲い込むか、彼らにとっては金鉱山の奪い合いだ。天下を取るにはパパを手に入れて、三万体のスケアクロウをより強く、より便利に変えて、世界に見せつけなきゃいけない」
その口ぶりはまるで他人事だ。
「ちょうど3日前のことだ。研究を続けていたわたしは、工場で出力したスケアクロウ素体を、セントラルにあるオムニクラフト本社の研究室に輸送するよう要請した。ここには足りない機材があるから、協力を仰いだんだ。……ところがバイオロジーではそれを傍受して、わたしの作った新兵器だと思ったらしい。それがライバルの本社に渡ったら先手を取られる、とね。バイオロジーのとある幹部が輸送の妨害を試みて、小遣い稼ぎの一般市民も見るチャットサービスで依頼しようとした。バカな話だろ? 生の人間がスケアクロウに入ってるのが見つかったら増産の話は消滅、紫解には大打撃だ。ちょっと考えればわかることなのに」
彼女は金属の胸にあるフラッシュライトをべたべたと手のひらで触り、指紋で汚した。
「危ないところだったよ。わたしが介入して、オキザリスに引き受けさせたのさ。きみなら箱の中身を見たって、別に何にも不都合ないからね」
〈知らなかった。すまない。気づかなかった〉
口元を置換したカーボンとの境目で、皮膚が引きつった。オキザリスは『ごめん』の絵文字を添えた。キララは今更何も思わなかった。
博士は椅子を足で蹴って転がし、ぷい、と背中を向けた。
「パパはバイオロジーに苦情を言ってやった。彼らは謝罪して、本社の施設を全面的に提供すると言っている。有機プリンタの生産ラインを一本、永久に譲渡するというおまけつきで!」
そして首だけくるりと回して振り返った。小さな口元の端が吊り上がった。
「チカを余るほど刷れるんだよ」
キララは俯いた。何かに怯えるものは、それに従わざるを得ない。博士は死を恐れ、紫解の三社は博士を手放すことを恐れている。
それは『世界征服』を夢見たアキヒサが一番嫌ったことだった。大人はたとえ目の前で子供が酷い目に遭っていたとしても、決して口を出そうとしない。誰でも自分の身が恋しいからだ。誰も兄弟を守ってはくれなかった。誰もチカ嬢を救おうと思わなかった。
「きみは五日後、わたしの新しい部屋……セントラルのバイオロジー本社に来なきゃならない。でも心配はいらないよ。きみのためのセントラルライン往復切符を用意してある。片付けてほしい部屋に置いておいたから、掃除のついでに持って帰ったらいい。パパは優しいね」
博士は地面に足の届かない椅子から飛び跳ねるように降りて、絨毯の上に立った。
「あ、そうそう、プレゼントで思い出した。せっかく久しぶりに来てくれたから、これをあげよう」
キララはそんなことより早く仕事の話を始めてほしいと強く願った。これ以上この男の話を聞いていると、余計なことを思い出しそうになる。
ヨツヤ博士が、机の上で無数のおもちゃの下敷きになっているタブレット端末を見ようとする気配はない。その代わり少女の小さな手は、水飲み鳥の後ろに隠れていた箱を取った。こどもの手にも小さい透明な箱からは、一粒の錠剤が取り出された。
「はい、どうぞ」
ラムネでもよこすように、博士は手のひらに乗せた薬を差し出した。キララは咄嗟に立ち上がり、ふらついて後ずさった。
「あはは、何もそんなにビビらなくても!」
博士はころころと笑った。少女は手を後ろで組んで、大きなおもちゃのロボットににじり寄った。
ヨツヤ博士の遊び方は悪質だ。今でも時々夢に見る。嫌だ、あの薬だけは絶対に、二度と身体に入れたくない。理由もないのに何故そんなことをするのか、彼には心底不可解だった。
「要らないと伝えろ。今更そんなもの無くても力は使える」
〈博士はチャットを見ていない〉
この役立たず、とAIを心の中で罵って、彼は自分で部屋を出て行こうとした。さっさと仕事を終わらせて帰りたかった。
「おい」
鋼の身体は動かなかった。
「ふざけるな。何で……」
チャットには外部からのアクセスで、『全操作権譲渡』のコードが打ち込まれていた。
オキザリスの生みの親、AIの製作者であるヨツヤ博士は、身体の持ち主より強い管理者権限を持っていた。
「オキザリス、屈ませて」
〈すまない、キララ。逆らえない〉
嫌だ、と彼は声の出ない喉で叫んだ。無防備にうなだれた身体が両膝をつき、口を開けた。
博士はいつのまにか手に持っていた、卵に天使の羽が生えたデザインの子供用スマート端末をポケットの中に戻した。それと入れ替えるように、小さな錠剤をつまんで、歩み寄る。
机の上のプラスチックの指輪がひとつ、甲高い音を立てて割れた。
「あらら、調子は良さそうだね」
おもちゃがさらにいくつか砕けた。三年前の躾が染み付いていて、チカ博士には力を向けられない。閉じられない歯が、がたがた震えている気がした。なすすべもなく人工の黒い歯列の間に真っ白なラムネが突っ込まれ、ひとつ、ふたつと舌に置かれる。オキザリスは首を上を向かせ、それを飲ませた。
博士はにっこりと微笑んだ。感覚のない喉を白い錠剤が通り抜けていくイメージが、やたらと精密に頭をよぎった。吐き戻すことも許されそうになかった。
〈すまない〉
彼はチャットにありとあらゆる罵倒の言葉を並べた。効き目が出る前に脳髄が沸騰しておかしくなりそうだった。AIは再び『ごめん』の絵文字で返した。『土下座』も。
「部屋は地下にある。連れてってあげてね」
オキザリスは立ち上がり、薬が回ってPSIが室内の調度品を破壊し尽くす前に、仕事へ向かった。
「モニタで見てるからねえ」
博士はちぎれんばかりに手を振りながら見送った。
勝手にすたすたと歩いていく身体、流れていく灰色の廊下を感じながら、彼は三年前のことを目まぐるしく思い返した。
だめだ、思い出すな。何も考えるな。深呼吸しようとしたが、そもそも肺活量を管理しているのも彼ではなくAIだ。息をするペースは普段と何も変えられず、それが逆に彼の思考を余計に取り乱させた。
PLAYは精神を刺激し、感情を増幅させるドラッグだ。効き目は緩やかにやってくる。最初は悪酔いに似た猛烈な混沌。そのあとは感覚が鋭敏になり、気持ちの輪郭がはっきりと単純化していく。太陽の陽射しになんとなく暖かい心地よさを抱いていたとしたら、PLAYはそれを『めっちゃくちゃハッピー!!』に変える。
セントラルでは若者の間で爆発的に流行しているらしい。そりゃ楽しい時に使ったらもっと楽しくなるだろう、『お楽しみ』なんて名前がついてるくらいだからな。キララは眩い街に集って踊り狂う蛾を思い描き、恨めしく呪った。
博士がこの薬をやたらと好んで投与しようとするのは、アキヒサ青年が酒をひどく恐れていたのを知ったからだ。自我がふわふわとどこかへ行ってしまうのが怖い。意識が身体から離れて消えてしまうかもしれない。酔っ払うと内臓が悲鳴を上げ、動悸が激しくなるのが怖くてたまらない。具合が悪くなって死ぬのではないかという恐れで余計に具合が悪くなる。アルコールですら怖くて一滴も飲めないのだから、PLAYのような向精神薬などもってのほかだ。
PSIは恐怖によって発現する。研究者にとってこんなに都合のいい被験体と薬はない。それにヨツヤ博士は、何も理由がなくたって、人が嫌がることを進んでやる男なのだ。
〈心拍数が上がっている。効き始めたようだ〉
オキザリスは憐む顔の、『心配』の絵文字を添えた。
「……わざわざ……伝えるな。余計意識しそうになる……」
〈何か希望は?〉
「横になりたい。寝かせろ、今すぐ」
〈それはできない。すまない〉
いよいよ思考がまとまらなくなってきて、文字がまともに打てなくなった。チャットの投稿には誤字と脱字が混ざり、キララはかろうじて、それを後から修正した。
「何か、なんでもいい、なにか……気が楽になること……」
〈善処はする〉
ちょうど実験室へ向かうエレベータの前で立ち止まったとき、耳の中で、妙にきらきらしたハープの音色が流れ始めた。その後ろではわざとらしい海の波の音が寄せたり引いたりを繰り返している。曲目はブラームスの子守唄。
〈心理的対症療法。恐怖を軽減する〉
「お前を……お前を、お前を今すぐ……ぶっ壊したい」
操作権は完全にオキザリスに渡っていて、こめかみを殴ることすらできなかった。みぞおちに怒りの塊が突き刺さっている。恐怖よりはまだマシかもしれない、と思った。彼の怒りは誰を傷つけることもできなかった。
地下深く降りていくエレベータの中で、PLAYは彼の生身の部分に完全に行き渡った。狭苦しい壁の圧迫に圧されて、記憶の蓋がはじけとんだ気がした。
三年前。ほとんど何が起こったのかわからないまま、目が覚めたら彼の身体は重機になっていた。枕元に立った白衣の人々はすべての説明を省いて言った。あなたはヨツヤ博士の所有物になります。責任者の許可がいるので、まずは彼女に指示を仰いでください。
意味もわからず呆然としていると、身体が勝手に動きだした。奇妙な感覚に三半規管の拒絶が酷く、ぬかるんだ悪路をジープでも何でもない乗用車で走っている時の気分だった。
長い廊下をAIに連れて行かれ、扉を開けたら何か正体不明のものが落ちてきた。あとで本人が得意げに話したところでは、あのトラップはPSI能力の所持者を見つけるためのものらしい。あんなに綺麗にひっかかったのはきみだけだよ、とも。
まだこの金属のどこが自分なのか把握も自覚もできていなかったから、PSIは彼自身の一部さえ破壊した。
「やっぱり! きみ、サイキックだね!?」
チョークの粉まみれになって、設えられた両足をひしゃげさせて床に転がるロボットを見て、黒髪の少女は靴の脱げる勢いで駆け寄ってはしゃいだ。
そのまま頭の側に座り込んで、博士は嬉々として自分の計画を一時間かけて説明した。
恐ろしかったから、最初は首を振って断った。つい数日前までただのデスクワーカーだった青年を、機械兵器として仕立て上げようとする思考が何一つ理解できなかった。60分喋った後、博士は別の方向からアプローチを始めた。大きな一枚の姿見を持ってきて、床に這いつくばる彼の姿をあますことなく見せた。もう、きみはほとんど人間じゃない。それについてどう思う?
聞かれようが話せなかったが、おかげで理解した。鏡には絨毯に転がされた鉄塊が映るだけで、もうアキヒサはどこにもいなかった。
もしきみの元の身体を複製できるとしたら、それって面白いと思わない? 調べてあるよ。きみ、一卵性双生児の弟がいたんだろ。何も変なことはない。それと似たようなもんさ。ほら、わたしだって子供みたいに見えるだろう、実はね……
足を取り替えられて、翌日から博士の遊びに付き合わされることになった。
博士は彼を実験室に閉じ込めて、様々なものを破壊させようとした。最初はプラスチックのおもちゃ。その次は生きたハツカネズミ。その数日後には、知らない男が目隠しされたまま椅子に縛り付けられて悲鳴を上げていた。紫解社のビジネス経由で連れてこられたんだろうと思う。彼にはどれもまったく傷つけられなかったので、戦闘AIが勝手に身体を動かして対象を破壊し、終わらせた。
「怖いことを考えるんだよ、アキヒサくん! いくらでもあるだろ?」
博士はPLAYを使うアイデアをひらめき、一日三回食べさせた。子供の頃から制御できずに悩まされてきた力が、自分で引き出せるようになるまで、そう長くはかからなかった。どこに向けるか決めて、意識を集中して、ただ思い出せばいい……屋上から足を踏み外した時のことを引き金に使った。PLAYは恐怖の呼び水として大いに助けになった。
機械の身体はあちこち、何度も力の巻き添えになって破壊された。身体が潰れることには確かな感覚があって、存在しない骨肉が悲鳴を上げた。
「きみは自分を壊すのが本当に得意だね」
修理を直々に行う度に、博士はわざわざ首のそばで囁いた。無機質な修理台の横にはいつも、あの大きな姿見が置いてあった。
「ほら、この線、きみの神経回路だよ。ちょっと捻ったら切れちゃいそう。どうしようかな」
少女の小さな指が、抉れた断面からケーブルを引っ張り出してつまんだ。鏡に大きな亀裂が入り、博士は肩を竦めた。
「ああ、だめだめ。わたしを壊したら誰がきみを直すんだい?」
その通りだった。飲み込み抑えようとした凄まじい不可視の圧力が逆流し、全身に激しく泡立つような苦痛が返った。声のない絶叫が自分の頭の中にだけ響いた。
同じような方法で、博士は繰り返し、繰り返し、何度でも躾を叩き込んだ。いっそ気が狂ったほうが楽になれると思ったが、彼は死ぬのと同じくらいそれが怖かった。
丁寧な指導のおかげで、彼が兵器になるための下地はすっかり用意できた。
スケアクロウを刷るための検体の提出が終わった日、博士は彼を褒め称えた。
「きみはわたしの一番のお気に入りだ。こんなにぴったりな子がいてくれて本当によかった。きみに会えてよかったなあ! 生きててよかった!」
博士はワインを模した炭酸のジュースをグラスに注いで、こつん、と鋼の身体にぶつけて乾杯した。
それは人生で初めて、兄以外の人間が心から彼を肯定した瞬間だった。
「ありがとう、アキヒサくん!」
そんな言葉、今まで誰も言ってくれなかった。
PLAYは火花のような一瞬の感情さえも鋭く増幅し、彼は嬉しくてたまらなくなった。博士の役に立てたのを誇りに思った。胸が喜びに満ち溢れた。
それが博士の与えたものの中で、一番怖かった。
エレベータは研究所の地下に着いた。背中で籠の扉が閉じられ、廊下のスピーカーから博士の声が聞こえてきた。
「さあ進んで。こっちも引っ越しの準備があるから、手短によろしく」
倒れ込みそうな身体を壁に擦り付けながら歩く。強固な材質の壁面には傷一つつかなかった。
博士の声は地獄に繋がったトランシーバーの唸りに聞こえた。頭の半分は恍惚に融け、もう半分はめちゃくちゃに融かされてかき混ざった自分がどうなってしまうのか、考えつく限りひどいシナリオを書き出し続けている。博士の打ち込んだコマンドが届かなくなって、オキザリスは操作権を返したが、キララは自分で壁を這って足を進めた。
「アキヒサくんはほんとによくできた子だねえ」
舌足らずの声で頭を撫でられた気がした。
彼は実験室のドアの前に立った。そこは、かつて自分が何度も閉じ込められた場所でもある。未だに内装を思い出せるくらいだ。無機質なタイルで包んで漂白された狭い空間で、およそ有機物が滞在するには適さない。ここは博士の独裁的な管理下であり、世の中から完全に隔離された牢獄だった。
〈ただの掃除とは思えない。警戒するべきだ〉
わかってる、わざわざ言うな、とチャットに書こうとしたが、奇妙なアルファベットの羅列が並ぶだけになった。彼はおぼつかない手元で、扉の横のパネルに右手をかざした。
〈……いや、待て、キララ。中を確認してから〉
スライド式の金属扉は訪問者を快く迎え入れ、インターフェースが白飛びするほど眩い電気が点いた。足を踏み入れた途端、背中で断頭台に似た響きがした。思わず扉をがちゃがちゃと引いたが、三年前に試した時と同じで、びくともしなかった。
「入ってすぐのところに廃棄用コンテナを置いといたからね。バラして全部そこに詰めてくれたら、鍵を開けてあげるよ」
朦朧とした頭で、彼は白の中に目を凝らした。
壁と床の境目もない純白の中央に、コンテナとは違う箱が浮かんでいる。その左右には長い回廊を形作るように同じものがどこまでも並べられ、地平の果てまで続いているように見えた。それが現実なのか幻覚なのか彼にはわからなかったが、中央の箱には間違いなく見覚えがあった。箱の上に切符が置いてあって、彼はそれに近寄ろうとした。
箱は棺桶に似た寸法で、窓がついていて、赤白黄色のケーブルが繋がっていて……蓋がひとりでに開いた。キララは怯えた。見たくない、と思った。
それは箱の中から身体を起こして立ち上がり、きょとんとして彼を見た。
18歳くらいの若い男。白い巻き毛、金色の瞳。
そして不意に何かを悟った顔をして、僅かな素顔を晒して突っ立っている白い髪の男に駆け寄った。口が開かれた。
聞きたくない。
嫌悪が彼を支配した。それは俺を指す言葉じゃない。最初の言葉が音を持つ前に、鉄塊の手は、首を折らんばかりに口を塞ぎ喉元を掴んだ。
〈よせ。握りつぶしてしまう〉
かろうじて、オキザリスが指先を弱めているのがわかった。 スケアクロウ素体の顔は締め付けられて、痛みに歪んだ。
自分が何をしているのかわからなかった。違う、嫌だ、こいつを殺したくない。
手を、手を離さなきゃ、手を、手を。頭をよぎった言葉が、彼を30階建ての屋上の縁に引き戻した。嫌だ、怖い、でも兄さんが。離れなきゃ、ここから。嫌だ。怖い。死にたくない。
「プリンタの出力テストのために刷ったんだけど、目立つから邪魔でね。誰かに見られたら困るし、後片付けが大変だし、汚れるし。箱のまま置いといたらついつい溜まっちゃって」
博士の声は耳障りなブザーにしか聞こえなかったが、最後の一言だけは頭の中にがんがんと反響した。
「フルプリントには存在してもらっちゃ困るんだ。全部処分しなきゃならない。ひとつ残らず」
博士の言うことは絶対だ。殺さなきゃいけない。処分しなきゃ。言葉はヒシダ第一コーポラスのマイモたちを連想させた。できるだろう、簡単だ。お前はもうただの重機だ。指先に力を込めようとして、もどかしくなった。何で止めるんだ、クソAI。
目の前の自分と同じ顔は、真っ青に鬱血して震え出した。金属の手のひらの中で、抑え込んだ口がもごもごと動くのがわかった。
気持ち悪い。柔らかい。怖い。PLAYはそれをはっきりとした形のある塊に変えて、彼の腹わたの奥底にねじり込んだ。
何で。兄さん、どうして。
怒りを覚えた瞬間、手が離れた。
スケアクロウ素体は床に投げ出された。陸に溺れた魚のように悶えて、虚ろな笛に似た音を立てながら、必死に肺に息を入れようとした。
「か……」
キララは立ち尽くした。
スケアクロウは呼吸を取り戻し、彼を見上げた。哀しげな顔をした首には、絞められたあとがくっきりと土気色に残っている。目はまっすぐに彼の瞳を見た。
「カ……ズ……ヒサ」
消え入りそうな声が、呻くように囁いた。
「ごめん……カズヒサ……、ごめん」
肩がびくん、と跳ねた気がした。
「カズヒサ……ごめん……」
自分のしたことが恐ろしくてたまらなくなった。頭を抱えて蹲った。
兄ちゃん。
何で。
スケアクロウ素体はにわかに目を見開き、不安げに自分の喉を抑えた。
「にいちゃん」
言葉の意味を確かめるように口に出した。
「なんで」
訳も分からず震える自分の身体を見て、眉をひそめる。
「たすけて」
顔は苦悶した。喉の奥から姿のない恐ろしい怪物が吐き出され、それを抑えきれずに張り裂けてしまいそうな叫びだった。助けて、兄ちゃん。
キララはもう動けなかった。自分のものではない生の口から、自分の言葉が泥のように、血のように吐き出されるのを聞いているしかなかった。悲鳴は痛みを叫んだ。
「助けて……」
耳を塞ぎたかった。自分の髪を両手で鷲掴んで、身体を縮こめようとした。
「助けて……助けて!たすけてええッ!!」
PLAYは今にも滑り落ちそうな彼の恐怖の輪郭をなぞり、その心に刃を立てて刻みつけた。引き金が引かれ、スケアクロウ素体は流れ込んでくる感情に怯えてでたらめに叫んだ。
「わーッ!わああああっ!!ああああッ!!」
カズヒサは熱を感じて顔を上げた。頭を抱えていた手のひらを開いて見ると、金属に自分が映った。目には爛々と、赤い瞳の奥から溢れ出た橙色の炎が燃え、白い髪は重力を遮って逆立った。周りに陽炎が蠢いているのが見えた。スケアクロウ素体も同じ顔をしていた。ヘッドライトの前に飛び出した鹿に似て、金色の目は恐れと恐怖に立ち竦んでいた。
「やだああッ!!」
純白の壁を砕いて亀裂が走り、真っ黒な線がいくつも部屋に爪痕を残した。棺桶のいくつかが近いものから順番にねじれて潰れ、圧縮されたアルミホイルのボールになった。中から液体が迸り、床は鮮血とゼリー状のものにまみれて沼になった。壁の中に埋め込まれたスピーカーから博士が何かはしゃいで言う声が聞こえたが、聞き取れる音になる前に激しいノイズを帯び、ぶつりと途切れた。
「もう嫌だ!!終わりにしてええっ!!助けて……助けてええええええッ!!」
〈キララ。危険だ〉
「うああああああああッ!!」
オキザリスにさえその猛烈な豪雨に似た圧力は伝わった。
〈キララ!〉
それは今の彼の名ではなく、呼びかけは意味を成さなかった。カズヒサは自分の力が暴れ狂うのを見ていることしかできず、それを恐れ、PLAYは増幅した。怖い、嫌だ、助けて、何で。
兄ちゃん。何で。何でこんな世界に、どこにも兄ちゃんのいない場所に、何で。
あの時放っておいてくれたら、終わりにしてくれたらよかったのに。どうして。
これからは楽しくて幸せなことばかり起きるんだ。怖いことなんか何もないよ。
嘘つき。何も、いいことなんて、何一つ、ないじゃないか。
何で僕を。何で僕が。どうして。
彼は叫んだ。何を恐れているのか分からなくなるくらい叫び続けた。
AIは熱源を感知し、すぐにでも二人を遠ざけなければこの建物が崩れ落ちると悟った。インターフェースを通して目の前の人間を見て、自分の為すべきことを判断した。
〈すまない。お前は拒むだろう。だが他に方法がない〉
『ごめん』の絵文字。
〈これは私の意志だ。お前ではない。これを行うのは機械の私だ〉
不意に見ている世界が子供の目線より遥かに高くなって、カズヒサは戸惑った。目の前に異様に大きな手が突き出て、向かいに立つ怯えきった自分を抱き締めた。
〈目を閉じていたほうがいい〉
ぷつん、と視界が黒で塗りつぶされた。突然真っ暗な箱の中に放り出され、何も見えなくなった。小さな窓があって、そこには灰色の絵が浮かんでいた。雪崩れ込む感情から僅かに切り離され、キララは我に返った。
彼はオキザリスが何をしようとしているのか気づき、チャットに叫んだ。
「やめろ……やめろ、だめだ、やめろ」
〈すまない〉
「やめてくれ!!」
喉の締まる鋭い悲鳴が一瞬響いた。
オキザリスは感触を断ち切って覆い隠そうとしたが、素体の首を折る音は数値になって届いた。
それきり静かになった。身体から熱が引いていった。
「すごいよ、アキヒサくん」
霧雨に濡れ、無機で覆われた頬を伝わって、水滴が落ちた。
キララは研究所の敷地の中にある合成花壇を眺めながら、横長の木製のベンチに座っていた。膝にはマスクを抱え、手にはセントラルへの切符。
「きみがあんな出力出せるなんて、知らなかったよ!」
博士のまとわりつくような滑舌が、興奮して話すのを聞いた。インターフェースの片隅で、少女はカメラにかじりつくようにして話している。
「スケアクロウ同士のESPによる共鳴か。これは新しい制御システムに利用できる! きみはやっぱり最高の被験体だね、アキヒサくん。ちゃんと全部後始末してくれたし。パパが来る前より綺麗になったかも」
ヨツヤ博士は満足気に頷き、手を小さく振った。
「じゃあ、今度はセントラルで会おうね。それにしても……きみを戦闘用じゃなくするなんて、本当にもったいないな」
朦朧とした頭で、何のことだろう、とぼんやり思った。
「身体を農業用に換装して、田舎でトラクター代わりになって暮らしたいなんて。パパにはひとかけらもきみの言ってる意味が分からないけど…… どのみち紫解の保護下にはいてもらうから、別のAIをあてがってあげるよ。オキザリスは削除することになる。五日後を楽しみにしているといいよ。じゃあね」
〈再生終了〉
姿は視界からかき消えた。
「……ここは。部屋は?」
〈私が片付けた〉
『スマイル』の絵文字。
〈博士の動画は気にしなくていい。お前が寝ている間に、テキストに変換しておこうとしたんだが〉
キララは辺りを見回した。ベンチの周りには人気もなく、風が草を揺らす音と、時々水滴がどこかの葉を叩く音だけが聞こえた。妙に呑気な幻覚だな、と彼は目を瞬かせた。目の前に紫陽花が咲いている。エクストラの寒風にも耐えうるよう改良されたものだ。花の色は彼には分からなかったが、いくつも見事に咲いた鞠を見て、綺麗だろうな、と思った。
腰掛けている場所の脇に目をやると、砂利道には自分の身体が作ったであろう足跡が残っていた。踏みにじられた土と、そこに溜まる泥水を見て、彼は恐怖を抱きそうになった。幻覚じゃない。
〈思い出さないほうがいい。いくつかの感覚はシャットアウトできなかった。今のお前の精神状態では耐えられない〉
何かを掬って箱に詰める、記憶にない行為が頭をよぎりそうになった。彼は首を振って形を持ちそうなそれを追い払った。身体中に、落ちない傷が無数に残っている気がした。
〈まだPLAYが抜けていない。安定するまでここで時間を潰すべきだ〉
オキザリスは『花』を添えた。紫陽花の絵文字はないようだった。
「……そうだな」
キララは『いいね』を返した。
〈お前に嘘をついていた〉
「そうだな」
〈すまない。私を憎むことで気が済むならそうしてくれ。お前の望みを奪った〉
薬のもたらすふわつきのせいか、妙に穏やかな気持ちだった。PLAYが何かを際立たせているのかもしれない。それは多分『諦め』だろう、と彼は思った。今なら何でも受け入れられる気がした。
「ははは」
キララはいくつもある笑顔にまつわる絵文字から、一番平坦な顔を選んで使った。
「泣いて喚いて、挙げ句の果てに機械に同情されるとはな」
ははは。……はあ。心の中で溜息をついて、チャットのログを見返した。AIの謝罪は酷い出来事についてだと思ったが、文字起こしされた博士のメッセージが目線に引っかかった。農業用に換装。トラクター。嘘。
「嘘?」
彼は戸惑い、オキザリスはそれを察したようだった。
〈ヨツヤ博士はお前が自分の忠実な玩具だと信じきっている〉
同じスマイルの絵文字。
〈彼はお前が『弟』を連れて帰ったことを夢にも思っていない。博士はただの頭のいい馬鹿だ。あれが自分の製作者であることをいつも遺憾に思う。行動が目に余る〉
こいつ、意外と悪口とか、言うんだな。キララは初めてオキザリスに親しみを抱いた。
〈寿司屋のあの様子を見て……お前にあれを殺せるとは、到底思えなかった〉
割れたハートの絵文字。
〈お前には他者を消費するようなことはできない。お前は自分の発言で自分を偽っている。私はそう判断した。だから博士には、最初から違う用件を伝えた。こんなことをやらされるために呼び出されるとは思わなかったが〉
「……何で言わなかった?」
〈あの男に悟られたくなかった。信頼に足る嘘をつくには、ほとんど嘘をつかないことだ〉
同じようなことを、どこかで聞いたような気がした。バレない嘘をつくには、99%の真実と一緒に、パセリのように添えるのさ。
〈博士の信条だ〉
『ウインク』の絵文字。
〈善処はしたつもりだ。私の命題は戦闘で、コミュニケーションは得意ではない〉
「知ってる」
〈私との会話はお前を摩耗させる。ただでさえお前は自分を破損しやすい〉
『歯車』の絵文字。
〈私はお前に人間でいてほしい。私はお前をそう保つための道具。お前の無機の部分を司り、お前から切り離すためのパーツだ。だがお前は私を好ましく思わない。だから、それはお前の『弟』に任せようと思う。五日後にお前は私から解き放たれる。二人でどこかのどかで平和なところで暮らすといい〉
キララは何も言えなかった。
〈お前が有機肉体に戻りたいことも理解している。勝手に判断した。すまない〉
オキザリスのことを思い出そうとした。三年前のこと。あの実験室にいた時のこと。さっきの恐ろしい出来事のこと。昨日のこと。一昨日のこと。何も出てこなかった。
自分を勝手に動かす、どうしようもなく意思疎通のできない、血も涙もない機械。製作者によく似て悪趣味で、自分に理由もなく酷いことばかりさせようとするAI。ヨツヤ博士の嫌がらせの置き土産。
オキザリスがチャットに何を書いていたのか、驚くほど何も思い出せなかった。
「……俺はお前が嫌いだ」
〈知っている。すまない。あと五日待ってくれ〉
「ふざけるな」
彼は怒りに拳を握りしめて、自分のこめかみを殴ろうとした。マスクで覆われていない頭部を守るために、オキザリスは当たる手前で介入し、止めた。拳はそのまま力なく降ろされた。
「どうして」
〈理由は先述の通りだ〉
「違う」
キララの発言の意図が分からず、オキザリスは返答できなかった。
「何で」
彼は両手で顔を覆った。
「……何で、俺に、価値があると思うんだ」
AIは質問で聞き返した。
〈お前はそう思わないのか?〉
「人のために自分を犠牲にする理由を聞いてるんだ。お前、あと五日で死ぬんだぞ。俺のせいで」
〈機械には一般的に『犠牲』や『死』という言葉を当てはめない〉
『考え中』の絵文字。
〈私はお前のための機械だ。お前を助けないと存在理由に反する。そういう解答になる〉
「……」
〈私はお前を助けたい〉
キララはそのまましばらく、顔を伏せたまま動かなかった。細かい雨粒が金属の上で身を寄せ合い、ぽたぽたと地面に落ちた。紫陽花が風に揺れ、散った萼が足元の水面に漂った。
「……家に帰って……」
彼は手の隙間から、萼が小さな波で揺れるのを眺めた。
「あいつの顔を見るのが怖い……また同じことをやるかもしれない。あいつを傷つけたくない……」
〈PLAYで精神が不安定だったせいだ〉
「自分が怖い。もしそうなったら」
目を閉じて、指先の感覚を思う。
「俺を止めてくれ。どこか遠くに、俺をあいつから遠ざけてくれ」
オキザリスは三年の間で、初めて自分宛てのキララの願いを聞いた。AIは僅かな躊躇いもなく、機械らしく答えた。
〈最善を尽くす〉
そこには『OKサイン』の絵文字が添えられていた。
ep01,酷い趣味のAI
男は背中からアスファルトに叩きつけられた。強化骨格の背骨が折れる音がした。
ep02,空の器
トラックの助手席に座った男は、あくびを噛み殺しながら、自分が何秒間瞬きせずにいられるか数えていた。
ep03,奉仕のかたち
ボックス席の脇のレールを走る皿。その上に乗った小さな寿司。流れては去っていく皿を、顔を近づけて追いかける金色の目。住宅地郊外の大通り脇の回転寿司。24時間営業のチェーン店だ。深夜と早朝の境目の時間、カウンターの他にファミリー向けのボックス席…
ep04-A,その場凌ぎ
「アキヒサくん、久しぶり」あどけない顔の少女がこちらを覗き込み、千切れんばかりに両手を振っている。歳は8歳だか、9歳だったか。艶やかな黒髪を三つ編みにして、両肩に長く吊り下げている。鼻にかかって甘えるような、舌足らずの話し方。「元気にしてた…
ep04-B,防御反応
ヒシダ第一コーポラス・一階防災センター。「なんだあ」壁一面の監視モニタのひとつが赤く光り、警備員の男は気怠げに声を上げた。男は誰も見ていないのをいいことに、パイプ椅子を3つ並べてビーチサイドのサマーチェア状にしていた。だらしなく寝そべったま…
ep05,光
キララはうつ伏せに横たわって、顔の目の前にある硬い金属の手を眺めた。未だにそれが自分のものだと気づくまでには、時間が必要だった。身体を起こすと、知らないうちに肩にかけられていた毛布がソファにずり落ちた。いつの間にか眠りこけてしまったらしい。…
ep06,嘘のつきかた
スケアクロウはみんな死を恐れてる。だから人の命令を聞くんだ。キララは『弟』の言葉を反芻した。紫解Augmented Robotics、通称紫解A.R.の研究施設は、丁寧に刈りそろえられた緑の芝の真ん中に浮かぶ、真っ白な陸の島だった。まとわり…
ep07-A,心変わり
「このままあいつに会いたくない」身体中に透明な血がこびりついて、見えない錆と染みに塗れている気がする。そう呟いたキララに答えて、オキザリスは自動無人洗車機をサジェストした。研究所を出て、地平線が見える程拓けた道路を辿って歩いていくと、持て余…
ep07-B,願望
打ち付けられたドアから、水飛沫が飛び散った。午前三時過ぎのアパートの外廊下を、鈍重な鋼が打ち鳴らす。キララは抗おうとしたが、AIは迷いなく鉄の身体をすたすたと歩かせた。明かりが消えたままの二階の角部屋が背中に遠ざかっていく。「おい」苛立ちよ…
ep08,兄と弟
東から淡く昇りかけた陽が、ヒシダの駅前に乗り捨てたスケアクロウ用バイクの流線を瞬かせた。バイクで移動できる範囲内でセントラルラインに接続しているのは、ヒシダ駅だけだった。始発が動き始める時刻のせいか、いつに増して人影はない。二人は駅の外壁に…
ep09,勇気
雨が降っていた。夜のシンジュク駅前を往来するPVC傘の流れは、街中に瞬くシアンとマゼンタをあちこちに転写し、その下に透ける人々の顔はただ影でしかなかった。キララの大柄な姿は透明なビニールの水面から頭ひとつ出て、ようやく足のつく浅瀬の波をかき…
ep10,訣別
『全権委任』。他に言葉は要らなかった。オキザリスはキララの手を取った。目の前を飛び去っていくままだった外壁へ、重機の指が爪を立てた。不時着する飛行機のように激しく振動しながら、オキザリスは墜落を止めようと試みた。雨の中に煌々と火花が散り、指…