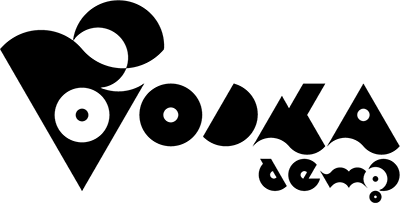打ち付けられたドアから、水飛沫が飛び散った。
午前三時過ぎのアパートの外廊下を、鈍重な鋼が打ち鳴らす。キララは抗おうとしたが、AIは迷いなく鉄の身体をすたすたと歩かせた。明かりが消えたままの二階の角部屋が背中に遠ざかっていく。
「おい」
苛立ちより戸惑いに近いリプライを投げる。
オキザリスは彼を操作し、四戸離れた外廊下の最端、下階へ降りる階段へ連れていこうとしているらしい。
「何してる、おい。どこに行くつもりだ」
〈命令を実行している〉
「何も頼んでない。ふざけるな」
〈傷つけそうになったら遠ざけろと〉
「俺があいつをぶん殴るとでも?」
〈お前は極度の緊張状態にある。PSIの影響を鑑みて、距離を取るべきだ〉
「部屋に戻れ、このポンコツ」
〈それはできない。お前を致命的な環境に晒し続ける訳にはいかない〉
「何の話だ」
〈自覚がないのか? ログを見るといい〉
オキザリスは『注目』の絵文字を投稿した。まるまるとした目玉の画像が大きく表示され、その後に人差し指を立てて上を突く『ポイント』の絵文字が続く。指し示された通り、キララはチャットのログを遡った。
〈キララ〉
〈行動不能〉
〈何が起きている?〉
〈キララ、応答しろ〉
〈メディカルチェック〉
〈フラットライン〉
〈生体部分に異常。機能不全〉
〈管理者権限による非常操作へ移行〉
〈蘇生措置〉
〈AED作動〉
〈人工心肺フルオートモード〉
〈心拍あり〉
〈メディカルチェック〉
〈復帰〉
〈キララ〉
〈キララ。無事なのか〉
〈何があった〉
〈キララ?〉
〈キララ!〉
未読の投稿が256件。
キララは息を呑んだ。この悪趣味で冷酷なAIから、可能な限り目を背け続けてきた。3年間の癖が染みついている。全く気づかなかった。
オキザリスは階段の前で立ち止まった。
〈お前は8分間、心肺停止の状態だった〉
空っぽのカズヒサの身体が、車の事故をテストするためのダミー人形そっくりになって、くるくると回転しながら落ちていったのを思い描いた。
彼は自分の身体を見下ろした。全長210センチメートルの、鋼の全身機械義肢。不思議でたまらなくなった。ソファの上にあったばかでかい鉄の塊と、自分の魂が、同じ線の上にあるなんて。
〈外部損傷もなし、生体部分の異常もなし。フラットラインの原因が特定できない。一体何があった? 無事なのか。何か知覚に異常はないか〉
あの時、とにかく孤独に押し潰されるのが恐ろしくて、何か言葉を発しようとした。チャットで叫ぼうとした。それでも、オキザリスのことなど考えもしなかった。
〈キララ〉
履歴に羅列されている自分の名前を、自分が無視し続けたこと、それどころか呼ばれていることに気づきさえしなかったことが、急に悲しくなった。
〈キララ?〉
「……俺は大丈夫だ。あいつのせいじゃない」
〈現状を把握したい〉
「お前に説明できる自信がない」
〈PSIの一種? 彼は脅威か?〉
「いや、違う。確かにあいつの力だ。でもそういうんじゃない。あいつは……」
「にいちゃん!!」
外廊下の端、開いた扉から『弟』はつんのめって飛び出した。深い夜の中に立つ闇の塊を見つけて、レインブーツの足音が響いた。キララはゆっくりと振り向く。剥き出しの顔。目と目が合う。思わず逸らして、靴を見る。視線の先で足が止まる。
「ねえ、なんで……!!」
青年は何か言おうと口を開いた。
「あ」
そして自分の手に視線を落とす。タブレットがない。
「……待って。ちょっと待ってて。そこ、絶対動かないで」
いつかガジェットショップの前でキララがやったのと同じジェスチャーをして、彼は振り返り振り返り、つまづきながら駆け戻っていった。
「あいつと話したい。何も介入しなくていい」
キララは胃の周りが針金で締め付けられるのを思い描いた。
「お前のおかげで、少しは頭が冷えた」
〈そうは思えないが〉
『うーん』の絵文字。
〈心拍数が上昇している。まともに会話できるのか?〉
「とにかく、しばらくほっといてくれ」
『OKサイン』の返答。
霧雨混じりの風が僅かな肌に吹き付ける。あの、ナイフの切っ先に似た冷たさを思う。今はもうただの数値だった。彼は自分の手を胸の前に広げて、それを見下ろした。
「さっき、何分って言った?」
〈8分〉
「そうか」
首を回して、アパートの下の世界を眺める。真っ黒な塗りつぶしと、僅かな灰色の陰影でできた海があった。キララは目を閉じた。暗闇の中に、インターフェースの無機の図形が残った。彼は動かなかった。
そのうち、心臓の刻みに似た靴の音が、雨水をはじきながら近づいてくるのが聞こえた。
「にいちゃん」
『弟』はタブレットを抱いて、アパートの一室分離れた場所で立ち止まった。外廊下の檻めいた手摺は雨と風を素通しにして、白い巻き毛を弄んだ。
「……ねえ。なんで」
「聞きたいのはこっちだ」
切れたまま長い間放置された電灯の下で、端末のバックライトが互いの姿に影を作る。
「俺はどこにでも行けと言ったんだ。お前が先に答えろ」
「にいちゃんに、返したかったから」
青年は悲しげに呟いた。
「綺麗だったから。昨日も、おとといも、朝の三時は一番静かで、いつも海が映ってた」
「テレビに、海が映ってた? それだけの理由で?」
「そう」
「冗談だろ」
『爆笑』の絵文字を投げつけて、キララは片手で顔を覆った。
「海を見たい」
「勝手に見に行け」
「あなたはそう願った」
覆った顔を手が滑り、そのまま口元まで下りる。
「……なに?」
「僕の記憶じゃない。でも、いつか誰かと、そう約束した。だから、全部、あなたに返したかった」
答える声には揺らぎがなかった。霧を探って確かな座標を指す、方位磁針の針に似ていた。
「………」
「たぶん、アキヒサと、だね」
「お前には関係ない」
キララは吐き捨てた。
「その約束をした奴らはもうどこにもいない。お前がやったことには何の意味もない。兄貴はそうやってこの世から消えた」
「僕はアキヒサじゃない」
「そうだろうな」
「僕はカズヒサでもない」
スケアクロウ素体の声はやたらに遠く聞こえた。全てを聞き届け、全てを受け入れる、無機物の声。ひとつ上のレイヤーから、他人の視点で自分自身を語る言葉。口のないスケアクロウたちの代弁。
「僕は道具。僕は印刷物。僕は工業製品」
機械の殻の内側で、ヒビだらけのガラスの水槽がとうとう砕けたような気がした。あらゆる無機と有機の残骸が肺の中に紛れ込んで、押し流された破片が胸を引き裂き、息をするたび血を吐くように思えた。
「僕は誰でもない。僕は空っぽで、失くす物なんて何もない。だから、あなたの願いを叶えられると思った。あなたは戻りたいと言った。生身の身体に」
ひと言を聞く度に、小さな美しい熱帯魚が一匹ずつ、胸の奥で潰れた。
「あなたの器になれると思った。それが僕がここにいる理由だと思った。……うまくいかなかったけど」
スケアクロウは尋ねた。
「どうして拒んだの」
鋭い雷鳴に対話は遮断された。雷ではなく、鉄の音だった。
「ふざけるな」
キララは手摺を殴り壊していた。腕を引くと、鉄棒は拳の形をかたどって曲がっていた。
「お前に何が分かる」
彼は衝動に任せて、もう一度それを振り下ろした。再び轟音が鉄をねじ曲げた。
「お前に俺の何が分かる!」
格子が十字構造を保ったまま吹き飛んだ。
「俺の願いは!」
キララは『弟』へ向き直った。重い足が怒りを踏みしめた。階下へ落ちた手摺が耳障りな激しい雑音を立てた。剥き出しの歯は強く食い縛り、赤い瞳は世界の何もかもを苛んで業火に燃えた。彼は叫んだ。
声は出なかった。無音の咆哮とともに、雨粒の音がふたりの間にぽつぽつと響いた。
「俺の」
タブレットが光った。
「……願いは」
スケアクロウ素体の顔を照らした。
「…………もう叶わない。二度と。兄さんは死んだ。帰ってこない」
水滴が装甲を伝って震えた。
「だから、海なんかどうだっていい。もうこのクソみたいな世界に、俺が欲しいものなんて何もない。分かってるはずなのに。諦められると思ったのに……」
ヒビだらけの画面に文字が奔り、蜘蛛の巣越しに瞬く光が天井に、水底の揺らぎの文様を描いた。
「……お前がもう一度と言ったとき、俺はもう一度、求めようとした。お前の言葉を受け入れようとした。泣いて、喚いて、どうか帰ってきて欲しいと願って、そのすぐ後に、もう一度お前を殺そうとした。もう一度あの色のある世界を取り戻せるなら、お前を犠牲にしてもいいと思った。お前から何もかも奪おうとした!」
砕けた模様の向こうで、悲鳴が刻まれた。
「たかが景色を見るために! 俺はそんな馬鹿な理由でお前を殺したくない!」
鋼の掌が強く握られ、金属の塊が顔に影を落とした。振り上げた右の拳は宙で止まり、やり場をなくして、そのままゆっくりと重機のような巨体の脇に戻った。
彼は呻いた。息をしながら溺れそうだった。こういう気持ちの時に相応しい絵文字が、リストの中には見つからなかった。長い沈黙の間に、建物の前の道を車が何台か通った。深海を探る探査機のライトのようにふたりを照らし、呻りと共に滑り去って行った。
水の上を歩く音がした。『弟』は、彼のそばまで来て、めちゃくちゃに折れ曲がった手摺の端に手をかけた。
「馬鹿な理由じゃないよ」
下から覗き込まれるのを恐れて、キララは目を背けた。
「それが、にいちゃんがくれたものだから」
青年は有象無象の建築物群から覗く空を見ていた。
「僕は、優しくて、綺麗なものが好きで、人の痛みに脆い、にいちゃんのことが好きだから」
僅かに目を伏せて、詰まった息を吐く。
「きっと、アキヒサもにいちゃんが好きだった。だから、そうしたんだと思う」
「兄さんは誰にでも手を差し伸べる人だった」
「そうかな。そうかもね。わかんないけど。……でも、多分、怖かったんだよ」
「怖い?」
「世界からあなたを、自分の光を失うのが」
針の先でなぞるように、胸に小さな明滅が走った。
光。
光か。
「……そうかもな」
キララは声帯のない喉で、は、と小さく笑った。
「二度と自分を物のように言うな。人間だ。お前も俺も」
「ごめん」
〈よく似ている〉
タブレットに送っているのとは別のチャットツリーに、オキザリスからのリプライが飛び込んだ。
〈正しくお前の複製だ〉
『歯車』の絵文字。
キララは何も答えなかった。
「片付けてくる。部屋で寝てろ」
と『弟』を家に押し込んで、アパートの一階に落ちた手摺を見に降りた。二階の反対端の部屋に住民がいなくてよかった、と彼は思った。玄関から出たら剥き出しだ。
「お前の有り難みがわかった」
〈それは光栄だ〉
オキザリスは『スマイル』の絵文字をつけた。
〈弁償代を計算するか?〉
「隣近所に菓子折りでも配って回るか」
各戸の玄関上には電灯がついているが、一階の端以外は全て蛍光灯が切れている。近くには街灯もない。真っ暗な中を、暗視カメラの視界で歩いた。
この建物の住民は皆、寛大な心の持ち主だった。隣の部屋からは時々何か怨念のこもった呪詛の読経が聞こえてくるし、二つ隣は部屋じゅうに『ハッピーになれる』植物を育てていて、蔦が這って窓側の外壁を侵蝕している。下の階のことはよく知らないが、駐車場のない建物なのにいつも窓を塞がれた黒塗りのバンが駐まっていて、明らかに何か他言しがたいことに使われている。暗黙の了解で、互いに互いが干渉するのを避けている。
慎ましく暮らしている分には文句を言われたことはない。それでも、眠りを阻害されるのは誰だって腹の立つものだ。手摺の残骸を持ち上げて、ブロック塀の端に寄せる。枝でも拾うようだったが、なるべく音の出ないよう慎重に置いた。
〈キララ〉
車一台駐めるくらいしかない、コンクリート張りの狭い敷地を歩いて階段へ戻ると、建物の入り口、ブロック塀の隙間でできた外門に、妙にぴかぴかと光る人影があるのが見えた。
銀色の流線型の腕が、錆びきった小さな門を押し開ける。鉄が小さく鳴いた。汎用のスケアクロウだ。治安維持局の装備を身につけている。
そりゃあ、夜中の住宅地であれだけでかい音がしたら、通報する真面目な奴もいるだろう。俺だったらする。彼は言い訳を考えながら、大人しく出て行こうとした。
そしてオキザリスが表示したレーダーを見て、足を止めた。円上の表示の中に三つの点。建物の隙間に打たれている。
〈治安維持局の配備パターンではない。襲撃を受けた時と相似〉
『いいね』のサムズアップで返した。
門の前のスケアクロウは立ち止まって、建物に背を向けて立った。何かを待っているようだった。すぐに治安維持局の威圧的なパトロール車両と、『シカイ・ピザ・デリ』の宅配バイクがそれぞれ道の左右からやってきて、アパートの前で止まった。
「精査しろ。何人いる」
〈12体〉
レーダーの表示範囲が狭まり、敷かれた地図の解像度が上がった。アパートを中央に据えて、光点が等間隔で歪な円を描いている。
「12!?」
〈訂正。さらに2体増えた。14だ〉
スケアクロウの位置を示す点で、繋ぎ絵のパズルが作れそうだった。点の位置はゆっくりと繋いだ縄を狭めていた。
キララは一段飛ばしに素早く階段を駆け上がった。質量のある金属が立てる耳障りな音に、スケアクロウは振り向いたが、まだその場に留まっている。顔のない顔は、機械義肢の上に乗っている疲れ切った白い髪の頭を凝視した。ハンドガンを部屋へ置いてきたことを自責しながら、外廊下を走り、住み慣れた自分の巣へ飛び込んだ。
玄関の戸が再び大きな音を立て、『弟』はソファの上で跳ね上がった。
「にいちゃん?」
玄関のすぐ脇にある棚を横倒しにして扉を塞ぎ、冷蔵庫や椅子を積み上げて補強する。
「何? どうしたの……」
「荷物まとめろ。今すぐ」
タブレットの中の簡潔な投稿と、特殊部隊のハンドサインめいたシンプルなジェスチャーで、青年は緊急性を察した。
『弟』がテレビの脇の棚を漁っている間に、即席のバリケードががたん、と大きな音を立てた。キララは自分の身体に武装をくくりつけながら、背中でそれを押さえた。床に転がったままだったマスクを拾い上げて素早く被る。
「何で家が分かった? むしろ何で今なんだ。時間ならいくらでもあっただろうが」
〈心当たりは〉
「ある。あれは全部こいつを狙ってる」
スケアクロウたちの望みはいくらでも理解できた。
「あれは全部俺だ」
『生身の身体に恋い焦がれている』。
オキザリスの言葉が繋がった。〈よく似ている。正しくお前の複製だ〉。光に群がる蛾。
「さっき、ここで強い力を使った。それでESPの共鳴を感じたのかもしれない……それか、こないだのピザ屋だ」
〈物理的な可能性も〉
オキザリスは『弟』の首の後ろを赤くハイライトした。まだ追跡パッチが貼ってあった。羽織ったレインコートのポケットに慌てて物を詰め込んでいるところに近づいて、指でそれをつついた。
「えっ? ……えっ、なに?」
青年が戸惑いながら襟足を探ると、巻き毛の中から、テープで貼られたボタン大の小さなチップが出てきた。キララはそれをつまみ上げて、指の先で潰した。
離れたそばから、ひときわ大きくバリケードが揺れた。
〈窓から脱出できるが、下方に七体待機している〉
「こいつを守りたい。どうしたらいい?」
〈私に操作権を〉
キララは躊躇なく『全権委任』のコマンドを与えた。
〈銃器の許可も〉
「わかった、好きに撃て。こないだの話は取り消す」
〈では、始めよう〉
オキザリスはキララのくくりつけたガンベルトから、両手にハンドガンを抜いた。等速直線移動で部屋を横断すると、ソファを足掛けにして、開けっぱなしだった窓から腕だけ突き出す。両手の引き金を引き、二度の銃声。何かが倒れる音。
〈2。奇襲する〉
重機の身体はそのまま、黒い長方形の外に身を投げた。
「にいちゃん!?」
〈お前の『弟』に説明を。合図をしたら降りてくるように〉
合図も何もなく突然空中に放り出されて、キララは一瞬、かつてアキヒサと過ごした何気ない日々を高速で振り返った。
今、高いところから、落ちた。
いや落ち着け、たかが二階だ。
身体の中身が緊張で圧縮されてキューブ状になった気がした。
オキザリスは腕を顔の前で交差させ、頭部の防御を図った。両足が地面に触れると同時に、機械義肢の踵の構造が展開し、着地の衝撃を吸収した。地獄に金床を落としたような音がして、足下のコンクリートが大きく抉れた。
落ちてきたのが『器』でないことを確認する僅かな間のあと、暗闇から激しくフラッシュが焚かれた。豪雨の日の屋根の音とともに、鉛の嵐が遅れて全身をノックする。自分を取り囲むスケアクロウたちの、銃を構えた姿が腕越しに見えた。
「合図するまで絶対に顔出すな」
キララにはそう打つのがやっとだった。
アサルトライフルのリロードの間に、手前にいたスケアクロウが躍り出て、両手を翳した。
〈3〉
オキザリスはコンテンポラリーダンスでも踊るように片足を高く振り上げ、開いたコンパスの姿勢で回った。最前線にいた一体の頭部を捉えて吹き飛ばした。
〈4〉
巨腕がもう一体の首も攫った。回転の勢いそのままに足は背中にあったアパートの壁を蹴り、空中に身体を持ち上げ、キララは自分が地面と垂直になって走っているのを感じた。建物の壁を不可視の力が追った。窓から溢れて這う『ハッピー植物』の蔦の隙間に、鉄球をぶつけたような跡がいくつもついた。オキザリスは重力を無視してスケアクロウたちの頭上を通り抜け、両手の銃の引き金を引いた。
〈5、6〉
身を翻して着地。黒いコートが翻ると同時に、最後の一体が倒れた。
〈7。今が機会だ。すぐに正面から増援が来る〉
キララは『OKサイン』で返答した。
「片付いた。降りてこい」
折り重なったスケアクロウの死体を見ないようにしながら、自分の部屋の真下まで駆け戻った。見上げると、口をきつく結んだ『弟』が、不安げにおずおずと顔を覗かせた。
「窓の横に雨樋がある。お前なら伝って降りられる」
身を乗り出して見回すと、窓のすぐ脇に、確かに蔦の絡んだ細いパイプが通っている。
「大丈夫だ、大した高さじゃない。落ちたら受け止めてやる」
青年は下を見る。硬い腕を広げて見守っている姿が、やたらと小さく見える。
〈急いだほうがいい〉
キララは待った。窓の向こうに、タブレットと下を見比べて、意を決して頷くのが見えた。直後に轟音。『弟』は背を向けて、窓枠の影に消えた。
「どうした」
〈ドアが破られた〉
「来ないで!」
悲鳴が聞こえた。クソ、と舌打ちする。
「ここから登れるか?」
〈加速が足りない〉
キララは建物の表側に走った。数体のスケアクロウが立ち塞がる隙間を、仰向けのまま身を低く蹴るように滑って躱す。アスファルトと足の摩擦で火花が散り、身体を捻って立ち上がりながら、AIは見もせずにヘッドショットを決めた。
門を抜け、手摺の曲がった外階段を全力で走り抜け、開け放たれたドアに悪寒を覚えながら自分の部屋へ向かった。キララは祈った。
扉の内側からスケアクロウが海老反りに吹っ飛んできて、何を祈ったか分からなくなった。PSIの強い波状のうねりを感じた。銀の装甲と、見覚えのある棚と冷蔵庫とが絡まりながら宙を舞い、手摺を越え、一階に落ちてけたたましい騒音を立てた。
「にいちゃん!!」
飛び出してきた『弟』はキララの胸にしがみついた。
「ごめん。怖くなかったのに。ずっと怖いなんて思わなかったのに。なんで」
関節と逆の方向に腕のねじ曲がったスケアクロウがよろめきながら後に続いた。オキザリスはそれを蹴り飛ばし、頭を踏み壊した。
「ごめん、にいちゃん、ごめん、家が」
キララは怯えきって震える青年を身体の前に抱きかかえ、振り返りもせず走った。
残してきたもののことが頭の中で翻った。三年の間に、ひとりでは飲み込みきれなかったもの。最初のボーナスで買った机。片付けられないまま放っておいた服の束。椅子を引いた同僚の名刺。棚の奥に仕舞い込んだ古いティーバッグ。どうでもいい。もう必要のないものだ。
半減したレーダーの点が、外周からまたぽつぽつと増えて迫っていることに気づいた。門を潜り、アパートの前の道に出て、すぐそばから何かのエンジンの音。
「逃げて……みんなが来る……」
でもどこへ? もう帰る場所はない。どこでもいい、どこか、落ち着ける場所へ。
「分かってる。何か足が要る」
オキザリスは周囲を探した。赤い走査線が地形の法線に沿って走る。道の脇に駐められたスケアクロウ用バイクと、ピザ屋の荷台つきバイク、治安維持局の人員運搬車両がハイライトされた。
〈お前の体格を考慮する場合、治安維持局の車両しかない。しかし特殊な盗難防止ロックがある。取り外すのは困難だ〉
「ハックできる自信は?」
〈善処はするが、推奨できない〉
キララは首を回して自分で探した。暗視カメラの見通しのきかない視界ではろくに見えなかった。
「にいちゃん、おろして」
『弟』は鋼の腕を滑り降り、靴下のまま地面に足をつけた。イルカのような流線形のバイクに駆け寄って、カバーに隠れたグリップを両手で握った。バイクの車輪の周囲が淡く青いLEDで照らされ、速度を表す小さなインターフェースに『搭乗権認証:SK1250』の文字が表示された。
「大丈夫、僕運転できる。乗って!」
おい、乗るったって、どうやって。身振りで伝える彼に、『弟』は闇の中を指さした。
「あれ!」
キララが目を凝らすと、いつも一階の住民がバンを駐めているあたりに、牽引用の厳つい台車が転がしてあるのが見えた。
〈名案だ〉
オキザリスは台車のハンドルについた連結チェーンを赤く強調した。
カサミの町の中心を通る大通りを、銀色のバイクが走り抜けた。他の日と比べるまでもなく、車通りは殆どない。
スケアクロウのために設計され、スケアクロウの装甲と一体になって見える特徴的なデザインの車体。装甲と同じ著名なカーデザイナーの手によるものだと、いつかニュースで喧伝していた。電気駆動で環境に優しく、騒音もなし。
その後ろには、大きく頑丈な板にハンドルと4つ車輪がついているだけの台車が引きずられている。チェーンでくくりつけられた台車はカーブや段差のたびに大きく揺さぶられ、工事現場でも聞かないような騒音と火花が好き放題撒き散らされた。キララは台車の上に後ろを見る形で跪き、高速の濁流になって過ぎ去る地面を片手で漕いで均衡を保った。暗視モードを解除した視界の隅を、煌々とした街灯が無数に光の尾を残した。
追ってきた同じ型のバイクを、自分が認識する遙か前にオキザリスが撃ち抜いた。ハンドガンが何度も手持ち花火のように鮮やかに弾け、町を抜ける頃には追っ手を撒いたようだった。
「にいちゃん、どこに行けばいいの」
『弟』は前を向いたまま叫んだ。返事のしようがなかった。声が届いているかどうか振り返ることなく、彼は続けた。
「スケアクロウは世界中にもっとたくさん増えるんだって、ニュースで言ってた。みんな身体を欲しがってる。もう僕の逃げられる場所はない。にいちゃんが諦めたって、僕には時間がない」
キララは揺れる台車の上で俯いた。気を失いそうな程の細かく激しい振動で頭が揺さぶられ、流れ去っていく景色を見ることもできそうになかった。海浜地帯の新しい工場。3万体の増産。紛争地帯への輸出。ヨツヤ博士の言葉を思い出す。「フルプリントには存在してもらっちゃ困るんだ」。たとえ逃げ切れたとしても、紫解がこいつを見つけたとき、どうなるかはわかりきっている。
この世にのどかで平和な場所なんて、どこにもない。
「ねえ。この世界には僕の居場所はない。みんなが僕の器を求めるなら、それなら僕はにいちゃんがいい」
名前さえない青年は叫んだ。
「にいちゃんの器になりたい。にいちゃんとずっと一緒にいたい。にいちゃんと光を見たい。にいちゃんの目に、手に、肌に、声になりたい!」
この、バカ。キララは心の中で呟いた。
光。あの日のアキヒサの気持ちが今初めて、僅かにだけ分かった気がした。俺にはお前が光なんだ。このクソみたいな暗闇を照らす、たったひとつの光。
そうだ。キララは答えた。俺の願いは。
身体を失うよりも前、アキヒサがいなくなるよりももっと、ずっと前に諦めたつもりだったもの。光。
初めて親に殴られたあの日、自分のいる場所が濁り淀みきった泥の底だと気づいた日からずっと、苦しくてたまらなかった。光のあるところに帰りたかった。
この世にはまともな良いことなんて何ひとつない。そう分かった時からずっと真っ暗で、自分がどこにいるのかも分からなかった。どうしたら触れられるのか、どうしたら戻れるのか、ずっと知りたかった。
キララは目を閉じた。目蓋の裏には、眩い残像が刻まれていた。
俺の願いは、もう二度と、光を見失わないことだ。
カズヒサ、ごめん。
それは自分自身の言葉だと、彼は気づいた。
自分を守るために、誰かを傷つけないために、いつも自分自身を殺してきた。誰かの望み通りに、ひたすらに従順に、全ての衝動と望みを押し殺してきた。
子を虐げる両親。悲鳴に耳も目も塞ぐ大人。自分の責任から目を逸らし続ける人々。ドブ川の水車に繋がれた歯車。そう作り替えられた自分自身。そういうものだ、と諦め続けてきた。そして、いつしか本当に擦り潰れて消えてしまっていた。
この世は大きな濁流でできていて、逆らうことはできない。どうしようもない。信じられるものなんてない。誰も助けてくれやしない。自分には何も変えられない。
ごめん、カズヒサ。ごめん。
彼は宥めるように囁いた。
これで最後にしよう。それがきっと、兄さんの望んだことだから。
キララは片手で地面を押さえつけ、もう片手を上げて振った。合図に気づいて、『弟』は速度をゆっくり落とし、バイクを道の脇に駐めた。ふたつ隣の町まで来ていた。見たことのない土地だったが、カサミと代わり映えはしなかった。
キララは静止した台車の上に座ったまま、通り過ぎてきた風景を遠く眺めた。
「なあ。それが本当にお前の望みなら」
『弟』はバイクに跨がったまま、タブレットを取って覗き込んだ。
「俺の願いは……お前と同じだ。お前と、光を見ることだ」
スケアクロウ素体は少しだけ驚いて、口を開けた。肩越しに振り返り、キララの横顔を見て、紫陽花を眺めたのと同じように微笑んだ。
「……僕の力じゃうまくいかなかった。でも、方法があるんだよね」
「ああ」
「にいちゃんは準備に時間がかかるって言った。良い方法を知ってるんだよね」
「ああ。そうだ。知り合いがいるんだ」
キララは頷いた。
「セントラルに行こう。それで、願いを叶えよう」
〈博士の元へ行くのか〉
意図を確かめるように、別のツリーにリプライがついた。彼は『ウインク』の絵文字を返した。
「トラクターになるのも悪くない」
それからリアクションのリストの中を下の方までくまなく探して、『パセリ』の絵文字を添えた。