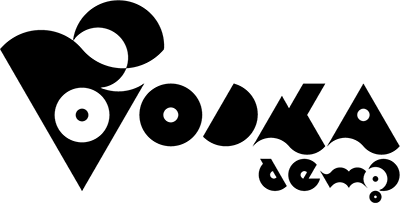雨が降っていた。
夜のシンジュク駅前を往来するPVC傘の流れは、街中に瞬くシアンとマゼンタをあちこちに転写し、その下に透ける人々の顔はただ影でしかなかった。
キララの大柄な姿は透明なビニールの水面から頭ひとつ出て、ようやく足のつく浅瀬の波をかきわけて歩いた。雨粒やすれ違う傘の先に肩を叩かれ咎められながら、鋼の身体は流れに逆らって、駅前のコインロッカーに辿り着いた。
改札すぐそばの壁一面を、プラスチックと金属でできた正方形のブロックが埋めている。カサミやヒシダの駅前にあったのと同じ規格のものが、置ける数だけ乱暴にコピー&ペーストされていた。
インターフェースが中段の五つの箱を赤く強調した。左端のものに近づき、パスコードでロッカーを開ける。中にはサイケデリックで扇情的なラベルの貼られた小さな瓶が置かれていた。キララはそれを軽く傾けて、中にPLAYの錠剤が詰まっていることを確かめると、コートの懐に入れた。
隣のロッカーの中には、クラフト紙の封筒があった。隣にも封筒、その隣にはまた別の封筒。封を開けて覗くと、黒い目隠しの紙包みが入れ子になっている。奥に小さな硬いカードが入っていた。
「本物なのか」
〈キーの出自を保証する画像が添付されている。IDは照合済〉
社員証の写真がチャットに貼り付けられた。それぞれのカードの持ち主のもので、役職とカードキーの有効期限が記されている。確かに紫解バイオロジー本社の関係者でなければ知り得ない情報だった。
「博士の仕掛けた罠だったら? この間みたいに」
〈我々には察知できない。避けるのは不可能だ。だが、ドアが開かなければ別の方法を使う〉
「なるほど」
画像を一瞥する。認知モザイクのかかった顔写真。どこの誰とも分からない。キララは呟いた。
「大して変わらないな」
〈不明な比較対象〉
「なんでもない。独り言だ」
『OKサイン』の絵文字。
三枚のカードキーをポケットに入れ、雑踏を肩越しに振り返る。人の群れ、人の群れ、人の群れ。
セントラルもエクストラも同じだ。数がやたらと多いだけで。
そこにあるのは個人ではなく、ラベルをつけられた情報の流動だ。本当は違う。名前も顔も声もある。誰にも聞き届けられないだけ。何を見ても知らないふりをして、目も耳も塞いで、傘の下に身を潜めている。
名もなき部品でいるのは正しい選択だ…… 自分さえ耐え続ければ誰も傷つかない。水槽の中の魚の群れが、一匹落ちても風景は変わらない。
世界は鏡だ。傷つかなければ傷つけられない。
「なあ。何で皆、チャットとロッカーを使うんだと思う」
〈匿名性〉
オキザリスはごくシンプルに答えた。キララは『いいね』の絵文字で返す。
「それに、誰かになれる」
〈矛盾している〉
「セントラルラインの切符がやたら高い理由は分かるだろ」
〈人口の流出を防ぐため〉
「そうだ。人が流れたら、世界は変わる。変わらないようにしてるんだ。世界はどうしようもなく磨り減ってる。少しでも傾いたら何もかも崩れる」
『歯車』の絵文字を添える。
「生き延びるには、世界を正しく回し続けるには、人は道具になるしかない。それは苦痛だ。だから自分だけの罪が欲しい。デカいものに痕を残したい。バレない程度にちょっとだけ。罰は受けたくないからだ」
〈意図がわからない〉
「意味なんかない。自分は本当は道具なんかじゃない、と証明したいだけだ。それがどんな結果に繋がるかは知ったこっちゃない。このキーをよこした奴も、PLAYをひと瓶ロッカーに突っ込んだ奴も。何が起きるかなんてどうでもいい。面白ければ何でもいい。火が見られれば」
ロッカーの残った最後の扉からは、ハンドガンの弾がひとかたまり出てきた。
「自分は火傷を負いたくない。だから誰かにやらせる。会ったこともない他人に。誰でもいいんだ」
三年前はこんな風になるなんて思ってもみなかった。胴に巻き付けたバックパックに突っ込んで、キララは駅に背を向けて歩いた。
濡れたアスファルトに自分の姿が映る。黒いマスクの奥に顔が見えた気がした。白い巻き毛。金色の瞳。銀色の流線型。その後ろに聳え立つ摩天楼、蛍光灯の生きた電光、数万通りの名前と声のある人々。
それから、コートを羽織った機械義肢の身体。
ごめん。
彼はもう一度、心に刻んだ。
これから起きるのは、酷いことだ。足取りは文字通り重かった。
傘を差して歩く人々の遙か上空で、雨霧の中を冷えたサーチライトが左右に揺らめく。藤の紋とDNAを掛け合わせた意匠が青白く浮かび上がった。紫解社のシンボルマークだ。
紫解バイオロジー本社には、シンジュク西地区に連なる超高層建築物の中でも特に際立つ存在感があった。厚いガラスで四方を包んだ完璧な壁。その奥ではフラクタル文様でできた有機的に発光するもやが蠢く。途方もなく巨大な濁った水槽。百二十階建てのビルを足元から見上げると、上層は実在するかも曖昧で、ぼやけて見えた。
一階の強化自動ドアが、備品用の埋め込みICチップを感知して開いた。入り口の検査ゲートは銃火器に反応して警報を鳴らした。立ちはだかったスケアクロウが頭を撃ち抜かれて倒れた。銃声。もう一人。銃声。もう一人。
エレベータホールに繋がる手前の空間には、『当社の主製品』として、展示台の上にマイモの置物が飾られていた。めいめいの仕事のためにそこにいた人々は、騒音と警報にざわめいた。エントランスに目を向けると、やたらと図体のでかいアンドロイドが立っている。
ロボットの肩に刻まれた紋章を見て、ひとりは「ああ」と思った。あとの数人は何も思わなかった。紫解のビルに、紫解の備品がいても何もおかしくはない。
オキザリスは無防備な社員に、ハンドガンを向けた。
「よせ。撃つな」
〈何故?〉
ようやく何が起きているのか理解して、人々は悲鳴を上げて正面玄関へ殺到した。逃げ惑う彼らを無視してすり抜け、キララは奥へ歩き去ろうとした。背中に強い衝撃。
振り返ると、スーツ姿の営業らしき男が何か喚き散らしながら、マイモの置物を振りかぶって殴りかかってきた。
本物にそっくりな毛で覆われた、羽を広げた姿のやたらと精巧な置物だった。
キララは思わず払いのけた。巨腕に人体はたやすく吹き飛ばされ、ちょうどその先に展示台の角があった。頭を打った男はそのまま動かなくなった。
無彩色の視界で、倒れ込んだ頭部から液体がゆっくり広がっていくのが見えた。自分が何をしたのかを神経が指の先から頭に伝えるまでの間、キララはぽかんと突っ立っていた。ひとり殺した。
激しい吐き気が彼を襲った。
〈効率を考えるべきだ。非武装の人間も無害ではない。警備を呼ばれるのは脅威だ〉
自責に潰された胃が鈍く悶え、食道を逆流して口の中に不快な酸っぱさが込み上げる気がした。
〈認識を改めたほうがいい〉
「わかってる……」
拳についた白い毛を振り払い、握り締める。紫解のゼリーの不味さもわからないはずなのに、まだ胃液の味がする。
自分が起こした混乱と悲鳴を後に、彼はエレベータホールへ進んだ。
向かい合った四基のエレベータのうち、左奥をオキザリスが赤色で指す。コインロッカーから手に入れたカードキーをボタン横の端末に通すと、扉はいとも簡単に開いた。
高速で上昇していくエレベータの籠の中で、キララはこの狭い箱が真っ直ぐ最上階に着いてくれることを、ひたすらに願った。非常事態を示すアラートがけたたましく鳴り響き、建物中を激しくかき乱している。自分の身体の金属と、ざらざらしたアルミ製の壁との間で、警告ランプが乱反射した。
頼むから、このまま何事もなく、誰にも会わずに済んでくれ。
〈緊急警報を受信したため、エレベータは当階で止まります〉
平坦な女声アナウンスが無慈悲に告げた。
「クソ」
〈指定された避難経路をご利用ください〉
エレベータは三十二階で急停止し、ドアが開いた。隠れていたロッカーをこじ開けられた気分だった。オキザリスはこの階のミニマップを表示し、点線で経路を指した。
〈廊下を抜けて反対側に、上層階行きの別のエレベータがある〉
頷いて籠の外に出る。
降りた先は味気ない、狭苦しい廊下だった。間髪入れずに、戦闘AIは警告を頭に突っ込んだ。
〈接敵する〉
ミニマップが、廊下の奥からふたつ駆け寄ってくる光点を強調した。
知らないオフィスフロアに向けて、ハンドガンを構える。行き止まりには複層のセキュリティドア。向こう側から開閉音が近づいてくる。3、2、1。扉が左右に開いた瞬間、オキザリスは弾丸を二発放ち、的確に相手の頭部を捉えた。
銀色の流線型が倒れるのを見て、キララは安堵した。スケアクロウで良かった。
「目視!」
そう思った直後、奥から人の声がした。自動扉が閉じかけたが、倒れたスケアクロウを挟み込んで止まった。
「アンドロイド一体のようです」
「研究フロアに通すな」
キララは死体を押し退けて、ドアの片側を遮蔽物にして身を隠した。オキザリスは捕捉した警備兵の画像を分析した。相手は四人。セラミックプレートの入った防弾ジャケットに身を包み、小型プラズマ砲を抱えている。
〈紫解専属の警備兵だ。重武装している〉
「迂回路は」
〈一本道だ。突破するしかない〉
廊下の反対側で、ブーツの固い足音が床を叩く。
「プラズマ砲、射撃用意」
〈キララ、危険だ〉
「構え」
最大級の警戒アラートが視界を真っ赤に染めた。
「撃て!」
AIに縛られ、全身がぴたりと静止した。頭のすぐ横で、乳白色の擦りガラスでできた頑強なセキュリティドアの、一点が赤熱していた。みるみるうちにそこから溶け広がって穴が空き、凄まじいエネルギー熱線がキララのマスクの鼻先を通り抜けた。
声があったら悲鳴が出た。
〈被弾は避けられない。だが当たれば致命傷だ〉
熱線はエレベータまで貫通し、アルミを焦がしてから消えた。腰を抜かしてへたり込むのを、オキザリスが許さなかった。
〈こちらが先に相手を無力化するしかない〉
「だったらどうする」
算出中らしく、AIは答えない。
「どうやって。なあ、おい。オキザリス」
返答なし。
指先が氷になった気がした。身体の末端で命が消える準備をしている。キララは自分の周りの空気が震えるのを感じた。ぱき、ぱきと、何かにヒビの入る音。
「オキザリス!」
「構え」
廊下の奥から再び号令。
死にたくない。キララは恐怖を手繰り掻き寄せた。死。キャンディみたいに溶ける自分の装甲。死のイメージ。
「撃て……」
プラズマ砲の発射より先に、穴の空いた擦りガラスがその場で砕け散った。記憶を重ねる。死。墜落。三十階。離さなきゃ。強風。手を。どうして、何で。
アキヒサの手を振り払い、鋼の掌を廊下の先に翳す。不可視の力が狭い通路に迸り、警備兵たちを圧した。
「何だ」
自分の手より向こう側の空気が圧縮され、壁やガラスの小さな欠片が床から数センチ浮かんでいる。キララは奥歯を食い縛った。死。
「ああああッ!」
廊下の先で何かが潰れた。
他人の苦痛の声を聞いて、固めた恐怖がぼろぼろと崩れた。PSIの影響から外れ、重力から切り離されていたものが床に落ちて散る。警備兵は内側に破裂した同僚の姿を見て喚き、プラズマ砲のトリガーを引いた。
しかしオキザリスには十分だった。自分の意思ではない駆動を体内に感じ、キララはそれに身を任せた。屈んで熱線を避け、前転、立ち上がり際に強く床を蹴り、硬い右肩を前に突き出して突進。逃げ場のない狭い廊下にホイールローダーが突っ込む。フロアが揺れ、人を撥ねる感触。血溜まりを踏みつけて、開きっぱなしのセキュリティドアを越え、速度は落ちず、壁が迫り、曲がり角にぶつかった。
最奥の壁に押しつける瞬間、防護ヘルメットを被った相手の怯える目が見えた。卵の殻に圧力がかかり、砕け、柔らかい身に鋼が届き、それを押し潰し、圧殺していく感触の全てを、キララの器官は数値で捉えた。衝撃。瞬きの後には、服を着た肉塊と血飛沫が壁にへばりついていた。
オキザリスは振り返った。突進をかろうじて避けた最後のひとりが、複雑骨折した死体の横で、床に這いつくばって震えている。
鉄塊が歩み寄る。
〈生かしておくべきではない〉
見上げきれないほどの巨体。赤い警告灯が輪郭を鋭く照らす。滴る粘液。影が覆い被さる。警備兵は口元のヘッドセットマイクに縋った。
「こちら、こちら甲班、三十二階に……」
オキザリスが右腕を掲げた。キララは、その手刀に自我を添えて振り下ろした。頭がバレーボールみたいに飛んでいった。色のない鮮血がマスクをべっとり覆った。
キララは吐いた。
この身体になって、初めて固形物を口にしたときの事を思い出した。今でも忘れられない。
三年前、研究所を出て、行くあてもなく家に帰った。冷蔵庫の中で、最後の夜食の残りが腐っていた。生身だった最後の日の朝に、帰ったら食べよう、とラップをかけて取っておいた惣菜かなにか。乾いた泥の塊に変わっていて、もともと何だったのかも思い出せなかった。帰宅までの数ヶ月の間に、何もかも変わり果ててしまった。
机の上にビスケットの箱があった。ただただ懐かしかった。〈食事には液体食料パックを強く推奨する〉とオキザリスは繰り返したが、キララはそれを無視して食べた。喉にはまともに嚥下する機能もない。小さなビスケットを一枚つまんで飲み込むのに、何時間もかかった。それでも、食べたら戻れる気がした。戻りたかった。
身体の内側の、もうどこからどこまでが自分のものだったかも分からない程ごちゃ混ぜになってしまった器官が、悶え苦しんで裏返ろうとした。痛みがないのが余計に気持ち悪かった。クラインの壺だか、管だか何だったか、全身がそれになった。表と裏が八の字に繋がって、理屈を無視してキャタピラみたいにぐるぐる回っている。異物を排出しようとする機構が過剰に働き、神経が誤解を繰り返す。何も吐けないのに脳は吐き続けている。
あの時のビスケットと同じ感覚。
〈キララ。大丈夫か〉
オキザリスが全ての操作権を返した途端、立っていられなくなった。壁にもたれかかって喘ぐ。
「気分が悪い」
〈生体部に異常は見られない〉
「わかってる」
これまでに何人ゴミ袋に詰めたか覚えてもいない。もっと酷い死体だって見た。だが、それをやってきたのはオキザリスだった。自分は仕方なく……意思に反して……従っていただけ。そのはずだった。俺が殺した。俺が。
「ごめん……」
違う。今までだってずっとそうだった。
箸を握るのは、ストローの先にいるのは、自分だ。これまでも、これからも。ここに来ようと言ったのも、これからしようとしていることも、全部俺の意思だ。
〈キララ?〉
「なんでもない」
キララは首を振った。なんとか身を起こして、インターフェースの赤い導線に向かって歩く。ここまできて、今更人を殺してビビってるなんてお笑い草だ。
「大丈夫だ」
何度も口の中で唱え、自分に言い聞かせた。
オキザリスに従って先へ進むと、次のエレベータが見えた。扉が開くと、奥の一面が鏡になっていた。キララはそこに映る自分の姿を見た。酸化しはじめた血のせいか、鈍くべたつき、どす黒く見えた。
「俺は悪の帝王になる」
アキヒサがそんな風に言い出したのは、八歳くらいの頃だ。
カサミの町には相変わらず雨が降っていて、カズヒサは窓の外を見ていた。ガラスの奇妙な位置に影が反射して、何だろう、と後ろを見た。
「兄ちゃん、なにしてんの」
アキヒサは椅子の上に片足立ちで腕を組んでいた。キャスターつきの椅子の足が軋んで鳴いている。
「あぶないよ」
「大丈夫だって。見てろよ、かっこよく飛び降りるから」
お手製のマントを首に巻き付けて、どうやったら一番見栄えがするか、試行錯誤しているらしかった。黒い5Lゴミ袋を切り開いて器用に作ったマントが、蛍光灯の下で威厳なくテカテカしていたのを覚えている。
ゴミ袋のマントはアキヒサの期待通りにはうまく靡かなかった。床に降りたときのどすん、という鈍い衝撃が、すぐ隣にいたカズヒサにも響いた。
「待った。今のなし。ダサかった」
「悪いほうがいいの? ヒーローじゃなくて」
「正義の味方なんかフィクションだろ。悪の帝王は実在する」
「そうかな」
僕には兄ちゃんがいるけど。そう思って、何となく口には出さなかった。
「それにヒーローは悩むけど、悪役は悩まない。ポリシーが決まってんだよ」
「たとえば?」
「じゃあさ。ここに人がいっぱい住んでるとするだろ」
アキヒサは弟の横に屈んで、毛足の長いカーペットに指で円を描いた。
「それで、ここに電車が通ってる。爆弾がいっぱい乗ってて、運転してるAIが暴走して、誰にも止められないくらいめちゃくちゃ速く走ってる……」
カーペットの上に描かれたのは、『トロッコ問題』と呼ばれる話だった。
電車の行く先は二股のレールに分かれている。片方のレールの先には町がある。もう片方のレールの先には空き地。そして、その切り替えレバーは自分に委ねられている。
「何もしなければ電車は空き地に行く。でもさ」
アキヒサは空き地行きのレールの上に、印をひとつ付け足した。
「ここに俺がいて、レールに靴の紐がひっかかっちゃって、逃げられない。このままだと轢かれる」
「やだ。頑張って逃げてよ」
「ほっといたら俺は死んじゃう。でも、レバーを切り替えたら人がたくさん死ぬ。お前ならどうする?」
「そんな」
カズヒサは口篭もった。
「兄ちゃんが。やだよ」
「泣くなよ」
「兄ちゃんが助かるほうがいいよ」
「でも、町が一個吹っ飛んじゃうんだぜ。みんなお前のことを恨んだり呪ったりする。今よりもっといじめられたり殴られたりする。最悪、後ろから刺されて殺されるかも」
「それもやだ」
「じゃあ、どうする?」
どう答えたのかは覚えていない。結局、決められなかったんだと思う。
「わかんないよな。こんなクソみたいな問題」
アキヒサは笑った。
「でもさ。でも」
笑いながら、急にきり、と表情を引き締めて、弟を睨んだ。
「悪の帝王ならそんな迷い方しない。悪の帝王は、一番合理的な判断を、感情抜きで決める」
それは一番『悪の帝王っぽい』決め顔らしかった。
「悪の帝王は自分の目的のためなら何でもやる」
「目的?」
「世界征服だ。世界を自分のものにするってこと。レバーがそこらじゅうにいっぱいあることになる」
「やだよ」
「帝王は全部好きなように、自分のやりたいように決める。レバーを傾けても、町が爆発しても、帝王は全然平気なんだ。自分がそうするべきだって信じてるから。傷ついたり反省したりなんて絶対しない」
「兄ちゃんは、そういう風になりたいの?」
「そうだよ。そうだろ。だって、今は……」
両手を大きく広げて、そこでアキヒサは言葉を切った。目と目が合って、言わんとしていることが分かって、ふたりで黙った。
マントの裾から見えた腕には、煙草の燃え殻を押しつけられた痕がいくつもあった。白い肌に青痣が痛々しく目立った。
「……誰も、電車が走ってるとこすら見たがらない」
ばつが悪そうに、アキヒサは身体にゴミ袋の余りを巻き付けた。
「正義の味方なんていない。だから、俺が全部決める。俺が悪の帝王になって、世界を征服するんだ」
同じ顔、同じ背丈。シャツの下にはお互い数え切れないほど傷があったが、アキヒサのほうが多かった。いつも弟を庇おうとするせいで。
昔のことがやたらと脳裏にちらついた。
夢見るだけなら子供でもできる。正義の味方は、いた。今はもういない。
悪の帝王はどうだ?
右手の掌でマスクを覆い、横向きに拭う。血の跡が轍になった。
最初の吐き気は忘れた。何度も警備兵と戦ううちに死者を数えきれなくなった。
戦闘と上昇と突破を繰り返して、キララは最後のエレベータに乗り込んだ。
〈ヨツヤ博士は中層の研究フロアに部屋を与えられているはずだ〉
オキザリスは紫解バイオロジー本社ビルの見取り図をチャットに表示した。
〈もう一度お前の意思を確認しておく〉
「行かなくていい。用があるのは屋上だけだ」
〈直接殺害する必要はないのか?〉
「ない。どのみち俺もお前も、何もできないだろ」
『OKサイン』の絵文字。
エレベータは九十階を通過した。
アクセスしづらい上層階には、社員用のホスピタリティ施設、食堂や会議室くらいしかない。紫解の警備兵たちには突如現れたテロリストの意図が掴めなかった。開発されている兵器やその研究者に用がないのなら、紫解バイオロジーを襲撃する理由は何もない。それでいい。
昇っていく数字を無心で眺めていると、すぐに120になった。海と同じで、着いてしまえばあっけなかった。
無菌室のようなエレベータホールを出ると、最上階のフロアプレートには「空中庭園」と書かれていた。キララはコインロッカーから得たカードキーで鍵を開け、温室に足を踏み入れた。
ちょっとした運動場程度の広さに、高い天井。水槽の天辺はテラリウムだった。
幾何学図形のように整った花壇。完全にクリーンな土に陳列されているのは、遺伝子組み換え野菜、バイオ燃料の原料になる穀物、観賞用の花。紫解バイオロジーの主製品だ。紫解のシンボルである藤の木を、アームだけの園芸ロボットが剪定している。
様々な合成植物の隙間に、細いスティック状の明かりが点々と刺さっている。光は濁っていた。ガラスの壁の内側は結露して不透明に曇り、外で吹きすさぶ風雨のほうがむしろ作り物に見えた。
一見して温室は行き止まりだったが、オキザリスは藤の木の後ろを赤くサジェストした。格子状にフレームの入ったガラスの一面が、よく見ると作業員用の扉になっている。生温く湿った夜の庭園を横断すると、キララの血を吸ったばかりの身体は刀に似て、ぬらぬらと光った。
最後のカードキーを扉の端末に翳す。とたんに高層の突風が流れ込み、黒いコートを攫おうとした。彼は咄嗟に襟元を押さえつけ、袖を首に縛った。
重い機械義肢の身体でさえ、ふとした瞬間に突き飛ばされそうな強風だった。地表から目も眩むほど離れて、高層ビルの天辺には驚くほど何もなかった。濡れたコンクリートの床と、空。その境界線には柵すらない。航空障害灯が規則的に並んでいるだけ。遙か下方からサーチライトが往来して淵を撫で、世界の終わりが物理的に存在していることを強調した。二基の厚い光線が重なる瞬間、交点は彼を待っていた。途方もなく巨大な手が蠅を払っているようにも見えた。
しばらくは動けなかった。
オキザリスが足を進めようとするのを感じて、ようやく「自分で行く」と答えた。空中庭園の明かりが背中を離れていく。一歩、また一歩。
なんとか時間をかけて、屋上のぎりぎり端に立った。現実味がまるでない。
足元を見下ろす。申し訳程度に、端に僅かな出っ張りがある。高さは彼の足の甲までしかない。そこから先は無だ。
雨が身体を叩く。集音装置が酷い轟音でいっぱいになり、キララはそれをミュートした。嵐の音は遠ざかり、壁を隔ててくぐもった。
マスクの向こうで、世界は窓の外の景色だった。水滴が絶えず上から下に流れ去る。水の塊がくっついては重みに引かれ、吹き付けられて蛇行しながら、どこかへ消えていく。子供の頃眺めたのと同じ。
ポケットからPLAYの詰まった瓶を取り出し、錠剤を手にぶちまけて握る。風で半分くらいが飛ばされていったが、なんとかうまく掴めた。
マスクをずらして、掻き込むように薬を口に突っ込み、舌の上で数える。うまく『トぶ』ための適量は六錠。何錠あるか全然分からない。奥歯で噛み砕く。
「よし」
瞼で箱に蓋をする。そばにいるのはオキザリスだけになった。
「これでいい」
〈気分は?〉
「これからもっと悪くなる。何か……話でもしろ。暇潰しに」
〈では、聞きたい〉
「何だ」
〈何故こんなことを?〉
『戸惑い』の絵文字に、『スマイル』で返す。
「あいつと俺のために。他にあるか」
〈理由ではない。手段だ。お前の思想からこのような方法が出てきたことが、未だに信じ難い〉
「そうか?」
手遊びでコインを弄ぶように、『歯車』の絵文字を添える。
「俺は自分を摩耗させるのが好きだ。お前が言った」
〈死を恐れていたはずだ〉
「怖いさ。だからこうするしかないんだ」
〈もっと効率的な方法をサジェストするべきだった〉
「できたのか?」
オキザリスは答えなかった。
薄目を開けて、視線だけ足の先の虚空に下ろす。晴れた日に来たら景色がよく見えるだろうな、と思った。あの日みたいに。120割る30。答えは死。
「はは」
くだらない連想ゲームに自分で笑う。キララは両腕を自分の身体の横に僅かに広げて、強風がコートを煽るのに任せた。じっとして、霧の海を眺める。
「準備はいいか」
〈決意があれば、いつでも〉
やがて視界が歪み始めた。薬が回っていく馴染みの感覚。
恍惚とした高揚と、ない肌の下を虫が這う嫌悪。いつもより強く波が引いていく。引き潮のあとに来るものの気配が、強い不安を呼び寄せる。
窓を睨む。雨が降っている。ねじきれてしまいそうに悶える自分の心音を数え、壊れないことを祈り、彼はリプライを投げた。
「やってくれ」
暗転。
〈再生開始〉
電光と明滅。グリッチノイズ。キララは声のない声で呻いた。
………「来いよ」男が喚いている。「死にかけのサイボーグひとりロクに殺せないのか」零れ出る血に噎せながら笑う。「来い、来いよ、来い、来てみろってんだ、かかってこい……」絶叫。生肉と機械が混ぜ合わさったものを引きちぎる感覚。ケーブルと臓物。気持ち悪い。
ばらばらに分解して両腕でプレスし、圧縮した残骸を黒いゴミ袋に押し込んでいく。指先から肘を伝って滴る真っ黒な液体。ぶつ切りの記憶が継ぎ接ぎで再生されていく。スケアクロウの頭部を握り潰した瞬間のフィードバック。硬い蟹の殻を折って、中の果実に指先がめり込んでいく。触った瞬間インターフェースの数値が変わる。生暖かさを想像して悲鳴を上げる。
オキザリスが監督した総集編ドキュメンタリーは、期待よりも遙かに悪趣味だった。三年間の記録を感覚つきで、サブリミナル並みの速度に凝縮した最悪の走馬灯。
休む暇なく矢継ぎ早に、断片的かつ的確に、最悪なカットが脳に直に突き刺さる。
大量のゴミ袋。自分が作った死体の塊の重さ。収集所に投げ上げる時のがさついた鈍い音。フィードバックが記憶と混ざってよりリアルさを増す。関節の隙間に貼り付くマイモの毛。喉を締めていく手の力の強まり方にデジャヴ。生身のスケアクロウ素体を抱き締めて壊した時と同じ。得体の知れない液体まみれで、汚れきった鉄塊の身体。
恐れと戸惑いに震え、穢れを落とそうと手で払う。洗っても洗っても落ちない染みつきと汚れと白い毛。嫌だ。怖い。
規定量の倍のPLAYが感情を見つけて捉えた。映像編集ソフトの上でお気に入りのカットを拡大するように、バウンディングボックスの角を掴んで無遠慮に歪に、縦横比を無視してめちゃくちゃに引き延ばす。肥大化したそれに押し潰されてキララは叫んだ。嫌だ。どうして。何で。助けて。やめて。もう嫌だ、終わりにして。耐えきれなくなって、身体はリアルから逃げようと前へ踏み出した。
無。
墜落。
がくんと視界が傾く。
極限まで圧縮された恐怖が、一瞬にして、月を街中に落とすように巨大に膨らんだ。引き金が引かれた。
キララは叫んだ。
炸裂したPSIが、墜ちていく彼の周囲を粉砕した。
割れた水槽の破片と一緒にキララは叫んだ。自分が叫んでいることが分からなくなるくらい、魂の器が共振で割れるくらいに叫んだ。
霧の下にひしめく光の中に、カズヒサの金色の瞳が振り返った。キララはもう一度、今度は自分に向かって叫んだ。見ろ。俺を見ろ。目を逸らすな。
カメラのフラッシュより速く明滅する過去が心を重力波で蝕み、それをPLAYが増幅する。大鋸屑の上で剥き出しの濡れた臓器を転がすように、恐怖は質量を増し、やがて記憶はオキザリスが作った記録を逸脱した。
身体中傷だらけだった。道具として扱われてついた傷。人を殺してついた傷。父親に押し倒されてついた傷。膝の上のマイモの重みでついた傷。蔑む人々の目の鋭利なナイフで、機械と蹴りで会話しようとする者の靴底で、ヨツヤ博士の言葉で、躾で、喉に刺さったビスケットの角で。
灰色の景色、無味乾燥の世界、軋む鋼の身体、それでも、死が一番怖かった。怖くて怖くてたまらなかった。助けて。どうして。何で。兄さん。帰ってきて。手を。もう一度。兄さん。量産されるスケアクロウ、スケアクロウ、スケアクロウ。怖い。「怖いことを考えるんだよ、アキヒサくん!」自分が怖い。「ありがとう、アキヒサくん」変わっていくのが怖い。「にいちゃん」「カズヒサ」また失うのが怖い。「僕の目を見て」「俺の目を見ろ」嫌だ。「もう一度」ふざけるな。
掻き混ざった意識で下を見る。どんどん加速していく。このまま地面に叩きつけられたら、きっとめちゃくちゃ痛い。
カズヒサの死体の有様がよぎる。三十階であれだ。120。死。死のイメージ。そうだ。想像しろ。死。
恐怖は実体を得た。
キララの身体を核に恒星を生んだ。百二十階建てのビルは球に抉られて蒸発を始めた。四角いバターの塊に溶接バーナーを滑らせるように、紫解バイオロジー本社ビルは渦巻くエーテル球が墜落していくのに合わせて熔解していった。
時間が、ひどくゆっくりになった。濡れたガラスの大きな破片が目の前を通った。綺麗だ、と思った。雨粒の一滴の動きを目で追うことさえできた。
あの日空っぽのまま墜ちていったカズヒサの器とは違って、キララの身体は水から宙を泳ぐ魚で、まだ生きていた。視界に黒い布が見えた。自分の首に巻き付けたコートが、マントのように見事に翻っていた。高さだ。キララは笑った。椅子じゃ足りなかったんだよ。
何かが砕けるのを感じた。そこから迸ったものが、PLAYによって増幅されはじめた。魂から切り離された恐怖のあと、ぽっかりと空いた穴を新しい感情が埋めていった。
兄さんは嘘が下手だった。この世には、ロクなことなんて何一つない。
……自分が気づいて選び取らない限りは。
水槽を割ったら、魚は生きられない。それでも、俺はこれを壊さなきゃいけない。
今までろくでもないことばっかりだった。楽しくて幸せなことなんて何一つなかった。怖いことばかりだった。
だから、これで終わりだ。俺は俺の願いを叶える。
破壊のために与えられた身体。俺は重機だ。重機のキララ。代償に何が壊れたって構わない。
もう怖くなかった。背徳を甘美にさえ思った。
雪より細かくなったガラスは、雨に混じって遙か地表へ降り注いだ。ダイアモンドダストを纏って墜ちながら、キララは後の全てをオキザリスに委ね、目を閉じた。