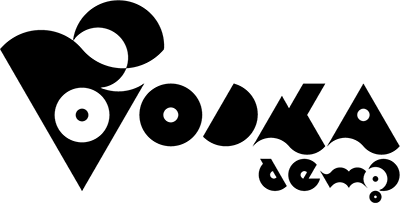東から淡く昇りかけた陽が、ヒシダの駅前に乗り捨てたスケアクロウ用バイクの流線を瞬かせた。
バイクで移動できる範囲内でセントラルラインに接続しているのは、ヒシダ駅だけだった。始発が動き始める時刻のせいか、いつに増して人影はない。
二人は駅の外壁に埋め込まれた、無人のコンビニに立ち寄った。生き物のいなくなった世界にぽつんと取り残されたようだった。
『弟』は軽食の棚の前でひとしきり呻り、キララのところへおにぎりを二つつまんで持ってきた。ツナマヨネーズと牛カルビ。俺だったら絶対選ばない組み合わせだな、と彼は笑った。
コンビニの用具入れから盗ってきた長靴を『弟』に履かせ、キララはセルフレジの台にふたつのおにぎりと、いつもと同じ紫解のパックゼリーを置いた。他に自分の口に合いそうなものはなかった。
駅の前には大きな橋がかかっている。広い川を見下ろす欄干に寄りかかって、食事を摂った。おにぎりのビニール梱包に苦戦している『弟』に、真ん中のテープを引けばうまく開けて食べられる、と伝えた。
外巻きの海苔と内側の米塊がはじめから触れていたように組み合わさって、にいちゃんこれすごいね、と感嘆の声が上がった。
川の向こうに、朝靄に滲んだヒシダ第一コーポラスが見えた。汚れたマイモを掴んだ手の感触は、それが幻肢痛に似たものだということに関わらず、未だに忘れられそうにない。しかし、不思議と心は凪いだ。あれからずいぶん長い時間が経ったような気がした。
ゼリーのパックの空き殻をコートのポケットに突っ込む。反対側の懐の中には、ヨツヤ博士がよこしたセントラル行きの往復切符と、コンビニの端末で発券してきた、貨物用の追加チケットがあった。
あの混乱で、切符を家に置き去りにしてこなかったことに安堵した……人間用のもう一枚を買うよりもずっとまともな金額だが、それでもセントラル行きの切符は高価だった。残高から目を逸らしながら決済して、吐き出されたのは宅配ピザのレシートと同じ、細長く薄っぺらな感熱紙。正方形の集合体で書かれたQRコードが大きく印字されている。
切り売りしてきた人生のおかげでようやく買えた魔法の紙切れが、まだそこにあることを確かめた後、キララはポケットの中から切符をつまみ上げて『弟』に差し出した。
「行くか」
「うん」
受け取って、スケアクロウ素体は頷く。切符の上にある、『往復』の印字が奇妙に思えた。
青年は二度と帰らないエクストラの街を一瞥して、朝焼けに目を細めた。
ヒシダ駅の外観は巨大な門そのものだった。吹き抜けの改札はがらんどうのコンサートホールになって、風の音を反響させた。
ふたりは門を抜けて歩いた。
荷物検査場で作業用旧式アンドロイドのふりをして運ばれていくキララと別れた後、スケアクロウ素体は、駅のホームに続く長い階段をひとり登った。
汎用のスケアクロウに見つからないよう、チャットに投稿された画像……彼には知る由もないが、オキザリスが出した経路表示つきのマップだ……に従って、タブレットを抱いて歩く。開けた場所に出た。アナウンスの指示通り黄色い線の内側に立って待っていると、目の前に銀とオレンジで彩られた列車が凄まじい風を伴って滑り込み、やがて速度を緩め、乗客を招き入れようと脇腹の口を開けた。
なるべく普通に、なるべく何にも興味のないように。
初めて見たなんて、美しいと感じているなんて、誰にも悟られないように。
心の中で繰り返しながら、自分がごく普通の人間に見えることを祈って、車両へ足を踏み入れる。
見たことのないものがいくらでも目を引いた。
壁に沿って横向きに、着席者同士が向かい合うように配置された座席。何のために使うのか、上からいくつも釣り下がったベルト付きの丸いプラスチックの輪。それを支える銀色のポール。列車の側面をくり抜く広い窓。
眩しい原色だらけの広告が、車内の壁という壁を神経質に埋め尽くしている。ドアの上には小さなテレビがついていて、家にあったものと同じように、有象無象の宣伝を垂れ流しているようだ。目につくものの中で唯一親しみのある存在に、少しだけ気持ちが落ち着いた。
不安を逆撫でする軽薄なメロディが鳴り響き、少し後にドアが閉じた。がたがたと振動が始まって、窓の外の景色がゆっくりと動き出し、たちまち目にも留まらぬ速さになって……
青年は、タブレットを抱いて一番隅の座席に腰掛けた。横の衝立に身体を預け、流れていく外の景色を見る。セントラルまでの所要時間は四十分。
窓ガラスの向こうでは、あらゆる物体が色つきの風になって、それが何なのか認識する遙か前に視界をすり抜けていく。バイクに跨がったときに見た風景に似ていた。
にいちゃんの器になりたい。
にいちゃんとずっと一緒にいたい。
にいちゃんと光を見たい。
にいちゃんの目に、手に、肌に、声になりたい。
自分の声の跡が、まだ喉の奥に残っている気がした。
器になるって、どんな感じなんだろう。
昨日は何も感じなかった。できる、と気づいて、衝動を信じて、次に目が覚めたら揺り起こされていた。
それだけ。夜眠って朝起きるのと同じ。
それでいいんだ、と青年は思った。
もう目が覚めないようにしてもらえたら、それでうまくいく。にいちゃんならきっと、ちゃんとやってくれる。元々それが理由でここまで連れてこられたのだから。
家にいる間ずっと眺めていた雨粒の、光に透ける瞬きを思い描いた。
何もないところから降ってきて、ちかちかと輝いて、水に溶けて流れに戻る。それと同じ。雨粒はいつか必ず地面に落ちる。水は川へ、そして海へ。
巨大な流動、自分はその一瞬の飛沫。光に照らされなければ、自分がそこに有ることすら気づかない。
そう、最初の箱の中より前のことは、何も記憶にない。あるのは自分のものではない、ずっと古い誰かの思い出だけ。器も記憶も借り物で、スケアクロウという工業製品ですらない。
誰もあの箱を開けなかったら、何かであることすら許されなかった。
にいちゃんが、僕をここに連れてきてくれた。
だから、にいちゃんになら返してもいい。
にいちゃんに光を見せたい。
にいちゃんに、本当の持ち主に返せるなら、消えてしまったっていい。
にいちゃんの器になれるなら、それで……
タブレットを覆う亀裂が広がって、液晶の弾ける音で我に返った。
「うそ。なんで」
自分の恐怖に応えた画面を、震える手で撫でる。端末は割れた液晶の向こう側で沈黙し、黒い鏡面にはばらばらの自分の顔が映り込んだ。
それで、諦められる。
心臓の刻む音が急に激しくなって、呼吸がうまくできなくなった。『諦められる』?
「見たいだろ、外の景色」
不意に蘇った文字列が胸に突き刺さって、鋭い痛みが走った。
「世界は色に溢れてる。好きなところに行って、好きなものを見てきたらいい。二度と帰ってこなくていい。そうしたら」
そうしたら、諦められる。
身体中が小さく震えて、呻きが零れそうになった。だめ、だめ、なるべく普通に。誰にも気づかれないように。座席に座ったまま、背中を丸めて小さく縮こまった。気を紛らわそうと、目線を上げてドアの上を見る。
海。
小さな液晶テレビの中では、真っ青な波打ち際を、アニメ調で描かれたカニが楽しげに走り回っていた。
「セントラル・ライン、豆知識クイズ!」と文字が跳ねる。きつく目を閉じる。暗闇が全てを覆い隠す。
「だめ」
両方の掌を傷つけるほど爪を強く握り込んで、その痛みで落ち着きを取り戻そうとした。不可視の力を飲み込んで、溢れ出ないように願う。歯を噛み締めると、全身の血管をガラスの破片が傷付けながら潜った。激痛。
知りたくない、怖い。
「にいちゃん」
まばらな車内の乗客の誰にも聞こえないように、息だけで悲鳴を上げた。
「にいちゃん……」
そばにいて。大丈夫だと言って。
早く着いて。早く。
助けて。
願い続ける間、四十分は永久だった。
助けて。
言葉が頭の中に、鋼鉄をアイアンのゴルフクラブで叩きつけたように重く響いた。
どうして、なんで。
キララはもう一度映像を巻き戻して、再生し直した。
「ごめん、カズヒサ……ごめん……」
貨物室のコンテナの中は目を閉じても開けても変わらないほど、光がなかった。記録の中の研究所の、真っ白な壁が目に刺さる。キララはため息をついた。幻覚じゃなかった。
でも、あれは俺だ。
セントラルに行くのは、昔は兄弟ふたりの憧れだった。一緒に海を見たかったから。
引き離されると分かった時には、セントラルとエクストラの境目はふたりを永久に分かつ深い海溝だった。
今となってはどうだっていい。もうこちら側に来てしまったのだから……キララ・カズヒサが来れなかった場所へ。
もう二度とあの街へ戻ることはないだろう、と彼は思った。
兄さんはもういない。アキヒサにはもう会えない。
泣き叫ぶ自分自身の顔を覆い隠して、チャットのウインドウが開いた。
〈宿泊先の予約を完了〉
キララはいいねの絵文字を返して、ウインドウを横に退けた。オキザリスは一度窓を閉じると、もう一度インターフェースのど真ん中にそれを開き直し、予約詳細と金額を表示した。
「おい。見えないだろ」
〈その映像を今確認することに、メリットはない。進んで動揺を招く必要が?〉
「人のメンタルを割れ物扱いするな」
でも、心配してくれるのには、礼を言おう。この前の分も。感謝の言葉を打ち込むより先に、オキザリスの投稿が続いた。
〈コンテナの中身はセントラルに輸送される高価な物資だ。お前がPSIによって破壊した場合、とても弁償の効く金額ではない。待機時間を持て余しているのなら、リスクの低い他の選択肢を推奨する。読書等〉
電子書籍のサジェストがつらつらと表示される。「怖い! 心配! を克服する3つの呼吸法」「気持ちが落ち着く曼荼羅ぬり絵」「あなたの悩みは筋トレで解決する」「声に出して読むだけで強くなれる魔法の言葉」。
ラインナップを見て、キララはもう一度ウインドウを脇に退けた。
「わざとやってるのか」
〈気分を害したなら、すまない〉
「いや、うん……正論だ。お前は正しい。内容はともかく」
研究所での記憶をしばらく見つめ直したあと、チャットを中央の位置に引き戻す。
「なあ。お前は存在理由のためだ、って言ったな」
小さなカタバミのマークを、落ち着いて観察するのは初めてだった。
「お前が俺を助けようとするのは、つまり、お前自身のためだ」
〈その通りだ。私はお前のために作られた。私は私の命題に添って行動している〉
「お前みたいになりたかった、オキザリス」
『Oxalis』という文字列を打ち込むのも初めてだったように感じた。XのあとにIが要るのか、要らないのか、少しだけ綴りに悩んだ。
〈なに?〉
「お前は悪趣味で、何でも理詰めで、情緒の欠片もない」
キララは途切れ途切れに書いた。
「でも、お前は、兄さんに似てる。自分にとって何が正しいかを知ってる。
……兄さんはいつでも俺の味方だった。アキヒサの夢は『世界征服』だ。悪の帝王になるには、人に自分を信じさせるには、自分が一番自分自身に正しくなきゃいけない。そう言ってた。
兄貴はいつも他人のために動き回ってた。学校で酷い目に遭ってた俺の代わりに、相手を突き止めて全員ぶん殴ってくれた。何も面倒見ようとしない両親の代わりに、炊事洗濯掃除、全部やり方を調べて教えてくれた。その親の気まぐれで夜中に玄関から閉め出されたとき、凍え死ぬ前に靴と上着を持ってきてくれて、一緒に治安維持局まで逃げた。
俺は兄さんがただ人のために尽くす、優しい人なんだと思ってた……そうだけど、そうじゃない。兄さんはきっと、自分がやりたいように、自分が正しいと信じてたことのために、やってたんだ。今なら分かる気がする」
AIは細切れの投稿の邪魔をしなかった。キララには、オキザリスがじっと待って、話を聞いてくれているような気がした。
「俺はずっと、誰かが助けてくれると思ってた。『良い子』にしてたら、世界に従順に生きていたら、いつか必ず報われると思ってた」
心のどこかで、いつか誰かが助けてくれるのを願い続けてきた。いつかまたもう一度アキヒサに会えたら、自分をこの地獄から救い上げてくれる。良い子にしてれば必ず、兄さんが、誰かが助けてくれる。そう信じようとしてきた。自分にそう嘘をついてきた。
「……だから、スケアクロウの検体を提供した。だから虐げられても、考えないようにしてきた。だからクソみたいな理由の人殺しを続けてきた。誰かの道具になれば、誰にも刃向かわなければ、それで価値を与えられると思ってた。
自分を擦り減らして生き続けるのは苦しかった。でも、死ぬのはもっと怖い。今まで苦しんで、苦しめられてきたのを、何の意味もなかったことにするのが一番恐ろしかった。願いを叶えてもらう前に死ぬのが怖かった」
映像に映る、自分の絶叫が耳を裂いた。
もう終わりにして。
助けて。
お願い、兄ちゃん、助けて。
「昔に戻りたかった。一番幸せだった頃に帰りたかった。でも、兄さんは死んだし、俺の身体はもう戻らない。
何もかも怖かった。こんな風になってまで、生きてる意味なんかなかった……つい、この間までは。やっと、今、何をしたいのか分かったんだ」
『きらきら』の絵文字を見つけて、そこに添えた。
「俺はお前がいてくれたことに、ずっと気づかなかった。どんなに誰かが手を差し伸べてくれても、光を見つけられるのは、自分自身だけだ。お前のおかげでそれが分かった」
彼はそこでテキストボックスのカーソルを止めた。
しばらくチャットの中に沈黙が流れ、オキザリスは返信した。
〈このコンテナ内に、光源はない〉
絵文字はなかったが、キララはその文字列に『戸惑い』を感じた。
「いや、やっぱり、いい。ただの独り言だ」
〈キララ・アキヒサはお前自身の名前では?〉
「ああ……そうだった。お前には言ってなかった」
どこまで遡って説明するべきか悩む前に、AIは単刀直入に尋ねた。
〈つまり、要点は?〉
その態度がなんとなく頭に来て、キララは勢いに任せて文字を打ち込んだ。
「じゃあ、ひと言で言ってやる。ありがとう」
〈それは一般的に、機械には使用しない言葉だ〉
オキザリスの反応は普段と何も変わらなかった。
「いつもありがとう、オキザリス」
〈道具へ必要以上に感情移入するな〉
「クソ。さっきの話は忘れろ。お前なんか嫌いだ」
恥ずかしくなって投稿を片っ端から削除した後、キララは打ち直した。
「気にするな。お喋りして暇が潰したかっただけだ」
〈それはいい考えだ。役に立てたなら嬉しい〉
『いいね』の絵文字。
そこは喜ぶのか、と思った。オキザリスの物差しは人間とは根本的に異なる。意味があるかどうか、キララ自身の利益になるかどうかだけを見て全てを判断する。誰よりも客観的で、誰よりも事実だけを見ている。
「そう……暇なんだ。ひとつ聞かせてくれ」
彼は思いついて、AIにリプライを投げた。
「お前は俺より俺をよく知ってる。だから聞きたい。俺の望みは、何だ?」
〈平穏〉
即答。
「平穏?」
〈恐怖のない場所。自らの精神を摩耗する要因がなく、恒久的に変化のない、安定した場所〉
オキザリスは当然のように答えた。
「なるほど」
的を得た上で、簡潔だった。
〈私がいる限りは無理だろう。本質的に、私には恐怖が分からない。だが戦闘はお前の望みの対極にある。それは私にでも理解できる〉
『ごめん』の絵文字。
〈きざしをもたらしたのは、『弟』だ。お前に本当に必要だった介助は、お前の平穏、お前の望みを肯定し、維持するものだった。私にはできない。だがそれを支援したい〉
「だから人を勝手にトラクターにしようと?」
〈少なくとも、武装は解除できる〉
『稲』の絵文字。
「……まあ、そうだな」
キララは頷いた。
「でも、それじゃ駄目だ」
どこかのどかで平和なところ。ただの都合の良い重機として生きている限り、この世には存在し得ない場所。
「俺は、スケアクロウの生産を止めたい」
彼はまた映像を巻き戻し、紫解A.R.のエレベータから自分の記憶を辿った。
「あいつに平穏を返してやりたい。あいつが安心して景色を見ながら暮らせる世界が欲しい。それに……これ以上俺が消費されるのを止めたい」
『歯車』の絵文字。
「だからここへ来た」
〈それは、紫解社とヨツヤ博士の完全排除を意味する〉
「できると思うか」
『うーん』の絵文字が溢れるほど大量に並んだ。〈善処は〉という文字列が見えるような気がして、キララはそれを遮った。
「いや、答えなくていい。分かってる」
まともにやったら無理だ。だから、昨日の夜からずっと考えてる。
チャットのウインドウを退ける。映像は再び、実験室の中でスケアクロウ素体と対面するところまで進んだ。
〈キララ〉
オキザリスは懲りずに邪魔な位置にウインドウを置いた。それをまた退けようと横にずらして、思考の中のドラッグ&ドロップはぴたり、と止まった。
光。
嘘。
酷い趣味のAI。
防御反応。
見たくないもの。目を背けたくなる光景。
ガラスの心臓。
共鳴。ESP、そしてPSI。
「なあ」
映像の左上に表示された、小さなタイムスタンプに目をやった。
「この記録、どこまで遡れる?」
〈お前の『セーブデータ』は、紫解のクラウドサーバ上に過去三年間分、すべて記録されている〉
「映像だけか」
〈いや。機械義肢と脳神経へ伝達される、全てのフィードバック情報が付随する〉
「それは切り貼りしたり、要らないところだけ消したりできるものか?」
〈その必要があれば〉
「オキザリス」
キララは『電球』の絵文字をAIに送りつけた。
「お前には才能がある。手伝ってくれないか」
〈善処しよう〉
オキザリスは『OKサイン』の絵文字を返した。
〈だが、何を?〉
窓の外に、不意に早すぎる夜が訪れた。日が落ちたと錯覚するほどの影が景色に覆い被さっている。列車は高層建築物の合間を縫って地中深く潜り、シンジュク駅の地下ホームへと到着した。
まだ何も見えなかった。
他の乗客の後を追ってふらふらと箱を降り、立ち止まる暇もなく流されていく。針の先でも触れたら弾け飛んでしまう気がしたが、誰も、何も、青年を気にも留めなかった。
そこら中に漂うオゾン臭い空気の一部に溶け込んで、スケアクロウ素体は歩いた。
鋼鉄の検問所で荷物検査と簡易的な消毒を受け、切符とキララ・カズヒサの市民カードを提示した。無人の門は小さな電子音を立てて、冷蔵庫のドアのように開いた。
タブレットは頼りにならなかったが、やるべきことはわかっていた。ヒシダの駅で覚え込んだ、チャットの投稿を口の中で唱える。
改札の前に、荷物を受け取る場所がある。そこで待ってろ。なるべく普通に、なるべく何にも興味なさそうに振る舞え。
ちょっとの我慢だ、またすぐ会える。
『スマイル』の絵文字。
もう少し。早く、にいちゃんのところへ、早く。足を動かしていると気が紛れた。早足で人の波を通り抜け、広い部屋に出て、全身が凍り付いた。銀色の流線型が見えた。
最初の警備スケアクロウが彼を見つけるのと、貨物引き渡し場の円環ベルトコンベアから見慣れた巨体が流れてきたのは、ほとんど同時だった。キララはコンベアを降りて、スケアクロウと『弟』の間に立った。
時が止まった。
生身の器と、それを背中に覆い隠して立ちはだかる大型作業機械とを凝視して、警備スケアクロウは静止した。睨み合う顔のない顔。
荷物を受け取りにきた他の乗客に邪険に押し退けられて、スケアクロウは引き下がった。キララは『弟』の手を引いて、人の波に乗って素早くその場を離れた。
シンジュク駅には人が渦巻いていた。人、人、人。地表を追われた者が詰め込まれてひしめく人の群れ。顔を見ることすら叶わない程の、絶えずうねり続ける流動。それでいて、そこには疑いようもない規則の信仰がある。駅は出口だらけの迷宮で、意図を以て銀の玉を弾き仕分けるピンボール台でもあった。
「にいちゃん」
羽織った黒いコートの裾が、きつく掴まれて皺くちゃになった。
声色の中になにかを感じて、キララは立ち止まろうとした。オキザリスが介入して足を止めさせない。無事で良かった、大丈夫か、とチャットで尋ねようとして、青年の手の中のタブレットが光らないことに気づいた。電池が切れたか、通知が何かの弾みでオフになったのか? そうでなくても、人混みに紛れて歩くのがやっとだ。画面なんか見てたら人に轢かれる。
キララは『弟』を側に引き寄せて、コートの内側に招き入れた。
人々でできた川の端々に、時折警備スケアクロウが立っているのが視界に入った。
他の人間たちを押し退けてまで、追ってこようとはしないのか。キララはピザ屋のスケアクロウが大人しく仕事をしていたのを思い出した。そうだろうな。自分の欲のためだけに、そんな大それた事はできない。
擦り切れた歯車。ルールを破って咎められることへの恐怖。アサルトライフルを抱えて突っ立っている姿が、哀しく思えた。
駅の内部は基盤の回路に似ていた。床に隠された順路別の色で光るライン、低い天井の所々に吊り下げられた矢印つきの電光表示。足を進めるオキザリスには、夜の滑走路より鮮やかに道標が見えているようだった。
〈西口に到着〉
濡れた外気がマスクの表面を覆って、外が近いことが分かる。幅の広い階段を登ると、露光の調整が入って一瞬、景色がホワイトアウトした。
オキザリスは立ち止まり、キララは空を見た。
恐ろしく巨大な格子の壁が空を覆っていた。どこまで見上げても途切れることのない、途方もなく高く積み上げられた長方形の構造物。
自分がコンピュータのはらわたに呑まれた小さなコンデンサ部品に思えた。
数百階建ての高層建築物が、所狭しと堆く聳え立つ。窓という窓の全てが検査機のインジケータめいてせわしなく輝き、その枠はひとつの歪みもなく、隙間には人の群れのもたらす秩序と混沌が交互に明滅している。
セントラル。この世の中心にして終点。
中央工場。
都市の脳髄。
最終処分場。
キララは何か言おうとした。
その前に横断歩道の信号が変わって、オキザリスは何の感慨もなくすたすたと交差点を歩いた。すぐに屋根のついた通路に入って、巨大都市の檻は覆い隠されてしまった。
「にいちゃん……」
『弟』は不安げに尋ねた。電源の入らなくなったタブレットを抱いて、キララの歩幅についていくのがやっとのようだった。
「どこに向かってるの」
「俺も聞きたい。どこに向かってるんだ」
周囲環境の情報量の洪水に、インターフェースの表示も頭の中もめちゃくちゃだった。
〈現在地を表示〉
オキザリスは点描かエッチングアートと見紛うばかりの周辺マップを表示した。地名の表示なのか、施設名の表示なのか、飴にたかる蟻のような文字の群れが理解を阻む。
「人間にわかるようにできないか」
〈宿泊先にピンを設定〉
マップが縮小されて表示範囲が広まり、離れた場所に点が打たれる。
「シブヤ・シティとミナト・シティを避け、人目の多い経路でシナガワ・シティに向かう。シナガワの治安維持局はまだスケアクロウを導入していない」
「なるほど」
キララは『弟』のタブレットを預かり、画面に触れた。
「あ……」
ひび割れが酷く、二度と使い物になりそうになかった。
「あの、ごめん、僕、それ……壊しちゃったみたい」
指先で肩を叩いて、そっと返してやった。
「ごめん……にいちゃん、ごめん」
俯いて床を見ながら歩く青年に、何も言葉をかけられないのがもどかしかった。まるで子供の頃の俺だ、と彼は思った。アキヒサに謝ることしかできなかった頃の。
「こいつをどこかで休ませたい。宿に向かうほうが早そうか」
〈我々は特別快速に乗ることができた。15時のチェックインにはまだ少し早い。宿泊先の周辺で時間を潰すことができる。希望は?〉
「お前に任せる。二十年近く、カサミからほとんど出てないんだ。土地勘も何もない」
『OKサイン』の絵文字。
〈サジェストを表示〉
半ば身構えながらオキザリスの指す場所を見る。始末屋の仕事をする時は、いつも目的地に早めに着いて、周囲で暇を潰しながら情報収集をしていた。場末の喫茶店。この図体で、しかも何も食わない客を喜ぶはずがない。ネットカフェ。まともに入れる部屋がない。それが嫌だと伝えたら、オキザリスは工事中の何もない空き地や、ビルの隙間の路地裏をサジェストするようになった。建築用の重機の気分になれて、最悪だった。
そういう類いを想像していたが、キララはマスクの奥で赤い人工眼を丸くした。マップには「海浜公園」の文字。
画面の大半を占める平らな塗り潰しが海だとしたら、オキザリスの指したポイントは、浜辺のどこかだった。
「海?」
〈昨晩、行きたいと〉
海。
「そうか」
今にも泣き出しそうな『弟』の顔と、チャットの中のカタバミのマークを見比べる。
彼は自分の中の誰かに呟いた。
「行けるのか」
〈懸念は特にない〉
オキザリスはあっさりと答えた。
マップの表示の現在地ピンが目的地に近づいていくのを見ても、心の内のどこかでは、まだエクストラにいて白昼夢を見ている気がした。
決して辿り着けないように思えたが、実際は、そう遠くもなかった。歩いて、歩いて、突然道幅があきれるほど広くなった。
〈到着〉
あまりにもあっけなかった。
万里の長城めいた巨大な摩天楼に添って歩き、ようやく見えた角を曲がると、そこには一転して空があった。牢獄の最後の一枚の壁を破ったように、あるいはそこで世界が終わっているかのように、街は消えた。
目の前の道が唐突に、直角に下りの階段になって、見下ろす程度に地面が低くなっている。
遮るものは何もなく、風が強い。
〈付近にスケアクロウの反応はない。接近時は警告する〉
急に身体が自由になって、吊られた糸を切る感覚と、自分の重みが四肢に戻った。オキザリスが操作権を手放したらしい。
軽い目眩がして、キララは喉の奥で小さく呻いた。
〈一時間ある。好きにするといい〉
チャットの窓はひとりでに閉じた。
「オキザリス」
インターフェースの片隅に、控えめに『15:00』のリマインダーだけが残されている。
「なあ。おい」
返事は返ってこなかった。
目の前は、海だった。
一面均一な灰色で塗られた空が、視界の中心の水平線を境界に、鏡映しでどこまでも広がっていた。
キララはカタツムリのように背中にしがみついていた『弟』の手をつつき、降りるように促した。青年は伏せ続けていた顔を上げ、小さく答えた。
「うん……? 着いたんだね」
背中の長靴が地面に触れるのを待って、彼は歩いて短い階段を降りた。コンクリートで固められた段差の、すぐ下が砂浜になっている。
わあ、と聞こえた。振り返って見上げると、『弟』は口を開いたまま立ち尽くしていた。
キララは足下を見た。階段の終わりから右足を伸ばし、足先だけを石と砂の境界線に乗せる。感触はわからない。
踏み慣れたコンクリートから左足を離し、砂の上に置く。両足が砂の上にあった。
細かな粒子が擦れ合い、ざらついた小さな囁きが起きた。金属塊でできた爪先は、音もなくゆっくりと沈み込み、快く受け止められた。
穏やかで、静かだった。
彼はマスクを取って、足元に置いた。
潮風が短い巻き毛の先を弄んだ。感覚は無く、景色は無彩色。柔らかい砂の上では、そんな事はどうでもよかった。何歩か歩いて振り返ると、ざくざくと心地良い音がした。
まだ階段の上にいる『弟』に手を振って、手招きした。
青年は揺れる吊り橋の上を歩くように、階段を下った。一番下まで来て、キララと砂浜と、その後ろに広がる海を見る。
「にいちゃん」
見れなかった。身体中の血が液体窒素に触れたように冷たくなって、足が竦んで、その場に蹲った。
「だめ! 来ないで!!」
駆け戻ろうとしたキララの足下で、踏みとどめた砂が隆起した。空気が震えて軋むのを感じた。
「……来ちゃだめ……危ないから」
不可視の力が身体の金属を圧した。彼はいつか、アキヒサに同じように叫んだのを思い出した。
数秒だけ待って、足を進めた。止めるなよ、と心の中でオキザリスに呟いた。
「だめ……」
弟の側まで行って、背を屈めて隣に座った。
「……」
青年は両手で胸を押さえた。キララは膝をつき、コンクリートの横の砂に人差し指を突き刺して、「大丈夫か」と書いた。
「ごめん。なんでだろ……僕……」
弟は俯いたまま、首を横に振った。
「怖くて。どうしたらいいのか、わかんなくて……昨日からずっと、僕が自分で言ったのに、どうして」
キララは鋼の手で砂をざらざらと撫でて、書いた文字を消した。払った場所に何か書こうとしたが、言葉が思いつかなかった。
「にいちゃんに返すって決めたのに。わかってるのに、これはにいちゃんのものなのに。僕はいなくなるのに、ここにいなくていいのに。でも、怖いよ。なんでかわかんないのに」
俺もそうだ、と言いたかった。
十一歳のあの日からずっと、同じ事を思って生きてきた。何で僕を。何で僕が。生き残るべきだったのは、兄さんだったのに。
だからアキヒサだと名乗り、アキヒサのふりをして生きてきた。
兄さんが消えてしまわないように、自分を殺して、全部なかったことにしようとした。
弟なんて最初からいなかった。
「ごめん」
大人になってから就いたのは、テレビの隙間に流す映像を切ったり貼ったりする仕事だった。編集AIがサジェストしたいくつかの自動生成を、繋ぎ合わせたり整えたりするだけの単純作業。それでも楽しかった。
たまたま幸運が巡ってきて、ちょっとした賞も取った。感心されて、褒められて、打ち上げでいい寿司屋にも連れていってもらった。ひと駅だけ、ほとんど一瞬とはいえ、セントラルラインに乗れる日が来るなんて思わなかった。
生まれてこのかたロクな事がなかったから、あんな風に扱ってもらえたのは初めてだった。
それはカズヒサのものじゃない。兄さんが生きてたら、本当は兄さんが得るべきものだった。
でも、電子記録された表彰状に、キララ・アキヒサと名前が書いてあるのを見て……一度だけ、鏡の前で謝った。
ごめん、カズヒサ、ごめん。
「にいちゃん、ごめん」
今思えば、そんな風にしなくてもよかった。
兄さんはカズヒサを生かしたかったんだ。そんなことしなくたって、アキヒサは消えたりしなかった。自分が必死で、気づかなかっただけで。
「僕、にいちゃんと一緒にいたい。にいちゃんはひとりでいいのに。『僕の』にいちゃんじゃないのに。分かってるのに……」
キララは砂の上に広げて置いたままの、自分の手を見た。
俺の、兄さんはもうどこにもいない。
でも、キララ・アキヒサはここにいる。
魂が流体で、器によって形を変えるなら。
彼は砂にもう一度指を突っ込んで、不器用に絵を描いた。限りなく四角に近い丸の下に、大という文字がくっついて、棒人間ができた。隣にもう一人。
弟の肩をつついて、その手で片方を指さした。もう片方の絵を同じ指で叩いて、今度は自分の胸を指す。
訝しげに首を捻る弟に向けて、最後に目の前の海原を指さした。
「……?」
同じ仕草をもう一度繰り返す。伝わる事を願った。
ふたりで、来たかったんだ。海に。
「…………」
キララは弟の手を取って、立ち上がらせた。
「わ、ちょっと」
片足を引き摺って、砂浜に長い線を書く。その奥側に歩いていって、線の反対側を下向きに指さした。
「え……こっちに立てってこと?」
頷いて、促す。コートの懐から朝食べたゼリーの空容器を取り出して、振り回して空気を入れ、膨らませて蓋をした。
「オキザリス」
即席の浮かばない風船を真上へ放り投げると同時に、いないふりを貫いているAIへリプライを投げる。
「戦いだ。手伝え」
重い手で叩かれたゴミのボールが、勢いよく飛んでいって線の向こうの砂に埋まった。
瞼を何度も瞬かせている弟を横目に、足で小さく一本の横棒を書く。キララは挑発に使われるジェスチャーで、投げてこい、と示した。
なんだかよくわからないまま、青年はゼリーの袋を砂から拾い上げ、線の向こうに放った。
思い切り鉄の腕を振ると、袋は弾かれ、本物のボールのように空中へ飛び上がった。加減を誤れば鉄をも砕く威力になるはずだったが、オキザリスは機械義肢の加速度に介入し、ビーチバレーに相応しいボレーを標的に与えて跳ね上げた。きれいな放物線を描いて、袋は青年の足元に落ちた。
キララはまた足で線を書いた。片手を広げて見せびらかし、「五点先取で勝ち」であることを示した。
ルールを察した青年は、大声で返した。
「え? ……ねえ! じゃあ今のは点数に入れたらずるいんじゃないの!? 僕わかってないのに!」
兄は肩を竦めた。
弟はレインコートの袖を捲り、ポケットや背中に入っていた荷物を脇に置いた。ボールを再び砂から拾い上げ、頭上に掲げる。
「いくよ、にいちゃん」
サーブの要領で打たれたボールは、境界線のほぼ真上、僅かにキララ側に影を落とした。キララは諦めようかと悩んだが、その前にオキザリスが低く身を屈め、倒れ込むのに近い正拳突きで弾き飛ばした。ボールは灰色の空に高く舞い上がる。
砂を蹴り、弟は思い切り飛び上がって、キララの頭の上で弾を叩いた。ボールはくるくる回って、背中のすぐ後ろに落ちた。
「やったあ、一点ね!」
足で素早く横棒を書きながら、青年は笑った。
飽きるまでビーチバレーごっこで遊んだ後、ふたりは引き潮の渚を端から端まで歩いた。
弟は砂の隙間の潮溜まりを遠目に覗き込んで、動くものがあるたびに「なにかいる。お寿司の材料かな」とはしゃいだ。
砂浜はテレビで見た透き通る水には程遠く、ペットボトルや様々なプラスチックで構成されたゴミ、得体の知れない藻の塊、小蠅のたかった海鳥の死骸が、波打ち際で揺らいでいる。
それでもよかった。海は海だ。
色も匂いも感じなくても、そこは美しかった。
「ね、見て」
流木の脇に屈み込んでいた青年は、何かを拾い上げて、キララの胸の前に差し出した。
片手に収まる程の大きさのそれは、長い間波に洗われて角の摩耗した、ガラス瓶の欠片らしかった。
「ほら、銀の虹。にいちゃんと、同じ色」
柔らかい手の平が傾くたびに、欠片の表面はきらきらと陽の光を瞬かせる。キララは見下ろした自分の胸元が、同じ反射パターンを持っていることに気がついた。目に映るのは灰色のグラデーションに過ぎなかったが、それで初めて、彼は自分を覆う硬く重い装甲が、何色なのかを知った。
焼けた金属の色。雨粒の中で乱反射した光。濡れた窓に雨上がりの陽が通り抜けたとき、机の上に生まれる小さく鮮やかな三原色。
「待ってて! もうひとつ見つけてくる。にいちゃんにもあげるから!」
弟は宝物をポケットにしまって、踊るような足取りで砂の上を走った。ふと来た道を振り返ると、ふたり分のサイズの違う足跡が右へ左へ、螺旋を描くように残されていた。
やがて時間が来て、ふたりはようやくホテルに腰を落ち着けた。弟は部屋の椅子に座っても、まだ虹色の欠片を蛍光灯に翳して眺めていた。
この上なく居心地の良い部屋だった。乱立する巨大構造物の中の一角、海を向いたホテル。『油とゴミの浮いた薄汚い海が見える』という点は、マーケティング上ではマイナス点であるらしかった。それを補うための、この宿泊施設の最大の売りは『機械義肢にもバリアフリー』。
管理は無人で、フロントには石版に似たタッチパネルボードしかなかった。ヒシダのマンションの入り口のような、人間とは何かを巡る怠惰で無意味なやりとりに身構えていたキララは拍子抜けした。機械は誰にでも平等だ。
扉のキーはランダムに生成された英数字混じりのパスワード。ベッドメイクもルームサービスもロボットが行い、建物内には無人コンビニがある。
部屋は失った家の居間のちょうど半分くらいの広さ。床も壁も衝撃吸収材で、重い足音が響かないようになっている。
壁の側には、立方体を削った形の椅子と机が一対。ひとり用のベッドの横に、キララのための大きなマットレスが敷いてあった。
どこを見ても頑強で無骨な設えだ。オキザリスが家を建てたらこんな風になるだろう、と思える、機能性以外の一切を省いたホテルだった。
廊下やエントランスの所々には強化自動ドアがあって、パスワードキーを知らなければ入れない。そして、館内にスケアクロウは一体も配備されていない。これにはこの施設で唯一、非効率的な理由があった……六割以上を置換した機械義肢の人間は、皆一様にアンドロイドの側にいることを嫌う。有事の際には自動ドアの横に隠されたタレットが起動するようだと、ダブルチェックを行ったオキザリスが補足した。
「よくもまあ、ここまで都合の良い場所を見つけたな」
『超いいね』の絵文字をつけて、キララは部屋の壁に背をつけて座り込んだ。
弟のほうを見る。机の上に新しい宝物を並べて、ひとつひとつを慈しむように撫で、持ち上げては光に翳し、眺めては驚いたり、睨んだり、微笑んだり。
寿司を見てた時と同じ顔だな、と思う。それから、自分自身が回転寿司を好きだった理由に思い当たった。あれが食べたい、と感じたものを、好きなように選んで食べられる。カズヒサにとっては夢のようだった。
兄弟には、選択肢はなかった。望んだものを望み通りに選び取る自由。
「いろんなことがあったからかな。なんだか、すごく眠くなってきちゃった」
備え付けの給湯器で入れてやった紅茶の残りを飲みながら、弟は四角いソファに背を預けた。
「楽しかった。にいちゃんと一緒に来れてよかった。テレビで見るのも、遠くから見るのも綺麗だったけど、でも……今日が今までで一番楽しかった」
眠たげな目で、微睡みながらはにかむ。
「生きてて、よかった。にいちゃんと会えてよかった」
キララは立ち上がって、弟のすぐ側に腰を下ろした。肘掛けを辿って細い腕がゆっくりと伸び、指先が鉄の手の平に触れた。
「ほんとはもっと、一緒にいたい。もう今日が来ないのが怖い。ずっと一緒に海で遊んでいたい」
金色の瞳は、白い睫と瞼に遮られて見えなくなった。
「でも……最後はちゃんと、お別れしてからがいいな。きっとうまくいくから」
話し声は少しずつ小さくなっていって、呂律も曖昧になって、丸い溶けかけの氷のよう。それでも言葉は続いた。
「ねえ、にいちゃん、どこにも行かないで。ずっと一緒にいて」
ほとんど音にならない声が縋りつく。
「僕が消えちゃっても。ずっと……」
キララは手を握った。
「………」
呼吸が寝息に変わるまで、ずっと手を握っていた。
それから、睡眠薬の混ざった紅茶の残りを、洗面台に流して捨てた。
仕事道具を詰めたバックパックからダクトテープを引っ張りだし、無骨なベッドに弟を寝かせ、両手両足を幾重にも巻いて拘束した。
テープは引き出すたびに耳障りな絶叫を上げたが、弟は静かに眠っていた。眉を寄せて不安げに、安眠とは程遠い哀しい顔で目を閉じているのを見て、金属の胸の奥が痛みを感じた。
「どの位効くと思う」
〈四時間。最長で 六時間。体質によるが〉
「そっちの首尾は」
〈お前の指示したものは全て受け取っている〉
『OKサイン』で返す。
「わかった。行こう」
縛り上げた弟に布団をかけてやって、心の中でごめん、と囁く。
俺も楽しかった。お前と一緒に、来れてよかった。
『起こさないでください』の札をドアノブにかけて、キララは部屋を後にした。