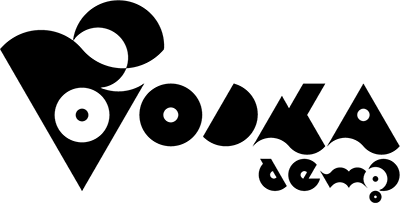『全権委任』。他に言葉は要らなかった。
オキザリスはキララの手を取った。目の前を飛び去っていくままだった外壁へ、重機の指が爪を立てた。不時着する飛行機のように激しく振動しながら、オキザリスは墜落を止めようと試みた。雨の中に煌々と火花が散り、指先は摩擦で赤熱した。
ガラスが抉られ、線を描いて砕けた。外装の剥がれた紫解の壁にブレーキ痕が刻みつけられていく。速度は落ちない。振動と熱に耐え切れず、左手首が損壊した。AIは次の損傷を予測し、両足を伸ばして壁に突き立てた。左腕はまもなく全機能を失ったが、オキザリスには想定の範囲内だった。まだ三点残っている。減速に支障はない。
気を失ったままのキララの身体は今、重力を直進するトラクターだった。豪雨が濁流となり、90度曲がった世界で装甲を迸った。ねじ曲げられた構造物の中で、鉄骨がしなった。鋼同士が擦れ合って甲高い悲鳴を上げた。
シナガワのホテルの一室で、スケアクロウ素体は痛みに悶えた。絶叫が喉を灼いた。心が挽き潰されていくようだった。
セントラルの街角という街角で、全てのスケアクロウがぴたりと静止し、空を見上げていた。顔のない顔、疑似複眼の向こうには、溶けた紫解のビルと光球の残像があった。金色の瞳がカズヒサたちの心を捉えて止めた。誰も動けなかった。
酷い悪夢だった。誰かの身の上に本当に起きたことを、嫌な部分だけ切り貼りして膨れ上がらせたような。人の五感が理解し得る耐えがたい感覚だけを、悪意を持って編集したような。悪趣味極まりないテレビ番組のような。
強烈な共鳴がスケアクロウたちを圧し潰した。キララの人生を煮詰めた記録が、彼らの稀薄な自我をずたずたに引き裂いた。硬い殻の中に押し込められていたカズヒサの魂が、ここから逃れたいと身を捩って悶えた。ダクトテープの拘束が、スケアクロウ素体の白い肌に痕を作った。
地表は目の前まで迫っていた。高度計の数値がアラートを点滅させはじめた。
オキザリスはキララの心拍を数えた。異常なし。減速を続行。
AIは、不可能ではないことを知っていた。
確率が0ではないのなら、それを試行するだけ。
道具がやるべきことは一つだけ。人間の選択を助け実現させる。それだけだ。
『全権委任』のコードの意味は、オキザリスにとって、どんな絵文字より明白だった。『死にたくない』。キララ・アキヒサは生きたいと願っている。
後で彼が見返す時のために、オキザリスはチャットに記録を残した。
〈接地まで10秒。カウントダウン〉
摩擦熱が身体を溶かした。振動が視界を乱した。世界のすべてが幾重にもぶれて、重なって見えた。
〈9〉
べたつく肉塊。どす黒い何か。汚いマイモ。女の子の笑顔。ゴミ袋。スケアクロウ素体は叫んだ。
やめて。
やめて、見たくない、知りたくない。
〈8〉
助けて。お願い。やめて。
信じてたのに。
どうして。何で。
言うことを聞いてれば、いつか必ず報われる、その日が来るって信じてたのに。こんなの見たくない。知りたくない。お願い。返して。やめて。奪わないで。
〈7〉
銀色の流線型の身体が、わなわなと震えだした。
〈6〉
紫解バイオロジー本社ビルの崩壊に気を取られていた人々は、ようやく異変に気づき始めた。
空を見ていたスケアクロウたちが、顔を覆って膝をつき、泣き崩れた。
傘を差した人々は、それを見て不気味に思った。スケアクロウが泣いてる。そんな訳あるか、ただの機械だぞ。
〈5〉
助けて。
兄さん。
「………にい、さん?」
スケアクロウ素体は、掠れた自分の喉から絞り出された音に戸惑った。吐かれた言葉は別の誰かのものだった。
「待って……」
幻が脳裏に閃いた。遠いどこかの砂浜で、何かが自分を待っている。自分ではない誰かを呼んでいる。
「やめて」
〈4〉
蹲っていたスケアクロウたちは、やがて、突然立ち上がった。大切な人から名を呼ばれたように。
〈3〉
「たすけて」
声が震えた。誰かが勝手に叫んでいる。
「置いていかないで……ひとりにしないで」
呼ばれている。金色の瞳。声。光。笑顔。ずっと会いたかった人。それに応えようとして、自分の中の誰かが泣いている。
「僕も、………俺も、………連れていって……」
知らない記憶。知らない切望。荒れ狂う衝動が胸の奥から溢れ出し、光を求めて叫ぶ。
「兄さん。兄さん……兄さん!!」
〈2〉
「やめて!」
『弟』は抗おうとした。喉元をシーツに叩きつけて喘いだ。空気に溺れる魚のようだった。痛みと傷で自分を繋ぎ止める。
「やめて……僕は、僕は行かない……!」
ダクトテープで縛られた身体がもどかしく、しかしそれがなければ、今すぐにでも窓から飛び降りてしまいそうだった。
「行きたくない……! 諦めたくない……僕は違う……! やめて……! 」
自分がどこかへ消えてしまいそうで、怖くて怖くてたまらなかった。ホテルの壁に亀裂が走った。恐怖が空気を圧縮し、ベッドや椅子を軋ませた。机の上の貝殻が弾けて砕けた。
身を捩っている間に、テープが緩んできていることに気づいてしまった。カズヒサもまた、それに気づいた。
〈1〉
スケアクロウたちは、自分が行くべき場所に気づいた。
「お願い……やめて………やめて!!」
『弟』は叫び、祈った。
「にいちゃん!! 助けて!! にいちゃん!!」
〈0〉
轟音。
キララは目を覚ました。窓が割れている。シアン、マゼンタ、イエローのけばけばしいノイズが迸り、真っ赤なエラーで視界中が埋め尽くされている。光。綺麗だ。
隙間から向こう側の景色が見える。地面。自分がコンクリートに放り出されて転がっているのがわかった。頭上から瓦礫が降り注ぎ、多分、どこかで何かが燃えている。ぱちぱちと火花の弾ける音がする。熱くはないが、やけに近い。頭の中で直接鳴ってるみたいだ。
ビビッドカラーをぶちまけて液状化したインターフェースの端に、見慣れたウインドウが残っていた。キララはそこにオキザリスの名前を打ち込もうとした。
〈善処はした〉
AIは尋ねる前に答えた。
『いいね』の絵文字をかろうじて送る。感情が空っぽで、なぜだか言葉がまとまらない。オキザリスは彼を立ち上がらせようとして、鋼の身体を震わせた。
〈移動を試みる。ここは危険だ〉
身悶えするが、動くのは首と右腕だけのようだった。何も感じない。
〈キララ?〉
彼は小さく頷いた。
何もない。穴。黒。無。
〈キララ〉
何も動かない。揺らがない。壊れてしまったのか、乗り越えてしまったのか。ぴんと張った糸のように澄んでいる。ずっと自分を満たしていたはずの感情が、1ドットの欠片すらない。あれほど苦しんできたはずなのに。もう思い出せない。
キララは三原色の光を見ながら、じっと身を横たえていた。長い間ずっと求めていたもの。これが答えかもしれない、とぼんやり思った。
オキザリスは身体中の動力を調べ、しきりに慌ただしく駆動させようとしている。
〈すまない、キララ。これは……想定していなかった〉
何かが腕を踏みつけた。
聞き覚えのある声が聴覚に飛び込んできたが、心拍数は変わらなかった。
「アキヒサくん」
顔を上げると、ヨツヤ博士が笑っている。
「ねえ、アキヒサくん。よかったね。生きてるよ」
ばかばかしい姿のせいか、最初はいつものビデオメッセージに見えた。小さな頭の上に三角のパーティハットが乗っていて、白衣は煤や塵で汚れ、血に染まっている。たすきがけされた『本日の主役』の字。
博士は側に屈み込んで、キララの首に両手を回した。留め金が外れ、割れたマスクは瓦礫の山へ放り投げられた。少女は目を細めて微笑んだ。しかしそれは彼ではなく、冷たくどこか空虚を眺めている。
「よくないか。残念だったね。せっかく死ぬ勇気が出たのにね……?」
小さな手が剥き出しの顎に触れ、くいと持ち上げる。聞き分けのない犬に呆れ返って、お前は馬鹿だ、と言う時の手つき。
「罪のない大勢を巻き込んで。今日はわたしの歓迎会だったんだ……さっきまでパーティだったんだよ。きみが溶かした部屋でね」
知ってる、と答えようとした。声は出ない。
だから、今日なんだ。あんたはパーティとか、記念日とか、そういうものが大好きだ。よく知ってる。だから今日は必ずここに、この建物にいると思った。
「他にもっといい方法がいくらでもあったろうに。悪い子だ」
博士は自分の玩具の耳元に口を寄せて囁いた。集音装置がため息を拾ってノイズに変えた。憎悪の言葉がかりかりと脳を掻く。
「この人殺し。きみはお気に入りだった。ずっと大事にとっておいたんだ。きみの怯えて怖がる目が大好きだったのに。処分しなきゃいけないなんて残念だよ」
子供の細い指が口の中に突っ込まれ、キララは反射的に吐きそうになった。
「ほら。苦しいか? そうだろう。今はわたしもきみと同じ気持ちだよ! あはは。どうしてくれるんだい。チカを刷る場所がなくなっちゃったじゃないか!」
喉の奥を引っかき回される。何度もえづく彼を見ながら、ヨツヤ博士は楽しくて仕方ない、と笑った。
「きみのやったことは無意味だ。スケアクロウをダメにしたかったんだろ。でもね、ここだけ壊したってどうしようもない。全ての工場を同時に潰しでもしない限り、きみ一人に我々は止められないんだよ。それとも、わかったうえでこのくらいしかできなかったのかい? ねえ……」
愚かだね、と嘲笑って、博士はキララの顔を覗き込んだ。絶望を見るのは彼の一番好きなことだった。
「………アキヒサくん」
思いがけない目の色を見て、博士の笑みは消えた。
キララの目は笑っていた。
波の音がした。
「何をした」
ヨツヤ博士は立ち上がって辺りを見回し、その正体を探した。さざめきが寄り集まってどこかへ向かう音。
瓦礫の向こうに答えが見えた。
「まさか」
白衣のポケットの中で端末が鳴いた。最初は一度だけ、やがて止まらなくなった。苛立たしく掴み上げるが、その手は震えている。8歳の少女に似合わない血の気の引いた表情で、目線を宙に泳がせる。会社からのコールに出るまでもなかった。
それは足音だった。
街灯に照らされ、雨に濡れた銀色のプリズム。生物の蠢き。静かに、怯え、しかし強い願いを持って、どこかへ向かうスケアクロウの群れ。ばらばらの足並みは行進とは程遠い。家族とはぐれてしまった迷子が、来た道の景色をうっすら思い出して、それを頼りに歩いている。泣きじゃくりながら。銃を抱えたものも、どこかの制服を着せられたものも、ステッカーを貼られたものもごちゃ混ぜに、ありとあらゆる全てのスケアクロウが同じ道を辿っていた。
道を埋め溢れかえって彷徨う彼らを、人々はなすすべなく見守ることしかできなかった。紫解のビルでのテロ騒ぎを撮っていたテレビカメラは、撮るものが消滅してしまったので、その光景を映すことにした。中継は瞬く間に拡散した。
気持ち悪い。誰かが囁いた。なんか、人間みたいじゃないか……
「……ESPの共鳴か。やってくれたな」
ヨツヤ博士は白衣の懐に手を突っ込み、小さなプラスチックハンドガンを取り出した。
「やめさせろ」
短い銃口をキララの顎に押し込む。
「やめさせろ。今すぐに。聞こえなかったのか」
チャットの文字を読むように、キララには博士の声が見えた。博士は怯えている。これから起きることを恐れている。
命令に従わないアンドロイドなどあり得ない。中身が人だなんてもってのほかだ。あれは、人の動きだった。誰が見ても疑いようがない。機械が泣くわけがない。
じきに真実が露呈する。紫解は全ての責任を博士に押しつけて、彼を消そうとするだろう。予備の身体は刷れない。
やっとここまで来たのに。余命を告げられたあの日から、ずっとやり方を考えてきたのに。冷たい暗闇、無、そこには何もない。何にも勝る天賦の才を持ってさえ、死の前では一切何の意味もない。もう二度とあんな孤独で、惨めで、恐ろしい思いはしたくない。それなのに。チカ嬢の奥の瞳はそう喚き立てていた。
イサキ博士は怖がっている。この男の奥底でずっと火をくべ続けてきた、彼の行動の原動力。それは死への恐怖だ。
キララは急におかしくてたまらなくなった。なんだ、同じだったんじゃないか。
「何を笑ってる!」
イサキ博士は、嘘のつきかたは上手くても、本音を隠すのは下手くそだった。わたしは死にたくない。PSIよりわかりやすい。ぎりぎりの所で、理性が、恐怖が、激昂を抑え込んでいた。引き金の上で指が躊躇った。
「……きみが死んだら止まるのか? それとももっと酷くなる?」
恐れて撃てない銃口が、キララの喉を深く突いた。感覚がないはずの粘膜を強烈な不快さが舐った。子供の頃、父親にやられたのと似ていた。あの時恐怖の代わりに抱くべきだったものを、キララは手繰り寄せた。
「……!!」
引き金から指が離れる瞬間を待っていた。歯を食いしばって首を捻る。少女の華奢な身体は、怒れる獣の激しい抵抗に引っ張られ、アスファルトの上を横転した。パーティハットが飛んでいった。反対側に首を振って、キララは安っぽいプラスチックを瓦礫の向こうに吐き捨てた。
「クソ。この……!」
痛みに毒づいて髪を振り乱し、呪詛とともに立ち上がる。
「オキザリス!」
博士は我を忘れ、怒りに任せて叫んだ。端末を握りしめ、擦りむいた手で何か文字を打った。
身体が縛られるのを感じた。操作を司るコードが博士の手に渡る。
〈逆らえない〉
オキザリスの短いチャットから、悲鳴が聞こえるような気がした。
〈キララ、すまない〉
「わかってる」
〈私は〉
「お前は機械だ。お前のせいじゃない」
〈すまない〉
キララは『OKサイン』の絵文字で励ました。
もう怖くはない。でも、まだ死ねない。このままじゃダメだ。
〈すまない。何もできない〉
彼は頷いた。俺だ。俺が、戦わなきゃいけないんだ。終わらせなきゃ。あいつのために。俺の弟のために。
「オキザリス。こいつを殺せ!」
右手はゆっくりと拳を握った。イサキ博士の憎悪の目が、キララを見た。頭よりも遙かに大きな鉄塊が、振りかぶって、自分の顔に影を落とした。
目と目が合った。少女の目の虹彩まで見えた。
弟?
ああ。キララは気づいた。そうか。
俺は、兄貴だ。
アキヒサ。
金色の瞳。
できる、と分かった。彼は両手を伸ばした。
不可視の重い腕が、イサキ博士の首を掴んだ。
正体不明の感覚。胸の底に隠した全てを暴かれるような。瞳孔が開いた。博士は眩い光に怯えた。
「な……」
その魂は少女の器から引きずり出された。
次の瞬間、ヨツヤ・イサキは暗い箱の中にいた。色のない視界。感触のない冷たさ、ぞっとするほど狭い暗闇。『あのとき』と似た感覚。孤独。極寒。死の記憶が思考を乱反射し、迸る恐怖が彼の心を震わせた。
いやだ。
神経に残った大量のPLAYが、その感情を見つけて捉えた。
やめろ。いやだ。
いたずらに引き伸ばされて巨大に膨らむ。
叫んでも声は出ない。切除された声帯の痕が空しく震える。
目の前に大きな窓がひとつだけあった。
壊れた極彩と無彩の窓。巨腕が、鉄の塊が見えた。こちらへ向かってくる。自分の右腕が、自分の意思ではない力に支配されている。
いやだ。
死にたくない。
いやだ。
博士はシンクチャットの打ち方を知らなかった。
脳内物質が時間を歪めて引き延ばし、窓の向こうの景色をコマ送りにして見せつけた。ゆっくりと迫ってくる巨大な質量。関節の奥で人工筋肉がAIの信号を受信し、それが機械義肢の中で反応し、構造を動かし、止まって見えるほどゆっくり時間をかけて、腕を振り下ろした。恐怖だけがあった。気が狂ってしまいたくても、張り付けにされた自我は恐怖以外の感情を抱くことを許さなかった。
やがて剥き出しのこめかみに鉄塊がめりこみ始めた。激しい衝撃。痛みを感じてから、しばらくして痛みを理解する器官が失われ、それでもなお想像がイサキ博士を苦しめた。抉られていく。
もう助からない。戻れない。死にたくない。
助けて、誰か。
嫌だ。
音のない絶叫。
PLAYはそれを魂に刻み、初めと終わりを筒状に縫い止めた。ヨツヤ・イサキは恐怖と絶望に悶え苦しみ、箱の中の意識が消えるまでの間、死の瞬間で永久に溺れ続けた。
箱の外では一瞬だった。
オキザリスは自らのこめかみを右腕で薙ぎ払い、その衝撃で、首が潰れた。跡形もなかった。
心拍計がフラットラインを記録し、全ての計器が沈黙した。
肺が大きく息を取り込んだ。
焦げ臭さと化学物質の刺激臭がそれをきつく苛んだ。熱い。最初の感覚は全身の灼けるような痛みだった。吸った息が咳になって吐き出された。吐ききった後も、呻きが喉の奥から勝手に滴った。身体がうまく動かない。目の前に投げ出された四肢が見える。力を入れると震えた。それでようやく、自分とそれが繋がっていることがわかった。どこかを動かそうとする度に、脊髄に電流が奔る。びくん、と細い指先が跳ねる。
手首を返すと、掌がどちらも真っ赤に爛れている。ずいぶん酷く擦りむいたらしい。
目の前に真っ黒なカーテンがあって邪魔だった。何度も頭を振ってはね除ける。自分の髪だった。雨が毛先を重く束ね、瓦礫と粉塵、細かいガラス片を伝う。服の下で水滴が皮膚を滑り落ちていく。雨粒が身体を叩く度、心臓の鼓動と混ざって低い音がする。
両腕でやっと胸から上を起こし、水溜まりに両手と膝をついて身体を支える。身体の下で、水が鏡になっている。波紋に揺らいでよく見えない。じっとしているうちに、波が止まった。チカ嬢の顔。
キララは自分のものになった顔に触れた。
柔らかい。それに、血塗れだ。
どうして消えてしまわなかったのかは分からなかった。でも、分かる気がする。彼は目を伏せた。
この力を使おうとした時、アキヒサも、あいつも、諦めてたんだ。自分を空っぽの器にして、魂を受け入れようとした。
自分の光を救うためなら、犠牲になっても構わない。そう祈ったんだと思う。
俺は逆だ。俺は、悪の帝王だから。
よろめきながら立ち上がって、足を踏み出した。身体中の皮を剥がれたようだった。
そこらじゅうに破滅が撒き散らされていた。溶けたビルの残骸、砕けたコンクリート片、墜落と崩壊に巻き込まれ、真っ黒になった人間の亡骸。雨の中で、細かくなったガラスが光の粉になって空気中を舞っている。紫解のビルだった瓦礫の山に囲まれて、目の前には黒い布のかかった巨大な鉄塊が転がっていた。
やたらに大きな手が布の下からはみ出ている。人を模した形のようにも見えるが、その首は轢き潰されたように削がれていた。
「オキザリス」
頭の骨に自分の声が反響した。散々聞かされてきた舌足らずで甘ったるい声が、くぐもって聞こえた。
「オキザリス……俺だ」
首なしの鋼鉄の身体を揺さぶろうとするが、重すぎてびくともしない。
「俺だ、キララだ。訳分からんだろうが、博士じゃない、俺なんだよ」
反応はない。
「なあ。俺ら、あのクソ野郎に勝ったんだぜ。オキザリス。お前がぶん殴ったのは博士で、俺は、俺、今、まだ、生きてて、ああ」
首のあった所から無色の油がどろどろ流れて、コートの下の水溜まりを汚染している。
「……オキザリス……」
胸のフラッシュライトが点きっぱなしになって、黒い布の隙間から漏れていた。銀とも虹ともつかない光に雨が跳ねる。
「……死んだのか。なあ、おい……」
モーターが小さく唸った。
「!」
水に浸かっていた右手が動き、指一本ずつ拳を握った。『いいね』を示すサムズアップの形。
そのまま持ち上がった。握った手の形のまま、親指を突き出して瓦礫の向こうを指す。無数のスケアクロウたちが夢遊病の足取りで群れをなし、光を探していた。
わざわざ人差し指に変えないのが、効率を重視するオキザリスのやり方だった。
腕はやがて力尽きるようにゆっくりと、地面に降りていった。金属が再び水に浸ると、鈍い音がして、虹に波紋が泳いだ。
「……ありがとう」
それは一般的に、機械には使わない言葉だ。
文字が見える気がして、キララは笑った。
自分の片割れを失うような痛みだ。でも、お前には分からないだろうな。機械の腕に小さな手を重ねて、彼は囁いた。
「ありがとう、オキザリス」
フラッシュライトが一度だけ瞬き、消えた。もう二度と点かなかった。
「………」
キララはよろめきながら、指の示した方へ歩き出した。行かなきゃ。あいつを迎えに行くんだ。銀色のさざめきが大きくなった。