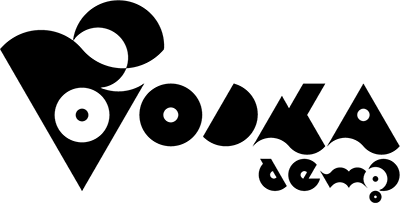「アキヒサくん、久しぶり」
あどけない顔の少女がこちらを覗き込み、千切れんばかりに両手を振っている。歳は8歳だか、9歳だったか。艶やかな黒髪を三つ編みにして、両肩に長く吊り下げている。鼻にかかって甘えるような、舌足らずの話し方。
「元気にしてた?オキザリスとは仲良くしてるよね。アキヒサくんのほうからお願いがあるって、パパびっくりしてすごく喜んでるよ」
ほら見ろ何も聞かなかった、とキララは思う。博士にとって他人の事情は、他人が見た夢の話よりも無意味だ。人として足りないものが多いあの男の人格に、『人の話を聞く』能力は当然欠落している。
「研究所でお話したいって。鍵は開けておくから、7日後に。パパをがっかりさせないでね!じゃあね」
〈再生終了〉
キララは横になったまま、右の掌で顔を覆った。視界が暗くなるだけで何の意味も成さなかった。
博士は人の嫌がることを進んでやる人間だ。
結局文字でのやり取りが一番効率的だ、と人々が気づいたこの時代に、わざわざビデオメッセージなんか使うのは博士くらいしかいない。そしてその理由は当然、被験者への嫌がらせだ。彼の手で行われた所業を知るものは皆、彼の娘の顔を二度と見たいと思わない。あの男の類まれな行動力は、今の自分にとっては見習うべき姿勢かもしれない。
「削除して字に起こせ」
〈7日後にリマインダーを設定。紫解A.R.開発研究所〉
7日。
7日。
頭の中で数字を繰り返す。彼は指の間からインターフェース越しに、自分の家の天井を眺めた。
時刻は昼の11時。明け方に帰ってきたにしては早く起きたほうだ。普段はワンルームに転がしたソファで寝ているが、今朝はそれを譲って床の真ん中に毛布を敷き、コートを日除けにした。
ぼたぼたと窓ガラスに雨粒がすがりつく音。ブラインドの隙間から見える空は、限りなく白に近いグレーで均一に塗り潰されている。
窓の下、壁の角に置かれた3人掛けサイズのL字カウチソファの上を見る。人影はない。
飛び起きたキララはソファの位置と窓枠の足がかりの良さから最悪のケースに思い至ったが、狭いキッチンの方向から冷蔵庫の扉の開く音がするのを聞いた。そしてすぐに閉じる音。
彼の『器』は、電源の入っていない冷蔵庫の扉を物憂げに撫でていた。
「にいちゃん!おはよ……」
スケアクロウは床の軋む音に振り返り、力なさげに微笑む。キララは無反応に静止したのち、ソファの横に煩雑に積み重ねられた段ボール箱に手を突っ込んだ。そこから液体食料パックをふたつ掴み取り、ひとつを放って渡した。
パックは一般成人が片手で握れるくらいの大きさだ。四方を熱圧着した銀色の袋で、短いチューブがついている。中の見えない無機質なパッケージには、使用期限と紫解社の紋章以外、何も描かれていない。
彼がチューブのキャップを外すのを見て、スケアクロウも同じようにした。マスクをずらして口元の構造を剥き出しにしたキララは、チューブを咥えてパックを握りつぶす。スケアクロウも同じようにしようとして、凍りついた。パックを持つ手が小刻みに震えている。吐きだすべきかどうか迷っているように見えた。
そりゃそうだ、とキララは思う。サイボーグ食は口から食うもんじゃない。彼が経口摂取するのは博士の思し召しによるものだ。
ネットに投稿された物好きの味見によれば、それは洗剤と同じ刺激臭で、子供の玩具の誤飲防止用塗料よりも苦いそうだ。しかしこの家には他に食料がない。
キララは空になったパックを冷蔵庫の脇のゴミ箱に投げつけた。狙いは外れて脇に落ちた。
スケアクロウは涙ぐむ目でそれを見ていたが、片手で鼻をつまみ、意を決した表情でパックを握り締めた。かろうじて吐き戻す前に飲み込んだようだった。
ゴミ箱の中心にゼロ距離ストライクを決め、戦いを終えた青年は得意げに視線を向けた。キララは部屋の壁にかけられたテレビを見ていた。
「………次のニュースです。ロボット・電子機器開発産業の紫解オムニクラフト社は本日、新たにアンドロイド・スケアクロウを100体、治安維持局に納品しました」
畏った佇まいをした仮想アナウンサーの3D映像に合わせて、男声自動音声が淡々とニュース原稿を読み上げる。スケアクロウもそれを見た。この家に入ってから、32型の液晶テレビはとめどなく極彩色を瞬かせ続けていた。就寝中も休みなく流され続けていた放送で、スケアクロウ素体はいくつもの新しいことを学んだ。自分の仲間たちのことも何度か話題に登っていた。
「本日午前10時頃、セントラル区のチヨダシティにある治安維持局チヨダ支部では、最新式アンドロイド・スケアクロウ100体の導入記念式典が行われました。治安維持局では近年のセントラル区の犯罪増加に対処する人材不足が深刻化していましたが、チヨダシティはセントラル全地区で7番目に導入を決めた自治体となり、治安の改善に期待が寄せられています。
スケアクロウは紫解オムニクラフト社の主力製品で、燃費の良さや量産の容易さ、機動性の高さなどを評価され、既に6つのシティに導入されています。電力の代わりに、市販されている機械義肢用の流体燃料をエネルギーとして使用し……」
参考映像と書かれたテロップが画面の左上に小さく表示され、紫解社によるエネルギー補給のデモンストレーション映像が流れる。流線型の背筋をS字の竿竹のように立てたスケアクロウのCG映像。脇腹に、車のガソリン給油口に似た小さな開閉式の蓋があり、そこに今しがたゴミ箱に放り込まれたのと同じ銀色のパックが差し込まれる。画面の前の金色の目は、ゴミ箱、ベッド横の段ボール、そして自分の背後で気怠げに立ち上がるキララを飛び跳ねて往復した。自分の黒いシャツをそっとめくって確認するが、肌に蓋はない。
映像はスケアクロウがいかに従来のアンドロイド製品と比べて革新的で優れているかを、聖典を読み上げるように朗々と説いた。
スケアクロウは電力を必要としない。流体燃料の摂取によって、熱エネルギーで稼働する。
有機硬化素材……これはエビやカニなどの甲殻類から着想を得たそうだ……によるアーマーで覆われているため、軽量かつ優れた防護性能を誇る。
有機素材のため、破損した際には容易に焼却廃棄することができる。アーマー以外の部分には地面に還る特殊硬化プラスチックを使用しているため、有毒物質や大気汚染ガスを極力発生させない。
トウモロコシを印刷原料とする有機3Dプリンタによって複製されるため、量産にコストを必要としない。
従来の二足歩行型に比べて敏捷性が高く、平衡感覚に優れる。自律式の思考ルーチンを持ち、状況に対して柔軟に対応することができる。
スケアクロウ以前の二足歩行型アンドロイドは、それはそれは無骨で親しみづらい鉄塊のような見た目で、景観にもよくなかった。第7世代スケアクロウは海外から招いた著名なコンセプトカーデザイナーが設計を担当しており、調度品のような優雅さを持つ。場面はデザイナーの事務所に移り、椅子に腰掛けた誠実そうな顔立ちの若い男が語る。
「街に彼らが並ぶ姿は美しいでしょう?曇りない鏡のようなビジュアルは犯罪者に己を顧みさせるためです。イルカを思わせる知性的で優美なボディラインは、アールデコとレトロフューチャーから着想を得ています。人類文明の発展が明るい未来を象徴している時代の、まさに実現です」
映像はセントラルの様子に戻る。鮮やかなシアンとマゼンタの光がアスファルトの水たまりにちらつき、それを雨粒がしきりにかき乱す。配備された新たなる守護者たちが横一列に堂々と立ち、一糸乱れぬ足取りで、混沌の街へ向かって歩き出す。雨が彼らの銀色の装甲を濡らし、滑らかなコーティングの上で小さなプリズムが七色の光輪を伴って乱反射する。
「虹……」
スケアクロウ素体は誰に言うともなく囁いた。
唐突にテレビは暗転し、別の映像を映し出した。画面には子供がクレヨンで書いた風の、『きょうのまいも』というカラフルな文字が踊る。
世の中どこに逃げても逃げ場がない。ようやくソファの座面の隙間からリモコンを発掘したキララは、心の中で悪態をついた。何もかも悪趣味なジョークだ。最も気に入らないのは、このテレビは電源部分が致命的に壊れていて、一度消すとおそらく二度と蘇らない、ということだ。24時間付けっぱなしにせざるを得ないが、無音よりはマシ、という以上に意味のある放送はない。
「きょうはエクストラ市のイシノさん宅にお邪魔しています。あらあら、たくさんのまいもちゃんにお出迎えしてもらいました」
「5匹飼ってるんです。さしみちゃん、しらすちゃん、すじこちゃん、ひらめちゃん、かれいちゃん」
「あらあ、お魚のお名前なんですね」
マイモは蛾の遺伝子を小型の小動物と交配させて作られた、芝生のような毛で全身を覆われた白い生き物だ。温和な性格で、人懐こく柔らかい。『自由気ままで甘えんぼ』なペットとして一般的に広く愛好されているが、キララはこの身体になる前からずっとマイモが嫌いだった。マイモを飼う人間は、他のすべての人間もそれを愛することが義務である、と強要してくる。キララの拒絶は子供の頃、無理矢理膝に自分の背丈の半分くらいあるマイモを乗せられた時まで遡る。
マイモは不気味だ。自由気ままと言われる通り、何を考えているかわからず、まともに意思疎通できない。人を恐れず、重さもサイズも5kg米袋程度の物量が躊躇なく顔面に飛びかかってくるのはかなり恐ろしい。大きさに対し奴らは異様に俊敏に動く。体の大きさに対してこぼれそうな2つの黒い目玉は、ぽろりと取れてしまわないか気が気でない。そもそも奴らは虫だ。蛾だ。羽があるし、触角もあるし、毛むくじゃらの足が6本もある。
「それでは、本日のまいも吸いタイムです!ひらめちゃん!失礼しますね」
テレビの画面ではリポーターの若い女性が、一匹のマイモの体を掲げるようにして持ち上げ、脇腹に顔を埋めて深呼吸している。
「にいちゃん」
魚の名前をつけるなら魚を飼えばいい、と思う。魚は人間の生活に干渉しない。向こうは水、こちらは空気で別々に暮らせば良い。キララは飼っていた熱帯魚のことを思い出した。
「にいちゃん……」
ゴミ箱の脇、部屋の中にかつて熱帯魚のいた名残を見て、キララはそこまで頭の中で捏ねくり回していた一切合切をどこかに吹き飛ばしてしまった。
水槽台の上の割れたガラス水槽に、見慣れない赤い縁取りがついている。その脇で立ち竦むスケアクロウの手のひらからは、白い肌に対を成す鮮血がぼたぼたとこぼれていた。床に滴る痛々しい液体は、空気に触れてゆっくりと透明に変化していく。
キララは間にある家具を全て蹴散らす勢いで駆け寄ってスケアクロウ自身の反対側の手で傷を塞がせ、頭上に掲げさせ、メトロノームめいて激しく左右に振った。
「絆創膏!」
〈室内を検索。半径10m以内に非検知〉
「止血器具!」
〈非検知〉
「もう何でもいい!」
〈検索不能〉
キララはスケアクロウの両腕を片手でいっぺんに握って掴み上げたまま、空いている方の手で周囲に積み重ねられた乱雑なものを漁った。仕事道具を置いた棚の中にセロハンテープがあった。
他に役に立ちそうなものは見つからず、仕方なくスケアクロウを洗面所に連れて行って念入りに手を洗わせた。濡れた手をハンドタオルで拭き、乾いた傷をセロハンテープで軽く、出来る限り慎重に巻き止めた。
キララは黒いビニール袋に床を拭いた雑巾、蹴り散らかした机の上にあったどこにも行き場のなかったもの、割れた水槽と魚にまつわるもの全てを放り込んで口を縛った。始末屋の性分が染み付いたものか、その手際は彼自身感心するほどだった。
〈面倒見がいいな〉
オキザリスの投稿には「いいね」のサムズアップマークが添えられている。
「俺の身体だ」
彼は熱帯魚を全滅させた時の、耐え難い虚無を思い出した。水槽を割ったときのことは今でも記憶に新しい。小さなアクアリウムの中身は全て床に投げ出され、魚は衝撃で死んでいた。覆水盆に返らず、という言葉の通り、ただただ眺めることしかできなかった。二度と生き物は飼うまい、と誓いを立てて、彼は砕けたガラスの残骸をそのままにしたのだった。
7日。
7日……ソファに座らされたスケアクロウはセロハンテープのつやつやした表面を窓の光に照らし、珍しい現象でも見つけたように眺めている。こんなにもあの博士の顔が恋しくなる日が来るとは、夢にも思わなかった。
テレビの時報が正午を告げた。
金物のぶつかり合う鐘めいた音に、スケアクロウは視線を引き寄せられた。テレビの横にある傾いたスチール製の棚を、頑強な手の甲で叩く音だった。壁に背を預けたキララは画面の中の『お昼のニュース』の文字を指で示し、相手の様子を伺った。
「おひるのニュース?」
字は読めるんだな、と得心して、キララは雑多な機器類が乗った棚を塞ぐようにA4サイズのコピー用紙を何枚かテープで貼り付けた。そこには台とは逆方向に傾いた、右上がりで極太の書き文字。それは無骨で角ばっていて、しかし妙に有機的にも見えた。
『家から出るな 何も触るな 俺は仕事に行く』
真ん中の言葉は下線で特に強調されている。彼は繊細な作業の不得意そうな手で黒のサインペンを握り、紙の下方の空きスペースに新たな文字を書き足した。ペンの背でそれを叩く。
『わかるか』
「うん。いってらっしゃい」
スケアクロウはソファの上で頷き、はにかみながら答えた。
「あの……にいちゃん……なんか、おいしいものを……」
『飯を買って帰る』
「やった!ありがと!」
キララは彼の体格に対して小さく見えるボディバッグや、スケアクロウには何なのか分からないいくつかの小物を背中や胴、足にくくりつけ、その上からコートを羽織った。背を屈めて玄関から出ようとして、すぐに一旦戻ってきて、コピー用紙の『何も触るな』の下に文字を付け足した。
『PSIも禁止』
「まかせて!」
いってらっしゃい、と見送るスケアクロウを部屋に置いて、彼は雨の中、濡れるまま扉を閉めた。オートロックが電子音とともにサムターンを回転させて鍵をかけ、鉄塊の歩き去る音は雨に紛れて遠ざかっていった。
部屋には自分の呼吸とテレビの囁きだけが残った。スケアクロウはソファの上から部屋の中を見渡した。ささやかなワンルームの壁は突然、途方もなく遠くにあるように感じられた。
ここは殺風景と雑然さの混じり合う奇妙な部屋だった。家主の几帳面さとそれに釣り合わない手の不器用さを象徴するようだ。家具はそれぞれ幅を広く取って設置され、その隙間には何かの意図を途中で放り出したかのような混沌が撒き散らされている。様々な書類や何らかの機械部品、スパナ、小銭、印鑑、ペン、銃弾の箱、空の薬莢、バネ、プラスドライバー。
腰掛けたソファの座面は普段乗せている重量に耐えきれずに、横になった人間の形にへこたれていて、よく見ると座面と背もたれの間は後からつけた金具で何重にも補強されている。先ほどの流血沙汰で蹴散らされたせいでその上だけ片付いたダイニングテーブルは、シックで落ち着いた黒い木製で、細く丸い足の優雅なシルエット。足は一本折れていて、黒いダクトテープを巻いてなんとか繋ぎとめられていた。その脇の椅子は机に全く不釣り合いな、頑丈さだけが取り柄の素材とデザインでできている。
テレビの横、コピー用紙が貼り付けられたやや傾き気味のスチール棚には、丁寧に整備されているであろう様々な銃器や工具、彼自身の仕事と身体にまつわるものが、ラベルを貼った小さなコンテナにそれぞれ整えて並べられている。しかしその横には開けっぱなしの工具箱に、何に使うのかわからない雑多な機器がぞんざいに突き刺してある。玄関の横にも似たような棚があって、そこには業務用ゴミ袋のストックが大量に保管されていた。
台所は直近でほとんど使用された形跡がない。洗濯機の置かれた洗面所は、少し曲がった蛇口が丁寧に磨き上げられ、タオルだけは数も種類も妙に多い。風呂には用途不明の、掃除機かSci-Fi銃かわからないノズルとコードのついた機械。トイレは予想外に普通だが、壁やドアには所々なにかをぶつけた痕があって凹んでいる。
ひとしきり室内を探検してみて、スケアクロウはひとつ興味深いことに気づいた。水槽が割られスチールの棚が傾いているように、今まで見てきた家具や壁、家の中にあるすべてのものは例外なく、一度は破壊されたあとがあった。そしてそれらは、強い感情を封じ込めて補修されていた。過剰なほどに幾重にも巻かれたダクトテープは、悲鳴と咆哮に似ていた。いとも簡単に壊れてしまうもの、そして何より壊した者への、憤りと深い失望。
自分の手のセロハンテープに目を落とす。同じ人物が貼ったものとは思えなかった。部屋は孤独と諦めで満ちていた。
再びソファの上に戻ってきて、彼はブラインドの隙間から灰色の空を見上げた。
窓の外の風景は吹き付けては流れていく水滴に滲み、白い薄霧のベールに覆われていた。雨は降り止みそうになく、スケアクロウにはその光景がひどく胸を締め付けるように思えて、いつまでも目をそらせなかった。
ep01,酷い趣味のAI
男は背中からアスファルトに叩きつけられた。強化骨格の背骨が折れる音がした。
ep02,空の器
トラックの助手席に座った男は、あくびを噛み殺しながら、自分が何秒間瞬きせずにいられるか数えていた。
ep03,奉仕のかたち
ボックス席の脇のレールを走る皿。その上に乗った小さな寿司。流れては去っていく皿を、顔を近づけて追いかける金色の目。住宅地郊外の大通り脇の回転寿司。24時間営業のチェーン店だ。深夜と早朝の境目の時間、カウンターの他にファミリー向けのボックス席…
ep04-A,その場凌ぎ
「アキヒサくん、久しぶり」あどけない顔の少女がこちらを覗き込み、千切れんばかりに両手を振っている。歳は8歳だか、9歳だったか。艶やかな黒髪を三つ編みにして、両肩に長く吊り下げている。鼻にかかって甘えるような、舌足らずの話し方。「元気にしてた…
ep04-B,防御反応
ヒシダ第一コーポラス・一階防災センター。「なんだあ」壁一面の監視モニタのひとつが赤く光り、警備員の男は気怠げに声を上げた。男は誰も見ていないのをいいことに、パイプ椅子を3つ並べてビーチサイドのサマーチェア状にしていた。だらしなく寝そべったま…
ep05,光
キララはうつ伏せに横たわって、顔の目の前にある硬い金属の手を眺めた。未だにそれが自分のものだと気づくまでには、時間が必要だった。身体を起こすと、知らないうちに肩にかけられていた毛布がソファにずり落ちた。いつの間にか眠りこけてしまったらしい。…
ep06,嘘のつきかた
スケアクロウはみんな死を恐れてる。だから人の命令を聞くんだ。キララは『弟』の言葉を反芻した。紫解Augmented Robotics、通称紫解A.R.の研究施設は、丁寧に刈りそろえられた緑の芝の真ん中に浮かぶ、真っ白な陸の島だった。まとわり…
ep07-A,心変わり
「このままあいつに会いたくない」身体中に透明な血がこびりついて、見えない錆と染みに塗れている気がする。そう呟いたキララに答えて、オキザリスは自動無人洗車機をサジェストした。研究所を出て、地平線が見える程拓けた道路を辿って歩いていくと、持て余…
ep07-B,願望
打ち付けられたドアから、水飛沫が飛び散った。午前三時過ぎのアパートの外廊下を、鈍重な鋼が打ち鳴らす。キララは抗おうとしたが、AIは迷いなく鉄の身体をすたすたと歩かせた。明かりが消えたままの二階の角部屋が背中に遠ざかっていく。「おい」苛立ちよ…
ep08,兄と弟
東から淡く昇りかけた陽が、ヒシダの駅前に乗り捨てたスケアクロウ用バイクの流線を瞬かせた。バイクで移動できる範囲内でセントラルラインに接続しているのは、ヒシダ駅だけだった。始発が動き始める時刻のせいか、いつに増して人影はない。二人は駅の外壁に…
ep09,勇気
雨が降っていた。夜のシンジュク駅前を往来するPVC傘の流れは、街中に瞬くシアンとマゼンタをあちこちに転写し、その下に透ける人々の顔はただ影でしかなかった。キララの大柄な姿は透明なビニールの水面から頭ひとつ出て、ようやく足のつく浅瀬の波をかき…
ep10,訣別
『全権委任』。他に言葉は要らなかった。オキザリスはキララの手を取った。目の前を飛び去っていくままだった外壁へ、重機の指が爪を立てた。不時着する飛行機のように激しく振動しながら、オキザリスは墜落を止めようと試みた。雨の中に煌々と火花が散り、指…