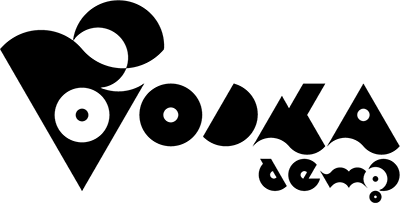いつものように狩場の丘へ向かうと、見慣れない光景を目にした。
丘へ近づくと、わたしの乗る虎の咆哮を聞き、野兎の群れが巣穴から飛び出してくる。これを仕留めて家へ持ち帰るのがわたしの日課だ。
野兎は非常によく利く長い耳と、鉄板をも貫く鋭い牙を持っている。体の大きさこそお伽話に登場する『ウサギ』と同じ位だが、小さくとも魔物であることには変わりない。野兎は音を察知して敵を見つけると、その鋭い牙を剥き出しにして一斉に飛びかかってくる。鉄板を幾重にも貼り付けた虎の側面に、弾丸のように突き刺さる野兎たちを、そのまま持ち帰って捌くのだ。
今日は先客がいた。丘の上には兎どもよりも大きな影がひとつあった。時折迷い込む旅人や盗賊の類かと目をこらすと、それは魔物の一匹に覆い被さって押さえ込み、生肉を食い千切っているようだった。兎たちは仲間の血の臭いに怯えて巣穴へ駆け戻っていった。
近づいてみるとそれは人間であった。少なくとも見た目は。わたしは投網でそれを捕まえて、兎の代わりに家へ持ち帰った。
頑丈な檻を選んでそれを入れ、よく観察することにした。
確かに人間だと思う。歳若い男だ。もしかしたら、まだ二十も行かない子供であるかも分からない。分からないのはそれが見た目以外は殆ど人間とは呼び難い振る舞いだからだ。
檻越しに離れて立つわたしを認識してはいるようだが、目の前の何かを獲って食いたいという意志以外は、知性の欠片も感じられない。檻の隙間から虚空に向かって腕を伸ばして振りかぶったり、檻にかじりついたりしている。兎を食っていた時は四つ足で歩いていたが、獣とは違い手でものを握ることはできるようだ。檻を掴む手はよく見ると左手の指がいくつか欠けている。目は虚ろに濁っているが、蓄光素材のようにぼんやりと緑色に薄く光っている。ずっと何かを呻き続けているが、何かの言葉ではなく、獣の鳴き声という訳でもない。特に理由もなく喉から声が出るに任せているだけのように見える。開けた口を見ると舌はあり、歯並びに牙などはなく、人のそれと同じようだが涎が垂れ流しだ。ぼろ布を纏っているのは、かつて人として過ごした日があった証なのか、ただそういうものを巻く習性が頭の片隅に残されているのか。
これまでに数多くの獣を見てきたが、人の姿をした魔物というのは初めてだ。捌いた野兎の肉を檻の中に放ってやると、それは素早く肉を宙で捕まえ食らいついた。姿は人だが、やはり紛れもなく魔物だと思う。
それを檻に入れてから三日が経った。捌いた兎を毎日与えているが、特に変化はない。そこで燻製にして置いてあった熊の肉を与えた。熊の肉は兎よりも深く呪われた猛毒だ。しかしそれは、丸ごと一匹をあっさりと平らげても平然としていた! 呪いに強い体質の人間でも、燻す煙を吸っただけで数日もがき苦しむような代物だというのに!
六日目だ。その日は虎を出して家から少し離れた荒野に出ていき、馴染みのキャラバンと取引をした。
狩人として彼らキャラバンと共にあちこちを回った日々は昨日のことのように思えるが、もう十数年も前のことだ。魔物やその呪いから身を守るために鎧を着込んだわたしの姿は、この歳になっても彼らの畏怖の対象であることには変わらないらしい。『肉捌きのアリサ』が来たと聞くと、彼らは貴重な酒を一杯注いでくれた。
キャラバンの護衛の若い狩人達と話すと、丁度その日は大きな魔物と対峙して、六人がかりで辛くも打ち倒したのだという。わたしはその死骸を捌いて有用な部位……皮や、体内に残った犠牲者の遺品などのことだ……を彼らに渡すと、余った肉を譲り受け、持ち帰った。人間の三倍の背丈はあるような巨大な鹿の魔物だった。
兎、熊、大鹿と餌を与え続けた所為か、初めの頃に比べてそれにも少しだけ変化があった。それは元々特に理由もなく呻き声を上げ続けていたが、わたしの姿を見ると口を開くようになった。「う」が「あ」に変わるということだ。
わたしが最初に考えていたよりは知性があるように思える。金持ちの中でも奇特な趣味の持ち主は、魔物を飼い慣らしてかつての『イヌ』や『ネコ』のように愛玩動物として扱うこともあるらしい。人の姿をした魔物なら、獣よりも芸を覚える見込みはあるのではないだろうか。
そこで檻の前で、肉を与える前にひとつ試してみることにした。わたしは自分の顔を指し、自分の名を言った。根気の要る日々ではあったが、ひと月も繰り返すとついにそれは、わたしの顔を見て名にかなり近い言葉で呻くようになった。「あ」と「う」なら獣でも鳴けるが、「り」が言えるならそのうち言葉も話せるだろう。
それからは、檻の中やそばにあるものの名を、肉を与えながらひとつずつ教えていった。
そのうち、たどたどしくも意思の疎通ができるようにまでなった。これも苦労したが、肯定と否定を覚えさせたおかげだ。
肉を見せて、これが欲しいか? と問う。イエスなら「あ」、ノーなら「う」だ。
空腹か?
あああああ。
おまえは人間か?
う。
おまえは魔物か?
うう……。
どちらかわからないのか?
あ。
ではこういう聞き方に変えよう。わたしとおまえは同じ生き物だと思うか?
う…………。
自分がどこから来たかわかるか?
う。
どうしてこうなったのか覚えているか?
…………うう。
腹が減っているか?
ああああああ。
曰く、腹が減る。際限なく腹が減る。ただ魔物を追い、捕らえ、食らい続けてあの丘まで来たという。
魔物は呪いによって姿を大きく変えた獣だ。旧い世界の人々がもたらした大いなる災厄によって、この世は呪いで満ち溢れた。ひと息吸えば命を奪うような呪いの力に抗うべく、この世の生き物の肉体は例外なく、その理を自らの『生き延びる』という本能に沿って書き換えた。魔物の身体は瘴気によって再生する。脚を捥いでも、皮を削いでも、とどめを刺さないかぎり時間さえ経てば際限なく蘇る。
この災厄の後の世で、人間は常に食べるものに困窮している。魔物は呪われていて、人が食べれば死ぬからだ。わたしたちは旧き人々の残した遺跡を漁り、そこに残された保存が利く食料を得て日々を凌いでいる。暮らしている人間の数もかつての世界に比べればごく僅かだが、食料と水を巡って争いは常に絶えない。わたし自身も人が飢えて死ぬのを何度もこの目で見た。
だからわたしはこの十数年を、肉を捌くことに費やしてきた。
魔物を食べることができれば、人の世はずっと豊かになる。その方法を探すためにわたしはここに住処を構え、長い間様々な方法を試してきた。
結局人間は呪いに弱く、すぐ死んでしまう。魔物に生まれ変わる程の本能はなく、臓物には瘴気を消化する力もない。そう結論づけて、この頃は半ば諦めかけてもいた。……だが今わたしの目の前にいるのは新しい希望だ。檻を掴む手を見ると、欠けていた左指もいつの間にか五本生え揃っている。
人が魔物に成れるなら、その魔物を人に戻す方法さえあればいい。
わたしは人と魔物の境目を考えた。
そういうわけで、彼に名前をつけてやることにした。
元々人であったならこうなる前の名残があるのではないか、と、彼の巻いていたぼろ布を檻越しに調べてみたが、特に手がかりはなかった。
先だって鹿の肉を捌いた時、キャラバンから礼の代わりに、その時使ったナイフを一振り譲り受けた。柄に刻まれた旧い世界の文字は『アレキサンダー』。孫も子もないわたしには名付けの才はないが、大いなるものの引用であれば悪くはないだろう。
名を告げて、気に入ったか?と尋ねてみると、肯定とも否定とも取りづらい曖昧な呻き声が返ってきた。後で気づいたが、あれはおそらく復唱だったのだろうと思う。
言葉を話すためには、言葉を聞く必要がある。丘に兎を狩りに行くのに加えて、彼に語りかけるのもわたしの日課になった。
長い間独りで暮らしてきたので、話すべきことは特に思いつかなかった。そこでわたしは自分の昔話をした。毎晩毎晩、少しずつ話をした。
幼い頃は水を運ぶキャラバンの一員だった父と共に旅をした。その一団が野盗に襲われて壊滅してからは、すんでのところで命を救ってくれた狩人の男の元で育ち、仇討ちのために自分も狩人となった。
あっさりと復讐を遂げてからは、命の恩人を助けて暮らした。彼は誇り高き屈強な男だったが、ある年に荒野の真ん中で飢えて死んだ。残されたわたしは朦朧としてあてもなく荒野を歩き、偶然にも別のキャラバンの一行と出会い、遺品を売って生き延びた。それ以来はずっと独りでこの暮らしだ。
この家は、かつての世界では警察署というものであったらしい。だから頑丈な檻がいくつもある。警察というのは罪を犯した人々を裁くものであったと聞く。そんな場所にわたしが住むというのも皮肉なものだ。
「にく」
「皮肉、だ」
そういう話をする頃には、アレキサンダーは片言ながらも言葉を話せるようになっていた。
「わたしは沢山人を傷つけてきた。わたしは悪い人間だ」
「うう、う」
彼は否定して呻く。
「なぜそう思う?」
「アリサ、にく、くれる」
「なるほど。おまえにとってはそうかもな」
檻の中は日の光も射さず、とても暗かった。濁った緑の目はその闇の中で光り、流れる言葉を遮りもせず、ただ聞いている。良い聞き手がいるというのは、何もかも洗いざらい話してしまいたくなるものだ。
「もう昔話も大体話し尽くしてしまった。わたしの懺悔を聞いてくれるか」
「ざんげ」
「どれだけ悪いことをしてきたか、という告白のことさ」
おまえの今入っている檻は、人を入れるためのものだ。
ここはキャラバンの通り道からも離れて、近くに村もない辺鄙な場所だ。しかし時折、道に迷った旅人や野盗、野盗に襲われたキャラバンの生き残りが訪れることがあった。そしてあの丘で野兎の巣に出会い、身動きが取れなくなる。下手に音を立てれば死ぬからだ。
わたしは彼らを見つけると、虎に乗せて連れ帰った。そして長年研究してきた『食事』を振る舞った。もちろん魔物の肉だということは明かさずに。
人間が呪いを身体に取り込むとどうなるのか、実に様々な反応を見てきた。その場でのたうち回るもの。食べた直後は平然としていても、時を追うごとにみるみる衰弱していくもの。青ざめるもの。全身に妙な斑点ができるもの。痙攣するもの、吐くもの、泣き出すもの。はじめの頃は、大抵は皆数時間のうちに死んだ。
わたしは少しずつ彼らを生き長らえさせる肉の捌き方を学んだ。肉を食う魔物の肉は毒が強いが、そういう獣が獲物にする、草を食べるようなやつは人間が食べてもすぐに影響は出ない。内臓を取り除けばより呪いの反応を先延ばしにできる。生よりは火を通したほうが良い。種類によっては焼くより煮込んだほうが良い。そうやって、長くて三日は保たせることに成功した。だが、三日もあるとわたしのやっている事は明らかになる。身体の異変とその理由を察して逃げ出そうとする彼らをここへ留めておくために、この檻のある建物はとても理に叶っていた。死にゆく人々はわたしを魔女とか、人の姿をした化け物と呼び罵った。
三日。わたしはどう頑張っても三日より先まで人の命を保たせることはできなかった。一年に一度か二度迷い込む実験の機会を何回費やしても、人間が魔物を口にして生き長らえることができる時間は、三日が限度だった。家の裏に墓を掘って死んだ人々を埋め、彼らが遺したものをキャラバンに売って水や缶詰と交換し、わたしはそれを食べて暮らした。そうして何年も何年も経った。
それでもわたしは信じている。人間が魔物を食べることができるようになれば、この世はずっと豊かになる。だからおまえは大いなる未来なんだ、アレキサンダー。少なくともわたしにとっては。
「アリサ」
「なんだ」
「……わからない」
「そうだな。おまえは魔物だ。だが人間になれ。それがわたしの願いだ」
そうだ、おまえに服でも見繕ってやろう。そう思って久方ぶりに馴染みのキャラバンと会うと、そのうちのひとりが血相を変えて駆け寄ってきた。ある男の名を聞かされて、知っているか?と尋ねられた。
知っていた。いつかずっと昔、わたしの家で夕食を食べ、のたうち回って死んだ男の一人だ。男の遺品は珍しい石でできた首飾りで、キャラバンはしばらく暮らせるだけの水と引き換えてくれたので、記憶に深く残っていた。わたしは答えずに、なにかあったのか、と尋ね返した。
男には息子がいたのだという。首飾りは偶然にもその子のもとへ渡り、彼は父がもはやこの世にはいないことを知った。そして長い月日をかけて形見の流れてきた道を遡って、彼は誰が仇であるのかを突き止めた。
彼は今や復讐に燃える腕利きの狩人となり、馬を駆って、もう明日にはここへ辿り着く。わたしはキャラバンの男に、『肉捌きの魔女アリサは決闘を受けて立つ。夜が明ける頃、荒野を越えてこの丘へ来い』という言伝を頼んだ。
わたしたちは戦った。
結論から言えば、わたしはまた生き延びてしまった。だがもう長くはない。若い狩人は野兎に噛まれて死んだが、彼の銃はわたしの鎧の隙間を何度も見事に貫いた。
流れ出る血をそのままに、痛みに悶えながら虎を走らせ、わたしは帰ってきた。
「アリサ」
血の臭い、生肉の臭いに正気と食欲を混ぜ狂わせながら、緑の虚ろな目が闇に輝く。
「おまえは魔物だった」
わたしはアレキサンダーの檻を開けた。
「魔物は人を食う。だがこれからおまえは人になる」
「アリサ?」
「人は人を食わない。わかるか。わたしを食え。食ってその味を忌み嫌え。忘れるな」
彼の名の刻まれたナイフを片手に握らせて、わたしはその場に崩れ落ちる。
腹が減っているだろう? わたしは最後に囁いた。
薄れていく意識のなかで聞いた呻き声では、返事はわからなかった。だが、わたしは信じている。彼が魔女たるわたしの罪を裁いてくれることを。