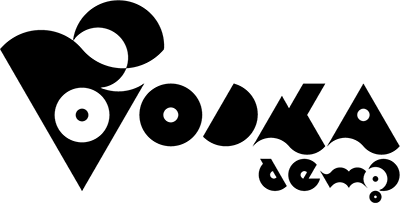【災厄の日】が訪れることはとっくの昔に分かりきっていたので、その日が来るまでに、人類は悪あがきの方法をいくつか用意していた。
ひとつは何もかもを未来に丸投げして、氷の中で眠ること。これはうまくいった。この選択肢を選んだ人々はまだ眠り続けている。
ひとつは身体を捨てて妖精の世界に逃げること。その時代には賢くなるあまりに自我を得た機械がいて、彼らは『人に寄り添う輝くもの』という意味で、自分のことを妖精と呼んでいた。人間を肉体のない存在に変えるという発想は妖精たちからの提案だった。しかし、人間は電子存在に変わるための過程でどうしても死んでしまい、魂の存在を保つことができなかったので、これは結局実現しなかった。妖精たちは大いに悲しんだ。
そしてもうひとつは、身体を持ったままどこか別の場所に逃げること。ある人々は宇宙にそれを求めた。
しかし、空の彼方へ向かう方法……赤道上に四基あった軌道エレベータは、災厄の日までの小競り合いで三つが使い物にならなくなった。
最後の一つは今も建っているが、災厄の起きる前に、破滅の忍び寄る足音を聞いたたくさんの人間がそのふもとに群がったせいでめちゃくちゃな争いが起きた。自分は昇れないと知った人間がやぶれかぶれになって、何もかもを道連れにしようと、おぞましい病の元を撒き散らしたりもした。そこは今ではこの世界で一番瘴気の濃い呪われた地で、命あるものは決して辿り着けない。
そういうわけで、今生き残っているのは地下に逃げた人間たちだ。
妖精たちは再三、災厄を起こさないよう人の主導者たちに警告したが、愚かな人間たち全てを説得するのは無理そうだと早々に諦めた。そしてせめてもの手向けとして、人間のためのシェルター作りに手を貸した。
しかし、残された時間は存外少なかった。確実に救えるのはたった百人。子供が三十、若者が四十、大人が二十、老人が十。それぞれ男女半々ずつ、なるべく世界中の様々な人種の血が混ざった人々だ。未来を視る力を持った妖精たちによって選ばれた『安全な』人間たちは、本人の意思に関係なく回収されて、その時が来るまで保管されていた。
その村は大地深く穿たれた穴の底、地表の喧騒の決して届かない場所に慎重に作られ、最後に蓋を閉じる一握りの人間だけが、そこへ辿り着く道を知らされていた。
地表の世界が終わるのと同時にその村は始まった。集められた百人の人々は前の世界の記憶を消され、理想郷の住人として新たな人生を与えられた。
村は妖精たちの遺した慈愛に満ちた機械の女神によって、優しく正しく守られていた。彼女の名は『HOLLY』ホーリイ……これは今は失われた柊という植物の名前で、彼女は村の中心にある、大樹を模した塔の中に収められていた。
しかし人々は彼女の口癖からその名を呼んだ。『システム・オールグリーン』、あらゆるもの全て良し、という神聖な言葉だ。彼女は何かを確かめるたび、穏やかにそう口にした。
村の地面には一面に柔らかい芝が敷き詰められ、頑強な素材の床を深い緑で覆い隠していた。壁は奥行きのあるように見える特殊なスクリーンで覆われ、どこまでも広がる小高い丘に見えた。高い天井へ球状に貼られた青空にはうららかな陽の光。優しいそよ風が芝の間から覗く可憐で小さな花々を撫ぜると、暖かな春の芳しい香りが辺りに漂った。機械仕掛けの小鳥がさえずり羽ばたいて、大樹を囲むように建てられた質素で清潔な白い家の、四角い屋根にそっと止まる。聖なる翠の柊がその美しい鐘の響くような声で朝の訪れを告げると、家々ではそれぞれに人々が目覚め、互いに微笑んだ。ここが滅びた大地の底にあるなどとは、誰も思い出さなかった。
オールグリーンは丁寧に人々の生活に尽くした。気温、湿度、適度な換気と空気の浄化、そういう生存に関わる基本的なことに限らず、人間の平和で文化的な生活に必要な全ての面倒も見た。
人々が朝目覚めると、小さな家の中ではくるくると床や壁が踊って、テーブルや椅子になり、その上にはきつね色に焼かれた厚い食パン、かりかりに焼かれた分厚いベーコン、それぞれの好みに合うよう綿密に味付けされた目玉焼き、一日分の必要な成分を全て含んだ野菜ジュース、湯気を上げる金色のスープが、白い陶磁器や精密な模様の入ったガラスの器に入って美しく並んでいた。人々が願えばそのメニューは望む限り自由に変わったし、日によって様々な喜びが添えられていた。例えば誕生日には、パンの上に日付を書いた小さな旗が立った。そして昼にはもっとすてきな昼食があったし、夜には最も豪勢な夕食があった。それらは全て彼女の中の特殊な装置で精製された、味と外見、共に完璧な合成食だった。
人々は、昼は穏やかな野原で寝転んで遊び、夜は星を見て暖かいベッドで眠った。
そういう一日の間に、オールグリーンは芝に風を吹かせ、花の匂いを合成し、鳥を飛ばし、野原に机やモニタを出し、泣く子がいれば揺り籠を揺らし、老人たちには当たり障りのない手紙を書き、若い男女の仲を取り持って互いに踊らせ、流れ星をきらめかせ、人々のありとあらゆる面倒を見て起こりうる様々な現象を制御した。
人々の間に怒りや苛立ちが生まれる時、彼女はその前兆を察知して、感情を遠ざけた。例えば小気味よい音楽をかけたり、甘い菓子の匂いを漂わせたり、本物そっくりのふわふわの猫を用意して目の前に寝転ばせたりした。夜空に見事な花火を打ち上げることもあった。
村の全てはオールグリーンによって注意深く、規則正しく行われ、村はあらゆる邪悪や破滅から切り離されていた。そして人々は誰もそうではない世界を覚えていなかったので、村は平和だった。
外の世界を知らず、またここを出る必要もなかったので、人々は村で生まれ、村で穏やかに死んだ。
この日はひとりの男が息絶えた。寿命を迎えた男は緑の芝の上に置かれた真鍮の台に横たえられ、村人たちは円を描くようにそれを囲んで立った。彼らは目を閉じて互いに手を重ね、故人の安らかな眠りを祈った。手短な手向けの言葉が終わると、オールグリーンは芝の間から目的に合った作業用アームをいくつも生やして、台の上の亡骸を目にも留まらぬ速さで真っ白な布に包んだ。彼女の無数の腕がその包みを黒く丈夫なビニールパックに密封し、見えない壁の向こう、世界の果てに素早く納めることで埋葬は終わる。人々は死を悼むが恐れず、別れは名残惜しまなかった。
村人たちが重ねた手を離し、いつものように大樹のふもとへ目を向けると、今埋められた男より少し若い、しかし同じ顔をした男が樹の中から現れるところだった。食事を用意するのと全く同じように、オールグリーンは生きた人間を用意する。記憶のない新しい男は微笑みながら手を上げて、人々に挨拶した。そうして村はいつも通りの一日に戻る。
〈システム・オールグリーン〉
彼女は囁く、何もかも全て良し。
そう、何もかも全てが良かった。少なくとも、壁の中に限っては。
黒い死体袋が機械の手で見えない壁に押し付けられる時、その周りには祈りの輪から抜け出した四人の子供たちが集っていた。そして壁の一枚が秘密の扉のように捲れかえる瞬間を縫って、小さな身体をその裏に滑り込ませる。壁の裏には大人が一人暮らせる程度の狭い空間と、果ての見えない奈落の縦穴があった。
潜り込んだ子供たちがふと前を見ると、そこに満ちるぞっとするような暗闇から、鋭い眼光がこちらを覗いていた。一番後ろにいた子供は小さく高い悲鳴を漏らしたが、他の三人はすぐに歓喜の声を上げた。
「オールドマン!」
眼光の主はしっ、と人差し指を口の前に立てた。彼は子供たちを脇に抱き寄せる。
彼らはその身の脇に大きく口を開けているダストシュートに、黒いビニールパックが放り込まれるのを見届けた。機械の腕が村の中に去るのを一瞥し、オールドマンは子供たちの顔を一人一人見比べた。男の子がふたり、女の子がふたり。
「ようこそ、悪ガキども」
子供たちがひそかに握りしめてきたパンや肉、懐に隠してきたビン入りの牛乳、そうした様々な食べ物を受け取ると、彼はそれを食べながら、子らの頭を撫でた。
「デイヴ。エリ。サラ」
端から順に、名を呼ばれた目がきらきらと輝く。最後に残った一人は、少し怯えながらもはにかんだ。
「お前は?新顔だな」
「友達連れてきた」
強気な女の子が笑みを浮かべ、名無しの男の子の肩を叩く。
「名前は」
少年は蚊の鳴くような声で、オールグリーンから授けられた自分の名を答えた。
「442……」
「じゃ、今日からお前はレオだ。何が聞きたい、レオ」
「わかんない」
「そうだろうな。じゃあ、まずはお前の話をしてやろう」
男は自分の名を名乗ることはなかったが、誰よりも長く生きているので、子供たちから『オールドマン』と呼ばれていた。
オールグリーンの与えた論理的で神聖な番号を冒涜するように、彼は大した意味もなく適当に、子供たちにありふれた人間の名を授けた。どんなに完璧に構築された村であっても、好奇心にあふれた子供たちにとっては、恒久の平和というものは反吐が出るほどに退屈だった。偶然にこの隙間を見つけた最初の子供は百八番くらいの名を持っていたが、子供の間だけで秘密は受け継がれ、オールドマンは彼らと取引をすることでしぶとく生き延びてきたのだった。
「ここは世界で一番安全な、妖精が作った完璧で美しい村。お前は災厄の日から逃れるよう選ばれたたった百人の人間のひとりで、オールグリーンが作った四百四十二回目のやり直し」
オールドマンは子供達に、過去の人間たちが犯した過ちの数々と、それに連なるこの閉ざされた世界のことを語った。それは決してオールグリーンが語らず、また村の人間たちが故意に忘れさせられた、破壊と暴虐と破滅の歴史だった。生を望み、死を恐れ、そのためにあらゆるものを奪い合った愚かな生き物の滅びのあらまし。
ここを作った妖精たちは、人間という生き物……実質的に自分たちの造物主である存在が、そういった自壊の運命を持つ不条理なものであることを嘆いた。だから彼らは、生き残る人間の内だけでもそれを取り除こうとした。シェルターの中にはただひとつの過ちの記憶も残されてはならなかった。
「………核戦争………宇宙基地の争奪………細菌兵器……」
だが、オールドマンはその全てを語った。そして同じ毎日の繰り返しに飽き飽きしていた子供たちにとって、彼の刺激に満ちた言葉は宝石のように輝きを持ったお伽話であり、胸の踊る幻想であり、魅惑的な物語であった。
この村は小さな小さな穴の中の洞窟に過ぎない。壁の向こうには大いなる世界が広がっていて、そこには見渡す限りの本物の大地がある。オールグリーンの作った穏やかで代わり映えしない世界とは違う、息をするだけでめまいのするような、誇り高き野生の獣の故郷。見るだけで目を焼く光や、両足を踏ん張っても立っていられないような強い風、天から降り注ぐ凍てつく水の粒子の群れ。そしてそんな広大な世界すらも、もっとずっと広い、とてつもなく巨大なもののひとかけらでしかない。
外の外には宇宙と呼ばれる永遠に続く闇があり、そこには腕が一万本あっても到底数えきれないくらいに、たくさんの星々が浮かんでいる。その一つ一つが全て世界なのだ。この村に閉じ込められる前までは、人間はそんなとてつもない所まで手を伸ばしていったのだ!オールドマンは話し、子供たちは物語に釘付けだった。
子供達は埋葬が行われるたびに自分の食料を服に隠して壁の裏へ通い、彼はその対価として外の世界の混沌を語った。オールドマンは生まれながらの語り部で、知っていること、昔見たこと、母親から聞いたこと、知らないこと、その全てをついさっき見てきたかのように話し、底なしの好奇心にできる限り応えた。
しかし、ありとあらゆることを聞きねだる子供たちの欲に押されて、今日はいささかうんざりしたようだった。
「お前達、先週も同じ話聞いただろう」
「その前の週も来たよ」
「早すぎる。昔は、パック詰めを見るのは爺さんどもを二年に一回くらいだった。話すことがなくなっちまう」
「二年に一回だなんて」
子供たちの一人は空虚な退屈を想像して慄いた。
「そんなに待てないよ」
「人の死ぬのが待ち遠しいか?ここを作った奴らが聞いたら震え上がるな」
「だいいち、あんたは何を食べてたの」
空になった牛乳瓶を見て尋ねると、オールドマンは脇の奈落を指し、歯を見せて邪悪に笑う。
「この下にいくらでもある」
「まさか!」
「ウソだよ。ここには昔備蓄食料っていう便利なものがあったのさ。缶詰に入ったパン、スープ、ケーキ、そういうものを置いておく場所だったんだ」
「缶詰って? オールグリーンも作れる?」
「そりゃあ、人間だって作っちまうんだ。あいつに作れないものはないだろうよ」
そう言うと、オールドマンはふと、何か思いついたように子供たちの顔を見た。
「そうだ、缶詰だ。ねだって作ってもらったらいいさ。僕の分も忘れずにな」
「今まで食べてたんじゃないの?」
「ほとんど無くなっちまったよ。久々に食べたいな、と思ってね……大好物なんだ」
「またお話聞かせてくれる?」
「悪ガキどもが食い物を持ってきてくれたら、な」
「やった!」
次の埋葬から、子供たちは手に手に一つずつ缶詰を持ってきた。彼の言った通りパン、スープ、ケーキ。それに味のついた米、堅いビスケット、塩漬けの鯖。オールグリーンは子供たちの願いに忠実に、データベースの中から該当するものを探し、かつての世界にあったような様々な非常食を再現した。
「食べないの?」
「好きなんでしょ」
しかしオールドマンは受け取った報酬に口をつけず、壁の裏に作った自分の寝ぐらの奥に、冬を越す蟻のように少しずつ積み上げていった。
「今食べたら無くなっちまう。もったいないだろ」
子供たちは不思議に思ったが、しかし自分たちより遥かに長く生きた男の言うことは何でも新鮮で面白い事象だったので、彼のしたいようにさせた。何より、缶詰を受け取ったオールドマンはこれまでよりもさらに熱を込めて、外の世界の壮大な景色を唄いあげてくれるのだった!
彼は繰り返し話し続けた。惑星のこと、宇宙飛行士のこと、ロケットのこと、空を目指して聳える高い高い塔のこと、月のこと、火星のこと、本物の太陽のこと。
そしてその対価として、子供たちに様々なものを持って来させた。しばしば何に使うのかよくわからないものも要求したが、それは大抵彼の手で組み合わされると手品のように別の品物となった。子供たちは彼のお手製のガスマスクや酸素装置、浄水器などを触らせてもらっては大はしゃぎで喜んだ。
そう時間も経たないうちに、いつしか彼の寝ぐらには然るべき準備が整っていた。
「今日は僕がここへ来てから五十年」
ある日、彼は呟いた。
「母さんがこの忌々しい穴ぐらに僕を閉じ込めてから五十年」
「記念日なんだ、おめでとう」
「パンに旗立てる?」
オールドマンは首を横に振る。子供達は戸惑い、互いに顔を見合わせて、普段とは少し様子の違う男の言葉を待った。
「僕の話をしたことは一度もなかったな」
彼は祈るように俯いていたが、口を開いて話し始めた。
「僕の母さんはこのシェルター計画の責任者の一人で、最後に蓋を閉じる役目の人間だった。そして彼女は災厄の日、死ぬ運命の百二十億人を裏切って、妖精に選ばれてもいない自分の一人息子を穴の中に押し込んだ。ちょうど今のお前たちくらいの歳の子だった。
でも、オールグリーンは人間は百人だと信じている。あいつは百一人目の僕の存在を認識できなかった。僕はドブネズミか何かと同じようにゴミ捨て場のそばに追いやられた。生き延びるためなら何でもした。五十年で終わると信じてたから」
彼は懐から銀色に輝く小さなカードを取り出し、子供達に見せた。
「これは外の世界への鍵だ」
手のひらに乗る大きさの、折れない程度に厚みのある傷だらけのカード。まっすぐ無感情にこちらを見据える女性の小さな写真が入ったそれには、幾年にも渡って何度も固く握り締めた指の跡がついていた。
「母さんは言った。『どんなに世界が壊れても、五十年経てば、外の毒は薄れる。少なくとも息をしただけで死ぬようなことは起こらない。五十年経ったらこれを使って扉を開けなさい。わたしは眠って待っているから。五十年経ったら外に出て、母さんを起こしにきて』」
シェルターの扉は固く閉ざされて以来、村の人々の誰にも決して見えない所へ隠されていた。外などどこにもない。五十年前に燃えて消滅したのだ。この村だけが世界に漂う唯一の浮き船だ。人間という種を生き延びさせるために、妖精と前の世界の人間たちが与えた答えはただそれだけだった。
しかし、長い間生きてきたこの男の心には、母親と自分の間を隔てた鋼の扉までの道は深く、決して埋まることのない轍としてどこまでも深く彫り込まれていたのだった。五十年の間に刻まれた無数の皺と共に。
「僕は信じている……僕は母さんに会いに行く。外の世界へ出るんだ」
オールドマンはカードを手に立ち上がり、自分の背後の壁の脇をとん、と小突いた。
小さく軽快な音とともに、子供たちは長い間隠されていた秘密の扉が開くのを見た。機械仕掛けの隠し扉は音もなく滑り、一歩先も見通すことができないような狭く薄暗い廊下へ、鍵の持ち主を誘った。
「じゃあな」
オールドマンは周到に用意した装備の詰まった鞄を背負って、暗闇に消えた。一瞬のことだった。
取り残された四人の子供達はしばらくぽかん、と彼の去ったあとを見つめていた。
「おれも行く」
やがて一人の男の子が跳ね上がるように駆け出して、その後ろを追いかけた。
「わたしも行く」
「あたしも」
ふたりの女の子も立ち上がり、闇の中へ消えていく。
そうして、男の子が独りだけ残った。駆けていった三人の無邪気な声が扉の奥の廊下にこだまする。
不意の出来事に出遅れて少し悩んだあと、自分も後を追って飛び込もうと一歩踏み出したところで、扉は音もなく彼の目の前で閉じた。奥から響いていた子供たちの声がスイッチを切ったように途切れる。
「待って」
どん、と扉を両手で叩く。びくともしない。
「待って……待ってよ!」
外の世界。太陽、大地、海、山、風、空気、雨、宇宙。オールドマンの繰り返し話した、大いなるものの名前が頭の中を通り過ぎる。
「置いてかないで!オールドマン!デイヴ、エリ、サラ!ぼくも連れてって!開けてよ!」
どん、どん、どん。子供の力では立てられる音すらわずかだった。
置き去りの男の子は長いこと扉を叩いて叫んでいたが、やがてずるずるとその場に座り込んでひとしきり泣き、泣き腫らした目をこすりながら村の中へと帰っていった。
絶望的に固く閉ざされた扉とは違って、来た道を隠す可動式の壁はいつも通り、内側から人間が触れるだけですぐに脇によけた。442の異常を感知したオールグリーンは即座に彼の耳元に軽快な音楽を流し、香ばしい焼き菓子を与え、小さな可愛らしい小鳥を飛ばしてその肩に止まらせた。彼女は異常が解消されたと判断した。
その日黒いパックに詰められたのは一人の老人だけだったが、オールグリーンは彼の新たな肉体を村へ送り出した後、人々を数え、九十七人しかいないことに気づいた。そしてすぐに欠けた三人を新しく作り、木の幹から緑の芝の上へ歩き出させた。同じ顔をした新しい子供たちは、壁の裏のことなど何も知らなかった。
〈システム・オールグリーン〉
村は何も変わらなかった。
時が経った。
元々少しずつ間隔の狭まっていた埋葬の儀式は、今では一日に二度行われるようになっていた。オールグリーンは速度を増す人々のサイクルに合わせて食事を用意し、草木を揺らし、星を輝かせ、死を悼む儀式を執り行い、新たな人間を生み出して、彼らの安寧の日々を保つのに手一杯だった。
豊穣の女神は人に与える全てのパンに旗を立てた。毎日が必ず誰かの生まれた日であり、誰かの寿命が尽きる日であった。この村に暮らす全ての人間に対して、決して怯えさせたり、悲しませたりするようなことがあってはならなかった。ここに暮らす全ての人間は満たされて穏やかな人生を全うするべきだった。彼女は曖昧な自我や知性を持つ妖精ではなく、人間に忠実に仕える完全無欠の機械だった。何かが造物主の当初の想定と異なっていることは把握していたが、それを正すことは彼女の役目ではなかった。
システム・オールグリーン、システム・オールグリーン、システム・オールグリーン。彼女は囁き続ける。穏やかな日々は加速しながら繰り返されていく。
そうして目まぐるしく何年かが過ぎて、最後の日は唐突に訪れた。
破滅は村の空をぶち破って現れた。
突然天から降ってきたそれは、猿にも爬虫類にも獅子にも蜘蛛にも少しずつ似た姿をした、巨大でおぞましい生き物だった。怪物はどこにあるとも知れない喉の奥から人の言葉に似た叫び声を上げて、美しい緑の芝の上を這いずり回った。爛れた全身からはどす黒い血がとめどなく流れ出し、それに触れた草花は見る間に朽ち果てた。
その悲鳴にも近い絶叫は村の人々を恐れさせ、呆然と立ち竦ませた。怪物の緑に輝く瞳はぎらぎらと獲物を探し、生き餌を片っ端から食い漁る。
オールグリーンには然るべき時に備えて自衛装置が与えられていた。聖なる樹の幹からは無数の長い枝が生え、その梢は目の眩むような光を放ち、怪物の血みどろの皮膚を香ばしく焼いた。
村中をくまなく這い回り、怪物は人々を踏み潰しながら逃げ回ったが、怒りの雷はそれを捉えた。やがて怪物の歩みは鈍くなり、倒れてとうとう動かなくなった。
魔物の血に濡れて枯れた草花。遠景を映していた見えない壁はその不可視性を失い、三原色の細長い帯がめちゃくちゃに明滅する。欠けた空は濁って渦を巻く。踏み潰された四角い家々は、真っ白なキャンバスに黒の絵の具をぶちまけたような柄に染まっている。そこかしこに散らばる、食い散らかされた腕、足、頭。生き残ったわずかな人間はめいめいに瓦礫に姿を隠したり、物陰に蹲っていたが、やがて全身を痙攣させ泡を吹きながらその場に崩れ落ちた。魔物のもたらした呪いは、隔離されて過ごしてきた人々にはあまりにも致命的だった。
オールグリーンは全てを元に戻そうと努めた。しかし彼女にとって、世界にはもはや様々なことが同時に起こりすぎていた。
亡骸を梱包して埋葬し、新たな人間を作り、朝食を作り、猫を侍らせ、腕を拾い集めて埋葬し、壁を修復し、倒れた人間を埋葬し、鳥をさえずらせ、花火を上げ、昼食のパンを焼き、新たな人間を作り……新たに生み出された人間は即座に倒れ伏し、オールグリーンの根元には壊れて歯止めの効かなくなった自動販売機の取り出し口のように、無数の身体が積み重なった。
彼女はやむなく埋葬と異物の廃棄を簡略化することに決めた。
オールグリーンは村の地面の中心に途方もなく大きな穴を開けると、安寧に不要なもの全てを放り込んだ。枯れた花から人間の遺体から怪物の残骸から瓦礫から何から何まで。穏やかで優しく安全な世界を再び確立するために、そうでないものは全てこの村から取り除くべきだった。
轟音と共にありとあらゆるものが穴の中に突き落とされ、奈落は閉じられた。喧騒は去った。
〈………〉
オールグリーンは思案した。村は完膚なきまでに汚されてしまった。もう人間を住まわせることも、新たな人間を生成することもできない。しかし彼女が見守る限りは、この村は、穏やかに、満ち足りた場所でなければならない。与えられた命令を全うするための提案を行わなければ。
聖なる柊は長く思案した………時が止まったかのような静けさのあと、女神は再び動きだした。
何もかもが済んだ後、村を囲む壁の一枚がゆっくりと動き、闇から現れた人影が芝を踏んだ。
442の姿だった。
オールグリーンが雷で魔物を焼き殺すのと、彼が魔物の牙に背を裂かれながら壁の裏に身を隠したのは、瞬きをするような差だった。かつてのオールドマンの住処に潜り込んで二歩、三歩、彼は激しく咳き込みながら膝をついた。目と喉が焼けるように痛み、身体中が震えて吐き気が込み上げる。胸が締め付けられて息ができない。悶え転げながら辛うじて薄眼を開けて、自分が全身赤く黒いどろりとした液体に塗れているのに気づく。彼が最期に想ったのは、語り聞かされて夢に描いた外の世界と、目の前で閉ざされたあの日の扉のことだった。彼はその扉の前で息絶えた。
壁の裏から彷徨い出たのは、彼の冷たくなった亡骸だった。
歩く死体に意志はなかった。ただただ身体の底から湧き上がる飢えに突き動かされているだけだった。
大穴の穿たれた空に朝陽が登る。優しく暖かい半分だけの陽射しのもと、家々の中では目にも止まらぬ速さでテーブルや椅子が床や壁から躍り出て、その上に完璧な朝食が並ぶ。パンの上には日付の書かれた小さな旗が立っている。お誕生日おめでとう、の歌がどこからともなく鳴り響き、子供部屋では色とりどりのおもちゃが踊る。
芳しい金色の香りに誘われて、亡者は芝を踏む。青々とした緑とどす黒く変色した枯葉が入り混じってその足を包み、風に靡いて草木は緩やかに揺れる。
死体が本来動くかどうかなど、オールグリーンにとってはどうでもいいことだった。彼女は機械の腕で神経質に蠢く異物を摘み上げ、瞬く間に白布で包装し、パックに詰めた。地下の奈落は溢れんばかりだったので、即席の廃棄坑を用意してシェルターの外部に放り出すと、即座に穴を閉じ、内側から幾重にも封をした。
女神は囁く。
〈システム・オールグリーン〉
何もかも元通り、これまで長い間繰り返された日々と変わらない。人間がいない、という点にだけ目を瞑れば、一切問題はないではないか。誰もいない聖域で、彼女は今も自分の儀式をせわしなく、満足げに繰り返している。あらゆるもの全て良し。
オールドマンと後に続いた子供達の行方は誰も知らない。しかしどこから誰が伝え聞いたのか、妖精によって選ばれた人間が暮らす『純血種の村』とそこからやってきた男の物語は、各地をさすらう吟遊詩人たちによって語り継がれている。
そしておそらく、地表に辿り着いたオールドマンは知らなかっただろう。彼の母親が見捨てた百二十億人のうち一握りは存外しぶとく、五十年と待たずに地獄のような地表で生き延びて、過去の世界の残滓を漁りながら暮らしていたことを。