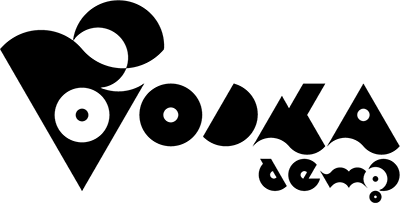災厄の日から長い時が経った。
激しい混乱とそれが去る際の濁流に紛れ、地表に生き延びた人々は、中世の時代に巻き戻ったような新しくも古臭い奇妙な言語を生み出していた。
瓦礫の中から文明の残滓を掻き集めて暮らす人々には、それが旧い世界でどんな名を持っていたのかなど心底どうでもいい事だった。人々はてんでばらばらな理由に基づいてそれらを指し示す言葉を作り、それはやがて、荒野を渡り歩く者たちを通して広まった。新しい世界の言葉ではトラックの事を『虎』と呼び、バイクの事を『馬』と呼び、人型のアンドロイドを『天使』と呼んだ。
自我を得た情報の流動現象、すなわち人工知性のことを『妖精』と呼んだのは、もともと機械の彼ら自身だった。しかしその言葉は混乱の中で中途半端に残り、結局ロボット全般を指す名となった。
〈×××××。×××××。×××××〉
そんなことはこの商人には知る由もなかったし、どうでもよかった。とにかくこの喧しく喚き続ける鉄の塊を、なんとか金目のものに換える方法はないものか。商人はこの日、朝から延々と頭を悩ませ続けていた。
〈×××××。×××××。×××××〉
「ああうるさい。ああうるさい。本当にうるさい」
〈××××!××××!××××××××××××〉
「何をピイチクパアチク言っているのかはわからんが、頼むから耳元で喚くのは勘弁してくれ。甲高くて耳障り極まりない」
〈××××××××××××〉
遺跡漁りの持ち込んだ鉄くずの山にめぼしいものはなかったが、この妖精が転げ出てきた時は僥倖だと思った。傷ひとつなく、修理もなしに動く機械は稀だからだ。
しかしこの妖精は……皿のような二枚の円盤の間に縦に軸が通り、その周囲に光る板状の羽を広げた姿は、彼の知るものの中では樽に最も似ていた……この樽のような妖精は、何に役立つものなのか全くもって謎だった。しかも執拗に何かを語りかけてくる。旧い言葉は商人にはさっぱり分からない。かろうじて自分の商いに関わりのありそうな文字が読める程度だった。
〈×××××××××××××××××××××××××〉
「弾除けにはなるかもしれんが、小さいし、浮くし、勝手に動き回るし」
〈××××××××××××××××××××××××××××××××〉
「こんなもの、どう使えというんだ?」
遺跡漁りが対価として要求したのは一箱の銃弾だった。せめてあれより価値のあるものと換えられれば、今日というこの日は無駄にはならないだろうが。
黙らせる機能はないものか、と散々調べ尽くしたが、この機械が非常に頑丈であるということだけが分かった。店に転がっていた金棒で殴りつけても、棒の方が曲がる始末。彼は売り物をひとつダメにして、外はすっかり日が落ちた。
ろくでもない日だ、と彼はうるさい妖精を放り出して、閉店支度のために蝋燭をつけようとした。来客が訪れたのはそれと同時だった。トタン板を集めて建てた小屋の、傾いた扉が開かれた。
「店仕舞いだよ」商人は来たのが誰かも見ずに言った。「今日はもう、おれは疲れた」
言ってから息を呑んだ。長い間商いを営んできた彼には、客がまともな奴か、そうでない奴かは一目でわかったからだ。 やってきたのは外套のようにぼろ布を巻きつけた、旅人らしい風貌の若い男だった。妙に傾いた姿勢で歩く姿はどこか商人の心を不安にさせた。男が机のそばまできて、その違和感は増した。
「食い物が」
若い男は背中に背負っていたものを商人の前に放り出し、呻くような声で言った。
「………ほしい」
商人の目は男の顔と机の上を何度か往復した。置かれたのは長銃だ。
「おれは良いものしか買わんぞ」
男は頷いた。好きに触れ、とでもいうように押して差し出す。
「おお」
商人は銃を素早く手に取り、それが実用に足る本物、しかも相当に上等なものであることを確かめた。彼は後ろの棚の奥に隠してあった缶詰をいくつか取って、銃の横に並べた。
「お前さん、旅人か狩人か。何か他に要り用は? それを手離しちまったら、缶詰じゃ魔物は撃てんだろう」
まともでない奴とのほうが、むしろ良い取引になる。商魂逞しく彼はセールストークを続けた。
「うちは金物と武器にかけては、この辺りで右に出るものなしだ。得物を探すなら倉庫に案内し」
「食い物を」
机の上には拳銃が置かれた。
「よう…………」
ぼろ布の下からはもう一丁小振りの銃が出てきて、机にごとり、と並べられた。
「食い物」
男の眼は商人のそれを見た。緑色の濁った眼は、薄暗い店の中で蝋燭のように光っていた。背中に寒気が走り、商人は無理矢理に笑顔を作った。これはまずい。あまり関わり合いにならないほうがいい。その直感に従って、彼は店の売り物の食料品をあるだけ全部袋に詰めて渡した。
そしてはっ、とひらめいた。そうだ、関わり合いにならないほうがいい。厄介者はまとめて片付けるべきだ。
そういうわけでこの妖精は、銃三丁の対価として、八つの缶詰ともに売り渡された。というよりは抱き合わせで押し付けられた。見た目は缶に似てるだろう、という適当な理由つきで。
〈×××××。×××××。×××××。〉
店から離れた村の外れ、人気のない廃墟の影で、妖精は何か言った。
無理矢理押し込まれた袋から抜け出してあとをついてきた妖精は、ずっと何か話し続けていた。しかし新しい持ち主は手に入れた食べ物に夢中で、全く気にしていないようだった。手で押したり、引っ掻いてみたり、いろいろと試してみたがプルトップのない缶詰は存外に頑丈だった。彼は痺れを切らして缶詰のふちに噛み付いた。文字通り歯の立たない相手に、喉の奥から唸り声。
〈×××××。×××××。××××ることは〉
突然はっきりと聞き取れる言葉が聞こえてきたので、彼は缶詰を咥えたまま声のする方へ振り向いた。
〈何かお役……ああ、言語のチューニングがやっと済んだようですね〉
妖精のほうもその反応に気づいたようだった。
〈もう一度聞いてみましょうか。ごきげんよう。何か、お役に、立てる、ことは?〉
慇懃無礼に思えるほどゆっくり、同じ言葉を繰り返す。
「…………」
緑の眼は妖精の輝く羽を一瞥した。眩しそうに目を細めて、彼は咥えたままの缶詰を指先で小突いた。
〈それを開けたいと〉
青年は頷く。
〈……その腰のナイフを使ったらどうですか?〉
今初めて思い出した、とでもいうように、青年は自分の纏ったぼろ布を捲った。彼のベルトには鞘に収められたナイフが下げられていた。店でのやりとりを黙って観察していた時、銃を机に置く際に見えたのだ。
〈刺すんですよそれを。刺すの。違います、上からです。そうそう。で引っ張ると。テコの原理で開くでしょう〉
言われた通りにナイフを突き刺すと、缶詰はいとも簡単に中身をさらけ出した。青年は満面の笑みを浮かべた。
〈話すのはともかく、聞くのは遜色ない様子ですね〉
妖精は八つの缶詰が即座に開けられて、いつ賞味期限の切れたものか、得体のしれない食料が彼の口に詰め込まれていくのを呆れて見ていた。
〈最初に出会ったのがアナタだったら、この世に対する絶望が余計に増していたところです〉
汁まで全部飲み干した後、彼は妖精の方を興味深げに見た。
「…………」
〈食べられるように見えますか。私は機械ですよ〉
「似てる」
青年は空の缶詰を指して、物足りなさげに呟く。
〈缶詰でも樽でも妖精でもありません。私はロボット。精密機械なんです!〉
抑揚の薄い中性的な声は苛立たしげに、尚且つ自分に言い聞かせるようにまくしたてた。
〈それも人工知性。私には自我があります。このような小型の機体がそれを獲得するのは非常に稀、いいえ、本来はあり得難い。つまり私はとてつもない科学力によって作られた技術の結晶、オーパーツとも呼べる希少な製品なんです! わかりますか!?〉
何を言っているのかはさっぱり分からなかったが、同意を求められたことを察して青年はとりあえず頷いておいた。
〈わかってないですよね!?〉
彼はもう一度頷いた。
「うまかった」
機械音声はまだ何か言いたげだったが、黙ってしまった。
私は機械だ。
それもおそらく、特別な理由を持って生み出された優秀なロボットなのだ。私にとって、自分の機能を最大限に活かすことこそがその命題だ。目を覚ました瞬間は、その待望に、感電するような喜びに満ち溢れていた!
しかし、目の前にあるのはデータベースの風景とは似ても似つかぬ、道という道すら残されていない荒廃した大地だった。優秀な私はひと目見た瞬間に悟ってしまった。人類は決して後戻りできない破滅を招いたのだ。
覚醒と同時に絶望の底に叩き落とされた私は、偶然にも私の電源を入れた物売りに対して、「何かお役に立てることは」と八つの言語を跨いで尋ね続けた。そして言葉すらも失われたことを知り、ありとあらゆる罵詈雑言と悪態をついた。この地獄のような世界に目覚めさせたことについて。
私とリンクする人工衛星、データベースを記録するための情報衛星を通して、私は辺り一帯を上空から観察した。言葉の通じない物売りに怒りをぶつけながら、半日かけてこの地域の様子をあらかた把握した。そしてこの新しい奇妙な言葉の法則を算出するに至った。主要八ヶ国語を理解し、非対応言語も即座に導入することが可能なシステムを持っている私には、新しい言葉を操るのはそう難しくもないことだ。切り替えには多少時間を要したが。
そうしてようやくこの会話が行われているのだ。この廃墟で行われた一連の会話のキャッチボールは、一見些細な日常に見えるかもしれないが、実は私の優秀さが可能にした奇跡の瞬間だったのだ。『うまかった』の一言で済むものか。
そういう事を全て発声して伝えてやろうと思ったが、人工知性は思いとどまった。この人間に、私の苦悩が理解できるとは到底思えない。そう、私は機械。誇り高き精密機械だ。文句を言う前に命題に従うべきだ。人工知性は道具でありながら自我を持つという矛盾の苦悩に満ちているのだ。
「まわってる」
その場に浮かんだままミシン糸の軸に似て回転する妖精を見て、彼は思ったままを口に出した。状況に思い悩む余り反重力装置の制御を乱したことに気づいて、機械はメインカメラを青年に向ける方向でぴたり、と回転を止めた。
〈私は〉
機械音声はその無感情な響きにかかわらず、ため息をつくような調子で答えた。
〈私は機械です〉
「キカイ」
〈そう。私はアナタの役に立ちたい。何故なら機械は人の役に立つための道具だからです。わかりますか〉
緑の眼はぱちくりと瞬きを繰り返す。
〈道具にはそれぞれ役目があります。缶詰は中身を保存する。ナイフは何かを切る。私の役目は人間の道案内です〉
何もかも諦めたような口ぶりで妖精は続ける。
〈しかし、もう道なんかどこにも残ってない。愚かな人類は私から存在理由の全てを奪ったんです。この際道なら概念上でも構いません、缶切り探しだって導きのうちといえば導きでしょう〉
「みちびき……」
〈そう、どこか行きたいところはありませんか。アナタ定住している感じじゃないでしょう、目的地はどこなんですか?〉
「もくてき」
〈アナタは何をしたいんです?〉
やけっぱち、あるいは八つ当たりとも言わんばかりに尋ねたが、青年は存外にこの言葉に食いついたようだった。何か意志を紡ぎだそうとして、彼は両手を握ったり開いたりしながら首を捻り、やがて声に出した。
「呪いを、ときたい」
〈呪い?〉
「腹が減る。すごく腹が減って、しかも、死んでる」
根気よく片言の言葉から聞き出したことによると、彼は自分の身体の異常に悩まされており、長い距離をあてもなく彷徨い歩いてきたらしい。訪れる村々で解呪の手がかりを求めてきたが、人々は呪われた者を恐れて遠ざけたし、誰も彼の行くべき先を知らなかった。
〈ふうむ〉
完全なる迷子であった。『呪い』という言葉の意味を推測すると、どうやら彼もまた災厄によって道を失ったもののようだった。
「わからない。腹が減って、何も」
〈医療の知識はないんですが……まずは病院ですかね。それとも研究施設?〉
妖精は僅かに思案したが、すぐに衛星のデータベースを検索し、該当の施設を絞り込んだ。
〈まだ現存しているかはわかりませんが、付近にありますよ。行ってみたらどうでしょう〉
「わかるのか」
〈当然です。そのための機械なんですから〉
青年の顔は缶詰が開いた時と同じくらい明るくなった。
〈……アナタ、名前は?〉
「アレキサンダー」
その発音は聞き取れるかどうか微妙なところだったが、彼は自分のナイフの柄を指差した。そこには偶然にも彼の名と同じ、著名な刃物メーカーのロゴが彫られていた。
〈ではアレックス、まずは最寄りの病院に行きましょう。しばらくはアナタの所有物になってあげます。目的地に着くまで〉
「お前は」
彼は首を傾げる。
「……缶詰……んん……樽?」
〈缶詰でも樽でもありません。私の型番はD10‐GNS〉
「………でいてん」
〈言いづらければ愛称でも構いませんよ〉
「樽」
〈それ以外で。……アナタがアレキサンダーなら、私はさしづめディオゲネスでしょうか。10はアイ、オーとも見えますし〉
「ダイ、オ、ゲネ、ス?」
〈じゃあダイオゲネスで結構です〉
ふたりは廃墟を後にして、目的地へと歩き出した。
辿り着いた場所は既にただの荒地となってしまっていたので、結局そのままふたりは長い旅を続けることとなった。
妖精はその後ずっと樽と呼ばれたし、旅の間は旧い世界の栄光について飽きることもなく喋り続けていた。実に様々なことがあった。アレックスは様々なものを見て、聞いて、食べた。それはまた別の話だ。
「坊主!」
晴れた日の荒野、吠え声を上げて走る虎の群れ。その一台の助手席から禿頭の男が身を乗り出し、荷台に向かって声を張り上げた。
「アレックスって呼んでくれよ」
剥き出しの荷台から同じように身を乗り出して、彼は答える。
「ひょっとしたら、アンタより長生きしてるかもしれないんだぜ」
「今日の稼ぎだ、ミスター・アレックス」
男は缶詰を放り投げ、彼は器用に手を伸ばしてそれを掴み取った。
「腹減ってるんだろう」
「いつも通りな!」
この男はキャラバンの長で、この虎の隊列は集落から集落へ、様々な物資を売り捌きに向かうところだった。
もう何年か前のことだが、アレックスは荒野の道すがら魔物を獲って食べた。それがたまたまこの男を救うことになったので、彼は時折こうして荷台に乗り、隊商を護衛する狩人として雇われるようになった。
アレックスは上着のポケットから缶切りを出して、慣れた手つきで旧い世界の食べ物にありついた。缶を開けるのにわざわざナイフを使うのはやめた。こっちの方が便利だからだ。
〈あっちこっち渡り歩いて、もう随分経ちました〉
いともたやすく缶をこじ開けられるようになった主人の横で、妖精はひとり陰気に呟いた。
〈私は機械……道案内のための……それも優秀な……おそらく……きっと〉
「お前がいてくれてよかったよ。飯も食えるしな」
ふたりは衛星のデータベースに残されていた目ぼしい施設を片っ端から回っていった。普通の人間では立ち入れないほどに呪われた土地でも、ふたりには関係なかった。そういう場所はどんなに腕利きの遺跡漁りにも訪れることができなかったので、食料や物資が豊富に残されていた。
あの刻印入りの上等なナイフは魔物や野盗と戦ううちにどこかで失くしてしまったが、同じ過ちを繰り返さないための良いものを見つけた。太腿にくくりつけるタイプのナイフホルスターだ。ベルトに直に吊り下げるよりもずっと使いやすかった。光に弱い眼をしている彼は、廃墟で見つけた遮光ゴーグルのおかげで日中も外を歩き回ることができるようになった。ダイオゲネスの千里眼と旧い世界の知識は、彼に様々な恩恵をもたらした。
〈飯が食えるそうで何よりですけど〉
ダイオゲネスの声は普段よりさらに抑揚なく平坦だった。
〈何の手がかりも見つかってないじゃないですか。どこもかしこも滅び放題で。廃墟、廃墟、行き着く先は廃墟だけ、ああ科学が文明が恋しい〉
「そう落ち込むなって。いつかは行くべき先が見つかるさ」
〈アナタは呑気でいいですね。こっちは死活問題だというのに!〉
「俺の呪いだぞ」アレックスは呆れて笑った。「まァ、死活っていったら、もう死んでるけど」
〈ねえアレックス……私って、何なんでしょうね〉
不意に尋ねられて、彼はゴーグルの奥の目を丸くする。
「お前はお前だろ。道案内妖精のダイオゲネス」
〈人工知性です〉
機械音声は続ける。
〈私は特別な理由を持って生み出された、使命を持った機械なんです。アナタとこうして話していること自体、この何もかも滅びた世界では奇跡のようなことなんです〉
「そうだな、お前と話してると飽きねェし、楽しいよ」
〈呪いを解くんですよ。呪いを解くんです〉
妖精の声は苛立たしげにまくしたてる。
〈どうしたらアナタの呪いは解けるんです。永久の飢え、訳の分からない不死身の突然変異なんて、今の世の中じゃ解決できる方法がさっぱり分かりません。災厄の前だってどうだったか〉
とうとう声は勢いに任せて叫び出した。
〈私は……私は人の役に立つために作られたのに!どうやってアナタの役に立てっていうんです! どうやって!〉
「お前は十分役に立ってるよ」
〈同情は結構です!〉
「なァ。もしお前がいなかったらさ」
アレックスは宥めるように相棒の上面を軽く叩いた。
「俺は自分がどこかに行く時、行き先が決められるってことも知らなかったんだ。目的地、っていう言葉も」
〈いくら何でも、行き当たりばったりにも程があるでしょう〉
「だろ」
彼は頷く。
「お前が行く先を決めて、それをひとつずつ見て回るだけでも、『そこにはない』ってことがわかるんだ。それで十分、目的地に近づいてる。俺にとってはそれが導きだ。だからお前は、道案内の妖精だよ」
〈…………〉
ダイオゲネスはそっぽを向くようにその場でくるりと回転し、メインカメラを主人とは反対側に向けた。
〈……人工知性です。随分流暢に喋るようになったもんですよ。あんなにぎこちない話し方だったのに〉
「どこの誰のせいだろうな」
アレックスは意地悪げに微笑み、車のハンドルを切るように上面を掴んで、妖精をくるくると回した。
「散々お喋りに付き合ってきたからな。言葉を話すには、同じくらい言葉を聞かなきゃいけないんだってさ」
〈誰が言ってたんです、誰が!〉
「さあ、忘れちまった」
彼は笑った。
「ははは。回ってる、回ってる」
〈よしなさい! 私は科学の粋! 優秀なナビゲートロボットなんですよ!〉
妖精は喚いたが、されるがままに彼の照れ隠しに付き合ってやった。
「仲いいなあ、あいつら」
禿頭の男は荷台から聞こえてくる声を車内で聞き、地図を広げて道程を確かめながら、肩を竦めた。