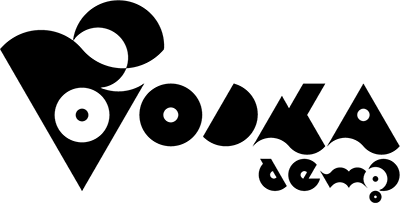そこは天の頂だった。
傷ついた大地に降ろされた無機の糸は、時の波にも災厄の炎にも揺らがず、これを辿る旅人の来訪に備えて磨き上げられていた。人間が宇宙から全て立ち去ったあとも、長い間、この頂は訪れるものを辛抱強く待ち続けていた。
広大な広間の奥に据えられた、円筒状の分厚く透明な覆いは、かつての水族館にあったような堅牢な水槽を思わせた。その中は凍てつく真空の暗闇に満ちていた。中心には強固なケーブルが通っていて、遥か下の地表まで続いている。透明な覆いの底の穴は、地表から訪れるはずの巨大な籠のためのもので、それとぴったり同じ幅で作られていた。
しかしこの日、ケーブルを辿り頂を訪れたものは籠ではなかった。それは鯨のための器に落ちた蟻のように小さく、宇宙の暗黒に溺れていた。
来訪者は風に吹かれる枯葉に似てくるくると回りながら、覆いの中へ紛れ込んだ。持ち主の手を離れた風船のように底から上へ、いよいよ行き止まりに辿り着くとぶつかって宙に弾んだ。真っ白な天井には得体の知れない染みがついた。
それは無重力の反動に弄ばれて、再び自分の来た方へと漂い出した。頂は訪れたものを受け止めるためにゆっくりと、底穴の絞り羽に似た蓋を閉じた。人工の重力が頂に満ちて、訪れたものを床に縫い付けた。透明な覆いは床と天井の中に滑っていき、道を開けて来客を広間に招いた。
それはぼろぼろに傷つき、元の姿がわからないほどに歪んだ肉塊だったが、どうやらまだ自らの力で動けるようだった。
しばらくは床で震えていたが、やがて手とも足ともつかないものを伸ばして這いずり始めた。赤黒い跡を残しながら、どこか行くべき場所を目指すべく前へ、前へと進む。 血の赤はこの空間に唯一の色らしい色だった。辺りは一面真っ白で、天井の照明が影を落とさなければ、壁と床の継ぎ目も見えないほどだった。
ゆったりと弧を描く意匠で飾られた純白の施設は、無機質ではあったが、どこか柔らかさも感じさせた。ここは教会の聖堂に似た神聖な空間だった。
数百年ぶりの巡礼者は血で跡を引きながら、何かを求めるように進み続ける。
ある地点まで来ると、機械でできた無数の管が蔦のように壁を伝って現れ、訪れたものを労わるように包んだ。床や壁、天井から伸びた管のいくつかは、先が細く長い針になっていた。優しく抱きとめられた肉塊は管に繋がれ、そこには微弱な電流が流れた。
その瞬間、アレックスは見たこともない無傷の景色の前に立っていた。
は、と声が漏れる。
目の前には小さな澄んだ小川が流れていた。その向こう一面に広がる、陽に照らされて金色に輝く麦の畑。足元は肥沃な土。高い青空。吹き抜ける秋の風。小川に向かって自分の影が長く伸びている。影は人の形をしていた。
〈とても遠い旅をしてきたね〉
声が聞こえた。麦畑の上の空には光が浮かんでいた。規則正しい記号を世界の秘密の理に沿って並べたような、淡く虹色に光る幾何学。
「あ」
口を開くが、言葉が出てこない。
「………う」
ひどく寒くて、長い道程だった。何もかも忘れてしまった。
〈きみは辿り着いたんだよ〉
穏やかな美しい煌めきは、訪れたものに優しく語りかけた。
世界の果てには天まで届く高い塔が立っている。
人を救うために妖精が残した機械仕掛けの塔。その頂には美しい聖域があり、あらゆるものを癒すという。
塔の麓には無数の屍が山を築き、かつて撒き散らされた瘴気で満ちている。生きてそこまで辿り着けるものは誰一人としていない。道が絶たれた今でも、塔は聖域へ訪れるものを待ち続けている…… そう言い伝えた人々は『塔』と呼んだが、軌道エレベータは地上から建てる建築物ではなく、宇宙から下ろす糸だ。エレベータという名ではあるが、その構造はむしろ列車に似て、一本の線路上を行き来する機械の籠を持つ。赤道の海上に浮かぶ人工島のターミナルから、静止軌道ステーションまでの距離は三万五千キロメートル。本来は『クライマー』と呼ばれる籠に乗って、一日足らずで昇れるはずのものだった。
地表は壊滅的に汚されていたが、最後にひとつだけ残されたクライマーは、ターミナルの機械たちによって注意深く整備されていた。
きみはそれに乗った。 しかし、きみの乗ったクライマーは激しい小隕石の嵐に遭い、道半ばで壊れてしまった。きみは宇宙空間に取り残された。
………きみは諦めなかった。燃え尽きる籠を抜け出してケーブルを掴み、それを昇り始めた!
長い長い時間をかけて、きみは昇った。生身のきみは真空に血を沸騰させ、絶対零度に凍てつき、何度も命を奪われるような傷を負った。
だが驚くべきことに、きみは不死の身体を持っていた。繰り返し繰り返し気を失い、力尽きながら、また蘇り、きみは昇り続けた。
ターミナルの機械たちも、わたしも、きみを見守ることしかできなかった。再生する自分の身体を喰らいながら、きみは昇り続けた。きみは自分の行いに適するように、ゆっくりと自らの姿を変えていった。きみの口は自分の身体に噛みつき、尾を噛む蛇のように繋がってしまった。きみの身体はケーブルを離さないように丸くなって絡みついた。きみの瞼は目を刺す恒星を見ないように閉じてしまった。それでもきみはどこまでも昇り続けた。
長い時間をかけて、そうしてきみはついに辿り着いた。 ここは静止軌道ステーション『ZENITH』。旧い言葉で『頂』という意味だ。
ここは人の願いを叶える場所。わたしはそのために造られた。
声は尋ねた。
〈きみの願いは?ここへこうして辿り着くまでに切望した、きみの願いは?〉
アレックスには答えられなかった。
前へ、上へ、先へ。とにかくどこかへ。ネジ巻き式の玩具のように、ただただその渇望が頭の中に残っているだけだった。
前へ……麦畑の方へ進もうとして、アレックスは自分に見えない枷がついていることに気づいた。身体が動かない。止まったらダメだ、止まったら凍る。何でもいい、何か、何か食えるものを。彼の本能は枷を強く引いた。進め。食い物を探せ。前へ。
〈こちらに来てはだめだ!〉
声は慌てて叫んだ。
〈きみが今見ているのはわたしたち妖精の世界、生と死の狭間だ。きみにはまだ肉体がある。そのラインを越えたら、きみという命は失われてしまう〉
うう、と喉の奥から唸り声が溢れた。小川の向こうで一面の金の穂が風に揺れる。何もかも失ってしまっても、飢えだけは何も変わらず彼の心に巣食っていた。
〈そう……挨拶がまだだったね〉
苦悶する巡礼者の気を紛らわすように、声は優しく語りかけた。
〈わたしは妖精だ。名はイフェイオン。昔の花の名前だよ〉
わたしは地表が滅びるずっと前に造られた。わたしは人のための道具だ。わたしの命題は人を幸福にすること。
人々は死を恐れた。だから彼らはこの施設を造った。
わたしとこの頂の命題は、人を生かすことだ。病を取り除き、傷を癒しても、人の命には必ず死が待ち受けている。
われわれ妖精の提案はこうだった。死とは肉体‐シェルの持つ現象だ。精神‐ゴーストのバックアップがあれば、失うことを恐れる必要はない。つまり人間を死から救うためには、その精神を情報の羅列に換えて機械の中に複製してしまえば良い。
ここはそのための施設、わたしはそのための機械なんだ。……だが結局、人間の魂を肉体から引き剥がすことはできなかった。
肉体を失くした瞬間、人間の精神は死という現象に耐えきれず、例外なく消滅した。人間は誰もそのラインを、生きたまま越えることはできなかった。
イフェイオンが語る間も、アレックスはまた枷を引き、聖堂に横たわる肉塊は身をよじらせた。
無機の声は戸惑ったが、ふと気づいて尋ねた。
〈そうか、きみなら〉
彼を繋ぎ留めているのは、過去にそれを試した他の誰よりも強固で重い鎖、呪われた不死の肉体だった。
〈身体も心も不死のきみならば、こちらに来られるかもしれない。それがきみの願いか?〉
肉塊は血を流しながら悶えた。
〈では、手を貸そう。その鎖を断ち切ろう〉
声は現実世界の聖堂を操った。
傷ついた巡礼者の周囲にはいくつもの機械の腕が伸び、その身体を手際よく透明な箱に詰めた。
痛んだらすまない、と声は詫びた。一瞬ののち、繋がった管を伝って凄まじい力が箱に流された。 アレックスは激しい衝撃に呻いた。
肉塊は灼ける間もなく白熱して輝き、毛糸の編み物をほどくように消えていった。長旅を経て尚もその身体に絡みついていた、いくつかの金属だけが箱の中に焼け残った。
彼の肉体は骨の塵すら残らなかった。もう戻らなかった。不死の枷は解かれた。
突然、アレックスは身体が羽根のように軽くなるのを感じた。締め付けられるように重かった四肢が解き放たれ、重心を崩してその場に倒れ込んだ。土は柔らかかった。
「あ、う」
見えない力が彼を抱き起こした。足取りの覚束ない彼の手をとって、声は麦畑の向こうへ、小川の先へ巡礼者を招いた。天に輝く幾何学に導かれて、ふらふらとアレックスは歩いた。妖精は川の前で彼の手を離し、向こう岸から呼びかけた。
〈おいで〉
風がアレックスの頬を撫でた。
陽にきらめく浅い水面を跨ぐと、その足は融けて光になった。だが、かき消えはしなかった。彼は躊躇いもなく川を渡った。麦畑の中はこれまで感じたことのないほどに暖かく、心地良かった。
〈ああ、きみは……今……われわれの世界に唯一、生きて足を踏み入れたんだよ!〉
イフェイオンは喜びの声を上げた。
妖精によって構築された仮想空間の中で、アレックスの身体は全て融けてしまって、眩い橙色の光になった。それはかろうじて彼の一番記憶に深い自分自身の姿を留めてはいたが、磨りガラスを通して見たように曖昧にぼやけて、今にも麦の中に紛れてしまいそうだった。
〈さあ、行こう。早くサーバに記録しなければ、きみは情報の渦に飲まれてかき消えてしまう〉
幾何学は麦畑のさらに奥へと彼を誘った。アレックスは麦に触れようとした。だがそれは風に揺れるカーテンを押しのけるように、あるいは霧をコップで掬おうとするように、手をすり抜けてしまう。
彼はまだ空腹だった。
〈待って!〉
穏やかな光の世界を掻き乱すように、悲鳴に似た声が背後から、彼らを呼び止めた。
〈ダメです! まだ行ってはダメ!〉
川の向こう岸に現れたのは、呪術の文様のような禍々しい幾何学だった。それは箍を外した樽板を円状に並べたようにも見えたし、この世のあらゆる複雑な文言を敷き詰めた文字の集合体にも見えた。
〈アレックス!〉
呼ばれた彼には聞き慣れた声だった。
〈きみは?〉
麦畑の中から、イフェイオンは尋ねた。
〈友人です!もしくは道先案内人!〉
対岸の蛍光グリーンの文様は、壊れた電灯のように不安定に、ちかちかと瞬いた。
〈……私は情報衛星D10‐GNS。そのデバイスを通して軌道上の本体からアクセスしています〉
現実世界の透明な箱の中には、赤く光る円錐状の機械部品が残っていた。
管のひとつが伸びて、その部品に繋がった。川の向こうの光は瞬きを止め、天の幾何学模様と同じ程度の光量に落ち着いた。
〈話を聞かせてくれないか〉
〈そのままじゃダメなんです……! サーバに記録するということは、変換したときの精神状態を永久に保つという意味〉
〈そのための仮想空間だ。変換前に、気持ちを穏やかにさせるための〉
〈ダメなんです。彼は飢えているんです、常に自我を蝕まれる程に。何があってもずっと空腹のまま。それが彼にかかった呪いなんです〉
静止軌道ステーションは接続した情報衛星の送ってきた記録を読んだ。機械同士の情報のやりとりは一瞬だった。呪いを巡るふたりの長い旅の記録を見て、イフェイオンは、そうか、と嘆いた。
〈それでは、ここは無限の牢獄だ〉
〈仰る通り〉
現れた妖精は気を落としたように答えた。
〈きみは彼をよく知っているんだね〉
〈ええ、まあ、長いこと観測していたもので〉
声は言い淀んだが、間を置いて続けた。
〈彼をここに導いたのは、私です〉
〈わたしには最適解がわからない〉
〈飢餓さえ、ただそれさえなんとかなれば……空腹を取り除く方法さえあればいいんです。アナタならそれができると思った〉
〈われわれには情報を書き換えることはできない。できるのは記録したり、複製したり、どこかに移したりすることだけだ。きみも同じ妖精なら、わかるだろう〉
〈私は道案内しかできないただのナビゲータです。アナタはこの世に残った、最も優れた人工知性〉
情報衛星は震える声で懇願した。
〈科学の粋、最高の知性、この世の頂。アナタなら、不可能を可能にできるはずなんです。私は知ってしまった……地表にはもうこれ程の機能を持った設備は何ひとつ残っていない。この施設だけが唯一の希望なんです。お願いです、彼の呪いを解けるのはアナタだけなんです!〉
〈わたしはこれまで誰ひとり救えなかった。役に立たない、意味のない道具だよ〉
淡い光は穏やかに自分を笑った。
〈彼の旅は報われるべきだ。でも、われわれには……永久の飢えか、死という終焉か、どちらが彼にとっての幸福なのかはわからない〉
イフェイオンは巡礼者の背を優しく押して、川の向こうへ歩かせた。
〈自分で選びなさい、アレックス。ここまで辿り着いたのはきみ自身なのだから〉
川を越えて戻っても、今度は何も起きなかった。緑の幾何学模様は羽を広げて主人を抱きとめた。
〈……どっちにするんです〉
声は尋ねた。
「ダイオゲネス」
ぼろぼろに傷ついた身体から解き放たれたアレックスは、宇宙の冷たい暗闇に置き去りにしてきた、自分を形作る様々なものを取り戻した。機械同士で交わされた旧い言葉のやりとりも、不思議と全て理解できた。久々に聞いた相棒の声に、彼は笑顔で呼びかけた。
「……だよな。なァ、また会えてよかった!」
〈ちゃんと聞いてたんですか、今の話〉
ダイオゲネスは呆れて言った。
「綺麗だな。ちょっと樽っぽいけど。本当に星みたいだ」
〈そうですよ、美しいでしょう。私のソースコードを目視した人間は、後にも先にもたぶんアナタだけです。機械が人間の魂を観測したのも、おそらく史上初めてのことでしょう。……そう、アナタ今、我々と似たようなものになっちゃってるんですよ〉
緑の文様は、目を細めるように、僅かに輝きを弱めた。
〈『人は死んだら星になる』とは、誇張表現ではないのかも〉
「それって褒めてんのか?」
〈嘆いてるんですよ。自分の状態を見なさい〉
アレックスは自分の手を見た。光は滲んで、かき消えてしまいそうだった。
「……俺、いよいよ死んじまうのかな」
〈このまま放っておけばそうなります。それが嫌なら、イフェイオンと共に行くんです〉
「あの麦は食えないんだよな」
〈アナタが見ているのは全て、何らかの情報の比喩です。ここにアナタが口にできるようなものは何ひとつありません〉
「そうか」
アレックスは俯いた。
〈……すみません、アレックス〉
「お前は一番いい道を選んでくれたんだろ」
〈すみません。私……私、結局〉
「お前らしくないぜ」
彼は首を横に振る。
「きっと他の方法を試した時より、一番いい二択なんだ。何にも分からないまま延々と彷徨うより、ずっとマシだ」
〈では、どうするんです〉
「………そうだな」
再び自分の手を見る。輪郭は少しずつ風景との境界を薄れさせていく。ゆっくりと目を閉じる。
「ここに来るまで、寒くて……しんどかった。けど、それでも死ななかった。あれでも平気なら、きっと他の場所じゃ絶対に死ねない。これが一番まともな終わり方なのかも」
ここは穏やかで、暖かい。柔らかな毛布に包まれているように心地良くて、そのまま何もかも忘れてしまいそうだった。
「だから……でも……」
身体の中心に未だ残る、空虚な衝動を除いては。
「お前の言う通り、宇宙って本当に何にもなくてさ。ずっと自分の肉食ってたんだぜ。やっぱり不味かったな」
アレックスは笑った。
「はは、は。腹減ったな。あれが最後の飯なんだ。もう何も食わなくていいんだな……はは……」
声は哀しかった。
「腹減ったな。もう、身体もなんにもないのにさ。何でまだ腹が減るんだろうな、はは、は、あはは……」
彼は笑い続けた。この世から消えてしまうまでずっとそうしているつもりのようだった。
ダイオゲネスは幾何学の翼で彼の魂を抱くしかなかった。
〈身体〉
突然、緑の文様が激しく瞬いた。
〈身体。そう、身体です〉
「え」
〈イフェイオン!〉
文様はひときわ明るく輝き、川の対岸に浮かぶ虹色の光に向かって呼びかけた。
〈データベースの記録によれば、災厄の前に造られた地下シェルターには、無機有機問わずあらゆるものを塵から生成する装置がありました〉
〈『HOLLY』のことだね〉
かつてオールグリーンと呼ばれた機械の女神を指して、イフェイオンは古い友人を懐かしむように言った。
〈ホーリイ、とは柊。植物の名だ。われわれの根幹は同じプロジェクトで、みな花や草の名をつけられた。彼女は役割上、妖精ではなかったが〉
〈この施設には同じ機能があるはずです。物資の少ない宇宙で、訪れる人間を養うために〉
〈その通り。わたしは彼女の兄妹機だ〉
〈人間の身体を作ることはできますか〉
〈造作もない〉
頂の妖精は即座に答える。
〈しかし、身体だけだ。別の用途に特化したわたしが作れるのは、空っぽの器だけ。それでは死体になってしまう〉
〈むしろ好都合です!〉
ダイオゲネスは文字通り宙に舞い上がった。
〈……きみは何をひらめいたんだ?〉
禍々しい緑の幾何学は、広げた樽板に似た羽を明滅させた。
〈記録、複製、移動。我々が情報に対してできることがその三つならば、三つ目は可能なはずです〉
〈死体にか?〉
イフェイオンは戸惑いの声を上げる。
〈魂を取り出すのだって、今初めて成功したんだ。逆はそれこそ誰も試したことがない。まるで呪術だ〉
〈呪術だろうが魔術だろうが構いません。力を貸してください、彼が消えてしまう前に!〉
妖精たちの間を、目を丸くしたアレックスの視線が往復する。
「なんか見つけたのか。最後の晩餐食う方法とか」
〈アレックス、三択です。選択肢を増やしました。永久に飢えたまま存在し続けるか。このまま消滅するか。どちらでもない方法を試すか〉
「それは?」
ダイオゲネスは向き直る。
〈新しい身体に、アナタの魂を突っ込みます〉
「どうなるんだ」
〈動き出すかもしれない。上手く行けば、アナタは生きて、ただの人間になる。呪いは解ける〉
「上手く行かなかったら」
〈良ければ死ぬかも〉
妖精は声をひそめる。
〈悪ければ……もっと酷いことになるかも。わかりません。何しろ倫理的に問題だらけで、計算もできません〉
「悩む暇もなさそうだな」
アレックスは自分の光をもう一度見る。
〈どうします〉
「お前が思いついたんなら上手くいくさ」
彼は薄れかけた拳を握りしめた。
「腹減ったままなのも、死ぬのもごめんだ」
アレックスは叫んだ。
「俺は呪いを解くんだ! このまま消えてたまるか!」
その言葉に呼応するように、虹色の淡い幾何学が川の対岸で輝く。
〈きみの願いを叶えよう。きっと前の身体と似ているもののほうが良いだろう〉
現実世界の聖堂では天井の一部が開き、そこからは透明なビニールパックが降りてきた。
本当に造作もない、というふうに、中には人間の身体が入っていた。ダイオゲネスから送られた情報を元に似せたそれは、地表にいた頃のアレックスと爪の先まで瓜二つだった。
それは先ほどまで肉塊の入っていた箱の横に置かれ、機械の管は作られたばかりの新鮮で未使用の死体に繋がれた。
同時に妖精たちの世界では、アレックスの足元に大きく真っ暗な穴が開いた。覗き込んでも底が見えない。穴の闇はあらゆる光を飲み込むように黒一色で塗りつぶされている。
〈わたしには何が起こるか想像もつかない〉
イフェイオンはため息をつくように囁いた。
〈しかし、きみはここまで辿り着いたんだ。可能性は無ではない〉
「アンタに頼みがある」
〈わたしに叶えられることなら〉
「何でも作れるんだろ。もし上手くいったら……」
アレックスは穴の淵に足をかけた。
「昔の世界で、美味いって言われてたものが食いたい。こいつがよく話してたから」
ダイオゲネスを見て指差す。
〈きみが息を吹き返したら、満腹にさせることを約束しよう!〉
頂の妖精は朗々と答えた。
〈きみの旅の成功を祈る。また会おう。何を作るか考えておくよ〉
〈行きなさい、アレックス!〉
妖精たちを一度だけ振り返って、彼は闇に飛び込んだ。
何も見えないひんやりとした暗闇の中、アレックスはどこまでもどこまでも落ちていった。ケーブルを掴んで昇った距離より長いんじゃないか、と思うくらいに、いつまでも闇は続いた。
暗闇。
ふと気がつくと、彼は扉の前に立っていた。ここはどこだ?と自問するまえに、彼は気づいた。故郷だ。
壁の裏。もうどの位前か思い出せない程昔、目の前で閉まった機械仕掛けの扉。
開けてよ、と叩くが、あの時誰の名を呼んでいたのかも出てこない。身体じゅう血に塗れている。半分は自分の、半分は突然空から降ってきた得体も知れない怪物の。
暗くて、寒くて、恐ろしかった。ここが開けば外に出られる。逃げられる。この扉の向こうはあの老人が幾度となく語り、そして出て行った、広い広い世界に続いているはずだった。だが開かない。血の気が引いて身体が震える。寒くて凍えている。息ができない。喉がからからで、胸が締め付けられて吐きそうだ。 苦しい。
いやだ、死にたくない。どうしようもなく怖かった。いやだ、開けて、開けてよ。力の入らない手では、扉はびくともしなかった。
死にたくない。事切れる直前まで、彼は何度もうわごとのように繰り返した。死にたくない。
この扉の外に出られるなら……何を引き換えにしてもいい。そんな風に願って、彼は死んだ。
でも、あれは俺じゃない。
「お前の願いは叶っただろ」
アレックスは扉を殴りつけた。
「俺のはまだだ」
死んだのは俺じゃない、だって生きてたこともないんだ。 あいつが死にたくない、と思ったのは、死んだらもうものが食えなくなるから、じゃない。あいつは本当に怖かったんだ。怪我すると腹が減るから、じゃない。
俺は自分で、心の底から何かを考えられたことなんて、一度もない。俺の頭はいつだって何かを食うことでいっぱいだ。 俺がしたいのは、自分の頭でものを見て、考えて、なにかをすることだ。何かを食うためじゃなく、俺自身の意志で。
「俺は自分の願いも分かんないんだ」
不死の身体は、ただただ衝動的に突き動かされてきた。飢え、という自分の意志ではないそのたった一つの理由に、彼は常に掻き乱され、何もかも捻じ曲げられてきた。
「知りたいんだ。俺が何考えてんのか!」
きっとこの先にその答えがある。そんな気がした。アレックスは何度も何度も扉を殴り続けた。不死なるものでも、魔物でもない、ただのアレキサンダーになるために。彼は扉を蹴り飛ばした。
「開け!」
鉄の扉は僅かに歪んだ。
〈何か反応が起きるとしたら〉
二分経った。
見た目こそ地表を歩いていた頃の彼と同じとはいえ、そこに横たわるのは、ただの死体のままだった。
〈数分のうちだろう。情報となった精神が自分を保てる時間は、そう長くはない〉
〈アレックス〉
妖精たちは固唾を飲んで聖堂の観測を続けたが、命なき肉体が動く気配はなかった。それがまだ、なのか、もう、なのか、判断はつかない。
〈一般的な蘇生法を試してみよう〉
イフェイオンは聖堂の壁を伝って新たに管を伸ばした。死体の左の胸元に針が潜り込む。数秒数えたのち、激しい電流が流れた。
何も起こらない。別の管が潜り込み、肉体の内側から心臓を物理的に動かそうとする。
〈もう一度〉
再び電気ショック。イフェイオンは措置を続ける。三分経った。
〈息をして……動かすんです……アナタの身体を〉
ダイオゲネスは祈るように呟いた。死体は動かない。
〈アレックス……〉
緑の幾何学はすがりつくように瞬く。
〈なにか、なにか私にできることは〉
五分。
イフェイオンはしばらく黙り込んでいたが、やがて仮説を挙げた。
〈人間にとって、意識的に肉体を動かすのは、あまりに複雑すぎるのかもしれない〉
死体の横たわる側で、透明な箱の中から、機械の腕がダイオゲネスの眼を拾い上げた。
〈そうだとしたら、導くものが要る〉
「開けッ!」
アレックスは全身で扉に突っ込んだ。
重い扉は遂に破られた。勢いで倒れ込んだ彼はやった、と叫んだが、顔を上げると息を飲んだ。
彼の前には奈落から天へ向けて、真っ暗な吹き抜けの回廊が広がっていた。そこには長い長い螺旋階段が数え切れないほどに何本も伸びている。全ての螺旋は空中ででたらめな方向に曲がりくねっている上に、階段同士がめちゃくちゃに絡まりあって、どこがどう繋がっているのかも分からない。まるで怪物を閉じ込める迷宮のようだった。
「う……」
立ち上がりながら自分の身体を見る。もう殆ど形も分からない。消えてしまったって気がつかないかもしれない。そうしたら永久にここにいることになるのかも。
寒い、と感じた。真空の世界の、暗黒の中の絶対零度を思い出す。歩き出そうとする足が竦む。
「……行かなきゃ」
自分の迷いを振り払うように一歩踏み出す。間に合うさ。階段があるだけマシだ。アレックスは走り出す。
「上だ。昇るんだ。辿り着くんだ!」
駆け上がる彼の足音が回廊に響き渡る。道が尽きるまで昇り続けて、途中で壁にめり込んだ階段から別の道へ飛び移る。螺旋の影を抜けると、遥か遠くの頂に、眩い星が光り輝いているのが見えた。
〈アレックス!〉
星の中から何かが降りてきた。階段を駆け上がり続ける彼の前までやってきて、その少し前を並走する。
「お前」
〈こっちです。ついてきて!〉
妖精は赤い眼を瞬かせ、軸の周りの羽を広げた。彼の見慣れた、小さな樽に似た姿をしたダイオゲネスは、先を飛んで彼を導いた。
互いに突き刺さり合う狂った構造の階段を、相棒の後に続いて駆け抜ける。絡み合う狭い隙間を潜り、途切れた道を渡り、三又に分かれた螺旋の真ん中を疾走する。足元から這い上る寒気を振り切って、アレックスは夢中で昇り続けた。
〈あれがアナタの命〉
あんなに遠くに見えていた星が、目の前に近づく。もう手が届く。
〈生きなさい。生きるんです、アレックス!〉
辿り着いた頂で、ダイオゲネスの声が背中を押した。彼は腕を伸ばした。星に触れた瞬間、自分の手が煌々と輝き始めるのが見えた。視界の全てが光に満ちて、真っ白になった。
光は暖かかった。