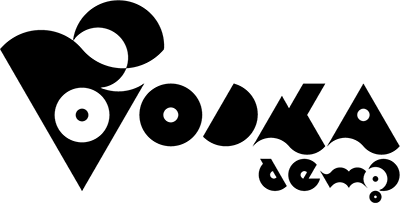〈………アレックス〉
瞼が開き、僅かな光が瞳に差し込む。
冷たい空気が肺を通り、開かれた目はぼやけた視界の先に焦点を合わせようとする。
〈アレックス!〉
「んん……」
眠そうな声が喉の奥から漏れる。
辺りは夜の深い群青に満ちている。彼は小高い丘の上に膝を抱えて座っていた。
「……今、ちょっと寝てた」
〈アナタが見たいって言ったから付き合ってるんですよ〉
身体に何枚も巻きつけた防寒用の毛布や人工毛皮を剥がして、大きく伸びをする。さっき食べた缶詰やカップ麺の空が、蹴飛ばされて足元で転がった。脇では焚き火の跡がまだ穏やかに温もりを漂わせている。
「腹一杯になると眠くなるなんて知らなかった……」
アレックスはあくびをしながら目を擦った。吐き出した息が白く煙る。夜霧は冷えたが、目を覚ますには心地良かった。
頂の妖精は別れを惜しんだが、引き止めはしなかった。
地表は今やきみには致命的な場所だろう。だが、きみが望むならわたしにはそれを止める理由はない。わたしは人の願いを叶える機械だ……人を不死の魂にするはずが、成し遂げたのはその逆だったようだが。
わたしは長い間、ここを訪れる人間の力になれる日を待った。こんな些細なことで良いのなら、わたしの命題はもう叶ったようなものだ!
そう言って、イフェイオンは楽しげにふたりのためにありとあらゆる用意をした。小さなカプセルポッドに、片道には十分すぎる資材を載せて、ふたりを地表で最も空気の綺麗なところに送り届けた。
世界に降り注いできた『贈り物』と呼ばれる流れ星は、この妖精がこうして定期的に投下していた資源であったことに、ふたりは気がついた。
新しい身体もまたよく出来ていた。多少の呪いでは死なないように強く造られていたので、地表の汚れた空気を吸って悶え苦しむようなことはなかったし、宇宙空間で作られたからといって、重力に負けて歩けないというようなこともなかった。ただ、それでも馴染むまでには時間がかかるだろう。何しろ、いつかは必ず終わりを迎えるように出来ているのだ。
あいつにはあの時、うまく行くってわかってたってことか? アレックスは相棒に尋ねたが、ダイオゲネスはいいえ、と答えた。
我々には未来が視えるわけではありません、予測をするだけです。その先に複数の可能性があれば、それに応じた備えをします。例えそうならなかったら無駄になってしまうことでも。
それって祈るみたいなもんだな、と彼は思った。
〈寝過ごしても知りませんからね〉
そう語りかけてくるダイオゲネスの声は、彼の頭の奥に響いてくる。
〈他にも見たいものがいくらでもあるんでしょ。人間の一生は短いんです〉
「わかった、わかった」
これもその祈りのうちなんだろう。彼は首の後ろに指を触れた。外から見ても手で触っても分からないが、この辺りにダイオゲネスの眼が埋まっている。正確には、あの眼の中から取り出した何か小さい板みたいな大事なものが、細い管を通して頭の中に繋がっているそうだ。この身体を動かすために、アレックス自身にはわからない些細で膨大なことを司っているらしい。
声が聞こえるのはそのおまけだよ、とイフェイオンは言った。もう不死身ではないきみが無茶をしすぎないように。
相棒の話をよく聞くことだ。今きみがそうして息をしているのは、きみの友達のおかげなのだから。
「ところで、お前がついてきてくれるのは嬉しいんだけどさ。……帰んなくていいのか、宇宙に」
姿の見えない相棒に、声を出して尋ねる。
〈帰るも何も、私はずっと人工衛星です。こうして通信を繋いでいるのは、アナタの中に組み込まれたものがみすみす野垂れ死なせるほど粗末ではないからに過ぎません。せいぜい余生を楽しむことですね〉
「俺は息してるだけで楽しいよ。お前もいるし、どこへでも行ける」
アレックスは笑った。
「だって生きてるんだぜ。俺は俺のものなんだ!」
辺りはゆっくりと色を取り戻しつつあった。朽ちた街の残骸、折り重なる瓦礫、焼けた大地、草木一つ生えない岩肌、折れた鉄塔、僅かに明かりを湛える小さな集落。丘からは、この荒れ果てた世界で今も尚滅びに向かいつつある無数の景色が見通せた。遥か遠く、天から降りる無機の糸が僅かにきらめいた。
〈そろそろ時間ですよ〉
地平線の向こうからは朝陽が昇りはじめていた。あらゆるものを分け隔てなく照らすその光は、アレックスのもとまでも違わず暖かさを届けた。
「ああ」
彼は待ち望んだ光景に、思わず声を漏らした。
「……太陽って、あんな色だったんだな」
〈相変わらず醜くおぞましい世界です。脆くて、歪で。でも〉
妖精は囁く。
〈いつか失くしてしまうものを、美しい、と呼ぶのかもしれません〉