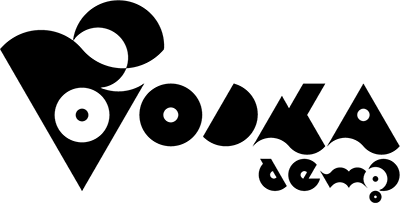「サカナって美味いんだろ」
透き通った分厚い板に思い切り頬と手のひらを押し付け、その向こうに広がる楽園へ目を凝らしながら、アレックスは呟いた。
「絶滅した理由、知ってるぜ。昔の奴らが食い尽くした。獲って獲って食いまくった」
〈一部の種に関してはその通り〉
その横から、無機質で平坦な抑揚の声が答える。
「滅ぼすほど食ったんだ。よっぽど美味いんだろうな」
〈災厄の前から魚は貴重な存在でした。だから人々はその姿を記録に留めようとした。ここはかつての水族館と呼ばれる場所であり、同時にデジタル·インタラクティヴ·アートの展示施設だったんです〉
「そりゃ美味いよな。こんなキラキラして、ピカピカしてて、スイッとして」
その日、ふたりが旅の間に訪れたのは、朽ちた水族館……凪いだ海のそばに佇むささやかな遺跡だった。外から見た姿は小さな椀を伏せたようだったが、そのドームの中には静けさを湛えた大広間と、地下へと向かって深く口を開けた階段があった。
ここはとても貴重な場所だ、と舞い上がるダイオゲネスの先導で長い階段を降りていくと、辿り着いた先には蛇の巣穴のように細長い通路が伸びていた。
通路はゆったりと円を描くように曲がりくねりながら、奥へ、奥へと続いている。
ふたりが立っているのはその迷路の壁に設えられた、大きな水槽の前だった。大人が両腕を広げても端まで届かないようなガラスの壁の中では、細かな砂の上に植えられた水草の絨毯が鮮やかな緑を輝かせている。草原の中心には広大な自然の風景を思わせる流木が横たわっており、その曲線が作り出すアーチの中を、小さな熱帯魚たちが群れをなして色とりどりに姿を踊らせているのだった。死んだ後に天国があるとしたらこんなところなのかも、と、アレックスは唾を飲み込んで溜息をつく。
「……で、なんたら芋がなんだって?」
〈本物に限りなく似せた芸術作品だと言ったんです〉
未だガラスに貼り付いている自分の主人に、ダイオゲネスは呆れながら言い改めた。
〈つまり、幻。作り物です〉
「俺はいま初めて昔の奴らがやったことを恨んでる」
〈今ここに来るまでに恨む機会いくらでもあったでしょ〉
アレックスはガラス、正確にはガラスを模した液晶画面を、どん、と拳で叩く。水槽の向こうの水は実際に振動を受けたように揺らぎ、魚たちは慌てふためいて逃げ惑った。旧い言葉の自動音声がざりざりと濁った音で、画面を叩かないでください、と注意を呼び掛けた。
「これがぜーんぶ、幻なんて!」
抗議するように相棒を仰ぐ。
「なァ。ホントに食えないのか? こんなに目の前に見えるのに?」
〈さっき自分の身を持って確認した通りです〉
つい数分前に同じように叩いて開けた穴が、彼のすぐ脇に大きな暗黒を湛えている。彼の髪には自分の手で叩き割った画面の細かな破片が、水飛沫を浴びたようにきらきらと絡みついていた。
アレックスは暗黒を覗き込む。砕かれた穴のふちは火花を散らしながら次元を違えたように点滅し、そのすぐ横を銀色に光る鱗が、姿を歪ませながら通り過ぎる。しかし穴の中には、水も、砂も、泳ぎ回る魚たちも、どこにも見えない。空っぽの空間があるだけだ。
ダイオゲネスの言う通り、水槽の中に見えるものはただの幻に過ぎなかった。かつて災厄の前に人々の作り上げた芸術作品が、未だ姿を変えずに上映され続けている。ここにはまだ動力の生きている発電機があるのだ。
〈でもアナタの反応を見たら、これを作った人々もさぞ喜ぶことでしょうね。魚がどんな生き物かよくわかるでしょう〉
妖精は軸の周りの羽を広げる。アレックスはもう一度ガラスに顔を押し付けて、水の向こうの世界を恨めしげに見た。
「そうだな。味まで想像できるくらいだ」
〈さあ、入り口で詰まってたら閉館時間が来てしまいます。もっと面白いものが見れますよ。奥へどうぞ〉
ダイオゲネスは羽をくるくると回転させて、軽快に通路の奥へと滑っていった。
〈貸切ツアーへようこそ! 本日のガイドは私、D10−GNSが務めさせて頂きます〉
「満喫してんな、お前は」
暗い通路の左右にも水槽が点々と設置され、水の屈折に揺らめく光を壁に投げかけていた。そのひとつひとつの中に、鱗を煌めかせて魚たちが泳いでいる。
〈素晴らしいでしょう!〉
「食えたらな」
アレックスは食えない幻から目を逸らそうとして、床を見ながらダイオゲネスの後に続いた。妖精は過去の文明が遺した驚嘆すべき作品を讃えながら、得意げに道の先を行く。
〈ただの映像じゃないんですよ。この魚たちはA-LIFEと呼ばれる技術によってリアルタイムで動いています。コンピュータの中に本物そっくりの環境を作ってシミュレートしているんです。さっきのは序の口。この施設の一番の売りは〉
突然ぴたり、と立ち止まったダイオゲネスに足をぶつけて、余所見をしていたアレックスは転びかけ、小さく声を上げた。
「わ」
〈拡張現実をデバイスなしで実現したこの展示です〉
顔を上げるといつのまにか通路を抜け、広い空間に足を踏み入れようとしているところだった。
辺りは薄く霧がかかったように霞んでいた。照明が絞られた薄暗く青い広間には、水の波紋や揺らめく模様がスポットライトで映し出され、まるで水底を歩いているかのよう。周囲は岩場に似せて凸凹を施された壁で囲まれており、広間の所々にも、自然を模して大小様々な岩が並べられている。室内であることを忘れてしまいそうな光景だ。
「お前にとっちゃ、遊園地みたいな場所だと思うけどさ」
〈ほら見て、足元〉
「俺には食えなきゃ何にも意味ない……」
言われて足元に目をやったアレックスは、咄嗟に太腿のナイフに手をかけた。巨大な蛇のような、反物のような、薄く細長くぎらぎらしたものがうねりながら自分の脚の間をくぐり抜けていく。
「魔物ッ!」
逆手にナイフを握った腕を振りかざして突き刺そうとするが、手は虚しく空を切り、魚は悠々と空中を滑っていった。泳ぎ去ろうとするそれを追いかけ広間の中心へと躍り出て、行き場をなくした衝動を消化するように、むやみやたらとナイフを振り回す。
「この、この、このっ」
〈こちらの一角は深海魚を間近で観察できるコーナー。図鑑好きの小さなお子様に大人気でした〉
「また幻か! わかってたけどッ!」
全長4メートルはあろうかという魚は龍のような身体を折り返して、巻きつくようにアレックスにまとわりついた。諦めきれずに摑みかかろうとするが、その手は霞のようにすり抜けてしまう。明確に捕食の意を向けられているにも関わらず、魚は一向に介さず、訪問者にじゃれつくように泳ぎ回っている。
「でかい。長い。食い甲斐ありそう。うまそう。脂乗ってそう」
〈実に見事な立体映像です。歯の一本一本まで正確にモデリングされています〉
「災厄の起きる前にも魔物がいたのか」
〈確かに奇妙な見た目ですが、魔物じゃありません。もともとこういう姿なんです〉
「へえ。なんで」
〈わかりません。実はどんなものを食べていたのか、どんな風に暮らしていたのかも不明です〉
「そこにいるのに?」
〈わかるのは見た目だけ。よく調べる前に人間のほうが滅びてしまったんです〉
ひとしきりまとわりついて、幻の龍は深海を模した岩場の奥へと、うねりながら去っていく。ある程度ふたりから離れると、その姿は霧のようにふっと消えた。
〈深海は謎が多く、データベースにも記録があまり残っていません。ここに展示されているのは貴重な映像。よく見ておいたらいいですよ〉
「食えないのに」
〈食えないからこそです。食べられたら見ないで食べちゃうでしょ〉
ダイオゲネスは向き直る。
〈いいですか。こんな施設がここまで状態良く残っているのも千に一くらいの奇跡。いつ電源が止まるともわかりません。この光景おそらくは、この世で見られるのはアナタが最後なんですよ〉
「最後に見るのが俺みたいなので申し訳ないね」
アレックスは抜いたナイフを手持ち無沙汰に放り投げ、指先でくるくると回して、太腿のホルスターに挿し直した。
「もっと気の効いた奴がお前の相棒だったら、お世辞くらいは言えたかもな」
〈でも、本物かと思ったでしょ?〉
「本物だったらよかった」
〈それで十分です。ここはそのためにある施設ですから〉
ほら、また別のが来ましたよ、とダイオゲネス。岩陰から新たに奇妙な魚が、訪問者をもてなすように泳ぎ回る。ぼんやり発光するものや、目を剥きだした頭だけが透けたもの、のこぎりのような顎を持ったもの、色とりどりに輝くもの。
〈観察してみてください。もう二度と会えない作品なんです〉
「食えないけどな」
岩で出来た広間の中心には丁度良く平らな小岩がいくつか並んでいて、アレックスはそこへ腰掛けた。
「でも、食えないって分かると、案外落ち着いて見てられるかも」
近寄ってくる魚に向かってじゃらされる猫のように手を振りかざしながら、彼は呟く。
〈全然落ち着いて見えませんけど〉
「サカナって光るんだな」
〈深海魚の特徴です〉
アレックスは遮光ゴーグルの奥の眼を細めた。魚たちは幾数年ぶりに訪れた人間に自らの姿を記憶させるように、現れては消え、現れては消えを繰り返す。無数の生物が発光ダイオードのように点滅しながら薄暗闇の中を漂う光景は、晴れた日の深い夜、空を見上げた時に似ていた。
「うまそう。それに、星空みたいだ」
〈アナタからそんな言葉が聞けるとは〉
「もっとロマンチックなこと言ってやろうか? 惚れちゃうくらいに」
〈『砂糖漬けのトゥインキーみたい』とでも?〉
「サイコー。歯が浮くほど甘い台詞」
最初に現れた龍に似た魚が、再び彼の前を滑っていった。立体映像は精巧だったが、記録された魚の種類は絞られているようだ。アレックスは奥歯を噛む。光るものは好きだ。綺麗だと思う。でも、それ以上に味が確かめたかった。どんな匂いなのだろう。どんな歯応えなのだろう。どんな風に筋の通った肉で、どんな風に血が滴るのだろう。遠目でぼんやり眺めていた星々にふと目の焦点が合う。どれも、これも、噛みついた時の感覚が思い描けるくらいにリアル。一度想像してしまうとダメだった。もう星には戻らない。涎が止まらない。袖で乱暴に口を拭って、彼は幻から目を背ける。
「ここを作った奴らは、よっぽどサカナが好きだったんだろうな」
〈ええ〉
「本物がよかった。生で食いたかった。同じ人間だろ。こんなの作るくせに、なんで滅ぼしたんだ」
〈どうして滅ぼしたんでしょうね〉
ダイオゲネスは抑揚なく答える。
〈わかりません。死人に口なしです。そしてアナタも同じ人間〉
「世の中わかんない事ばっかりだな」
〈深海は宇宙と同じくらい謎の深い場所でした。未知を知にすることは科学の発達がもたらす分かりやすい恩恵ですが、今はもうどちらも、どんな場所だったのか、知る術はありません。文明が失われて以来とても人間の手が届く場所ではなくなってしまっ……ああ〉
突然どこかでばちん、という大きな音がして、辺りが真っ暗になる。
ダイオゲネスの光る羽とカメラアイだけが取り残されて、視界に見えていた一切合切が暗闇に飲み込まれた。アレックスは立ち上がって戸惑いの声を上げた。
「なんだ」
〈たった今、施設の電気系統が落ちました。修復は不可能です〉
「サカナは」
〈もう見れません〉
遮光ゴーグルを外して額に退けると、緑の眼が闇の中に浮かぶ。夜目を効かせて辺りを見回すが、周りの光景は何も変わっていない。ただ真っ暗になっただけだ。
「なんで。こんな急に?」
〈急じゃありません。いつか訪れることが決まっていた瞬間です。それがたまたま今だっただけ
「嘘だろ。だって、何にも前触れなかった」
〈動いてるのが奇跡だったんですよ〉
「知ってたらもっとよく見といたのに!」
〈だから言ったでしょ。ショウはおしまい〉
暗闇の中、妖精は電子音で鼻歌のようにメロディを鳴らし始めた。
〈残念ながら、閉館のお時間です〉
歌を背に、アレックスは辺りをぐるりと回って、全ての岩場の陰を覗き込んだ。魚はどこにもいなかった。電子的な弦楽器で奏でられる『蛍の光』の最後の一音は、つい先程まで深海だった暗黒の中に吸い込まれていった。
ふたりは順路に沿って、来た道を引き返していった。迷路めいた通路の壁にはガラスの板と組み合わせて液晶画面が点々と埋め込まれていたが、電力の供給が断たれた今、それはただの黒い板に過ぎなかった。ダイオゲネスの行灯に似た緑の光が、ぼんやりと無を照らした。
ふと前を見ると、とりわけ大きなガラス板が通路の壁にあった。床には鋭い破片が散り、巨大な黒の隅には手で砕かれた穴が空いていた。
「なァ」
〈なんです〉
「本物も、こんな風にいなくなったのかもな」
何もいない壁面を手で触れて、アレックスは呟いた。
「ある日突然、ぷつん。後から悔やむんだ。知ってたらもっと大事にしたのに、って」
〈アナタにしては人間的な、実に愚かな発言です〉
「お褒めの言葉をどうも」
〈ひとつ面白いことを教えてあげましょうか〉
「なんだ」
〈外に出て、本物の海を見ましょう〉
長い階段を言葉もなく登って、広間を出て、傾いた重い扉を押し開ける。海風が強く吹き込んで、水族館のエントランスの床に散らばっていた古いパンフレットの束を巻き上げた。
外は既に陽が落ちて、月がよく見えた。ドーム状の枠組みで出来た水族館の蓋を背にすると、広い海原が月光に照らされて緩やかに揺らいでいた。遺跡の建つ丘の足元、人工的に固められた防波堤の残骸には、得体の知れない海藻のようなものがいくつも巻き付いているのが見えた。
〈実は、魚の絶滅は確認されていません〉
妖精が天気予報でも言うようにさらりと告げたので、アレックスはふうん、と面白くなさそうに答えて水面の波を見ていた。そして相棒に掴みかかった。
「な、な、なんだって!」
〈早とちりしないでください。『確認されてない』だけです、災厄より前に調べる方法がなくなったせいで〉
しかし確率は低いですが、と念を押して、ダイオゲネスは続ける。
〈もしかしたら、まだいるかもしれませんね。まぁ呪われてるでしょうけど〉
「いる。絶対いる! こんなに広くて深いんだぜ、絶対どっかにいる!」
今にも目の前の海に飛び込みそうな勢いで身を乗り出しながら、アレックスは海原に向かって叫んだ。
「待ってろよサカナ! 俺が見つけて食ってやる! 顔覚えたからな!」
〈私は塩水は嫌いですよ〉
「サカナーッ! 味確かめるまで死なねェからなーッ!」
〈死なないでしょ〉
海は答えなかったが、波がさざめいて朽ちた護岸に打ち寄せた。ふたりは防波堤に沿って海岸を歩き、かつて海を泳いだ様々な美しいもの、美味しいもの、人が愛したものについて話しながら、月明かりの中を次の旅路へ向かっていった。