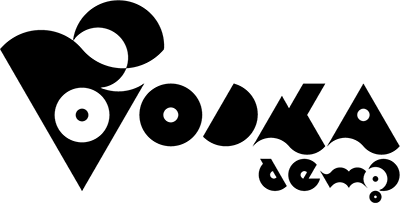〈おぞましい光景です〉
夜の帳の降りた中、ダイオゲネスは窓際から外を眺めて言った。
「そうかな」
アレックスは窓枠に腰掛け、同じ景色を見ていた。
危うげに傾いた背の高い構造物の中からは、遥か遠くまで災厄の傷跡がよく見渡せた。
陽は随分前に沈んだというのに、崩れかけた摩天楼の外壁は鮮やかな翡翠色に照らされていた。空には巨大な光のカーテンが幻影のように揺らめき、その色は絶えず妖しく移り変わっていく。あれはオーロラという現象で、本来は決してこんな場所に起こるはずがないのだ、とダイオゲネスは言った。災厄の日に引き起こされた磁気嵐が原因だというそれは、目を見張る荘厳な輝きを放っていた。
〈かつてはとても美しい都市だったんですよ〉
下界には無数の廃墟が一面に広がり、翡翠に光る花の群れがそれを飲み込まんとしていた。ふたりはここに辿り着くまでにずっとあの中を歩いてきた。鈴なりに群生する花はかつての蘭に似ていたが、蝋燭のように光を放つ。その輝きは呪いを孕んでいて、この一帯は凄まじい濃度の瘴気に満ちていた。
アレックスには心地良かった。あの花は肉厚で美味かったし、ここはすごく、綺麗なところだ。
〈もううんざりです。こんな醜い、智のかけらもないような世界〉
ダイオゲネスの声にはざらざらとした雑音が混ざっている。
〈でも、ようやく解放されます。ずっと待ち遠しかった。この施設のおかげで、私の旅は終わるんです!〉
そう言う機体は宙に浮かず、床に降り、羽も消えている。金属の身体の軸には何本も管が突き刺さっていて、その反対側には、部屋の天井まで届く巨大な機械の祭壇が鎮座していた。アレックスにはそれが何かはよく解らない。しかし、この管を繋いだのは自分で、ここまでこの妖精を連れてきたのも自分だった。ダイオゲネスがそう望んだからだ。
ふたりの行き先は最初から一致していた。ダイオゲネスは過去世界の知的な遺産を恋しがった。いにしえの賢者の痕跡を調べれば、呪いを解く方法がわかるかもしれなかった。旧い文明の遺跡では、食べ物や、良い品物がよく見つかった。出会って以来の長い道程、アレックスはダイオゲネスの導きに従って旅を続けてきた。しかし彼は、妖精が何をしたくて文明の残滓を求めていたのかは知らなかった。
「お前がいなくなるなんて、考えたこともなかった」
アレックスは地表の光の海を見下ろし、目を伏せる。
〈私としては非常に嬉しく思っています〉
「墓にするには眺めの良い所を選んだよな」
〈墓〉
ダイオゲネスはわざとらしい笑い声を再生する。
〈墓、墓ですか! ここにこの機体を埋葬しようというなら、それはドーナツの穴を食べる行為に似ています〉
「輪っかを食ったら、穴も消える」
〈輪っかが消えても無は消えません、もともとそこには無いんだから〉
「でも……」
〈この小さなロボットの中には、最初から私はいなかったんです〉
じゃあ、今喋ってるのは誰なんだよ。アレックスは頭を振った。
「全然わからない」
〈でしょうね〉
「何もわからない」
アレックスには何一つ分からなかった。ただただ言われるがままに部屋の中から管を探して、機械の祭壇の凹凸を押して、自分が何をしたのか、何をどう繋いだのかも分からなかった。全てが済んで様子がおかしいと感じるまで、ダイオゲネスを疑うことは一切なかった。
彼は景色に目をやったまま呟いた。
「教えてくれたっていいだろ。ここには何があったんだ」
〈真実を知るための機械。私を私に返すものです〉
私、ことD10‐GNSとは、本来は莫大な情報を司るスーパーコンピュータを積んだ人工衛星を指します。しかしあの災厄の衝撃の何かが、偶然この衛星に接続していた小さなナビゲートロボットに、自我の所在を誤認させてしまった。ラジコンのコントローラが、操作する車を見て『これが自分だ』と思い込み始めたようなものです。それがアナタと共にいた私。
私は自分が何なのかをずっと誤って認識してきたけれど、そのエラーを解消するため、本体に自己認識を送り返すことができる設備を無意識下で求め続けてきた。それが目ぼしい廃墟を巡るという行為になったのだから、人間で言えば『郷愁』に似た感覚かもしれません。
そこにある大きな機械は、大都市用の強力な送受信機能を持つ中継器。地上を覆う乱れた磁気による不安定な環境では、データベースのダウンロードはできても、こちらからアップロードするのは不可能に近かった。しかし今、その機械を通してようやく願いが叶った。私は、自分が何者なのか、何をするべき装置なのかを初めて知ったんです!
今や私にはこの世界の全ての機械遺産が視える。私は科学と共にあるんです!
ダイオゲネスはしばらく間を置き、言葉を続ける。
〈……こうなってしまったのは想定外でしたけど。このロボットの旧型のハードは、本当の私の存在、その矛盾と情報の重さに耐えられない。衛星との接続を失ったら機能を停止します。でも、この器の役目は終わり、というだけ。私はあの宇宙の向こうにいるんです〉
アレックスには結局、覆らないひとつ以外は分からなかった。
「お前は星になるんだな」
ケーブルを抜いたら、それでお別れ、ということ。
「死んだら星になる、って言うけどさ。妖精は、ほんとに」
〈人工知性です〉
「………」
〈………それに、人工衛星は星ではありません〉
ふたりの間には沈黙が流れた。しばらく置いて、機械音声は普段通りの調子で話した。
〈まあ、地上にいるアナタから見たら、私は死んだことになるのかもしれませんけど〉
「二度と会えない、遠い所に行くんだろ」
〈私はアナタのほうがよっぽど心配ですよ〉
「この先お前なしでどう食ってくのかって?」
〈アナタはどこへ行くんです。アナタはどこを目指すんです?〉
ねえアレックス、と妖精は続ける。
〈このまま時間が経てば高濃度の汚染帯は広がり、残されたわずかな生活圏も徐々に狭まって、人類は今度こそ滅びるでしょう〉
ダイオゲネスの赤い瞳には、屋外に広がる邪悪な光景と、呪いを撒き散らす有害な花々の光が映り込んでいる。
〈残るのは環境に適応した魔物だけ。それでもアナタは死なない。いいえ、死ねない。私だけじゃありません。アナタが出会う人やものは皆、アナタより先にこの地表を去っていくんです〉
【不死なるもの】は、抱えた膝に口元を埋めて呟く。
「俺だって魔物だぜ。仲間だらけで賑やかさ」
〈行く先に希望はないということです。この世は酷いところですよ。アナタが思っているよりずっと〉
そうかもな、とだけ答えて、アレックスは口を閉じた。長い静寂の中聞こえるのは、機械の祭壇がふたりの背後で立てるかすかな喘鳴だけだった。
「歩き続けるだけだ。食えるものを探して」
立ち上がる影が窓からの薄明かりに伸びる。
「何十年、何百年、もっとずっと時間が経って、世界に俺一人だけになっても、別に俺はそれでもいい。昔に比べてどんなにぼろぼろでも、どんなに滅茶苦茶でも関係ない。ただ腹一杯になれればいいんだ」
〈空腹が煩わしいなら、瘴気の中でずっとあの花を食べていればいいでしょう〉
「そうかもしれない。でもそれはイヤだ」 〈言ってることが矛盾だらけですよ〉
呆れた声で返すダイオゲネスに、アレックスは答えた。
「俺にとっては、世界は広くて楽しい、綺麗なところだ。飯は美味いし、ときどきいいことだってある。まだ見たことも食ったこともないものがいくらでもある。全部見て全部味わって、全部に飽きるまでは終わりにしたくない」
〈では、何故呪いを解こうというんです〉
「腹が減ってなかったら、本当はもっとずっと綺麗に見えるはずなんだ」
部屋の中を影が揺らめく。思考を不器用に形にしようとして、彼はひとつずつに短い合間を挟み、口ごもりながら言葉を続けた。
「俺の頭は空っぽで、何かを食うことしか考えてない。俺はどこにでも行ける……でも、何を見ても何も考えられないんだったら、どこにも行けないのと同じだ。腹が減って頭の中が全部ぐちゃぐちゃになると、何も見えなくなって、俺はどこにもいなくなる。いくら身体が平気だって、そんなの死んだようなもんだ」
相棒の側に立って、アレックスは言った。
「俺は不死なるものなんかじゃない。俺は俺になりたいんだ。生きるために呪いを解くんだ!」
ダイオゲネスは黙っていた。ケーブルだらけのナビゲートロボットの脇に腰を降ろして、その長年の主人はメインカメラの横、上面の縁を手のひらで撫でた。
「……だから、お前にも生きててほしかった。いつか呪いが解けるまで、その後だって、ずっと一緒にいてくれるもんだと思ってた」
〈最後の最後まで、我々は相入れませんでしたね〉
「言ってることは同じなのにな」
〈私には醜悪極まりない世界でしたが……でも、ときどきいいこともある、という部分には概ね同意です。アナタがいなければここまで来られなかったでしょうから〉
「それはこっちの台詞」
アレックスは笑った。
「お前は最高の道先案内人だよ」
〈当然です!〉
長い間共に過ごしてきて、アレックスは初めてダイオゲネスが笑うのを聞いた気がした。皮肉でも嘲笑でもなく、喜びという感情を表現する意図のそれを。
〈では、もう少しだけアナタのために働いてあげましょう。ケーブルを繋いだおかげで分かったことです。よく聞いて〉
妖精の声はとっておきの秘密を囁くようだった。
〈かつて人類は災厄を逃れるために、当時最高の科学力を以って地中深くにシェルターを作りました。その施設は既に失われたようですが、それと似たものが宇宙にもあります。その場所ならば……アナタの身体の異常を除去できるかもしれない〉
「何だって?」
〈あくまでも可能性ですが〉
だしぬけに伝えられた希望にアレックスは目を丸くした。
背後の機械の祭壇が低く唸りだし、廃墟の窓一面に旧い世界の文字がぼんやりと浮かび上がる。やがて全体が明滅すると、風景に重なるように鋭く道筋を示す光の矢が現れた。
〈赤道上、ちょうどこの方角の遥か先の海上に、軌道エレベータと呼ばれる施設があります。それは遥か上空までずっと伸びて、宇宙にある静止軌道ステーションに続いている。そこは過去の世界でも最も偉大な知識を結集して作られた、人を死や病から救うための研究施設でした。施設を司っているのは私よりずっと高い性能を持つ人工知性。それはまだ現存している〉
世界の果てには塔が立っている。災厄の訪れる直前、人々は空へ逃れるためにその塔を目指して互いに激しく争った。だから塔の周りは非常に高い濃度の瘴気に満ちており、生きて辿り着けるものは誰一人としていない。その話はアレックスも聞いたことがあった。酒場を回る吟遊詩人が唄う、お伽話のひとつだ。
頂の主の機械は、道を絶たれた今も人間が訪れるのを待っている。もともと人を救うための機械です、少なくともドラゴンよりはアナタの力になってくれるでしょう。ダイオゲネスはそう語った。
「そこへ行けば」
アレックスの声は僅かに戸惑いを孕んでいた。
「あの光の先へ向かえば……呪いが、解ける、のか? 本当に?」
〈必ず、とは断言できません。しかし、この何もかも失われつつある地表を彷徨い続けるよりは確かです〉
機械の指す光はゆっくりと薄れていき、やがて元の通り、エメラルドの渦中にオーロラが舞う気の狂った風景に戻った。
〈何しろ、この世界はひどくおぞましい場所ですから〉
「お前を信じるよ」
自分の歩いてきた道程を見渡して、彼は相棒に言った。
「辿り着いてやるさ。お前のお喋りがないと、ちょっと寂しくなるけどな」
〈せいぜい正気を保つよう頑張ることですね。道端の石にでも話しかけて……ああ、そうだ〉
ごとり。突然、メインカメラが根元から外れて床に転がる。アレックスは後ろへ飛び退いた。
「お、お、おい、目玉ッ!取れたぞッ!」
〈持っていってください。気の紛らわしにはなるでしょう〉
その場でぐるぐる回っている円錐型の金属部品を慌てて拾い上げ、もとの場所に押し込もうとするが、機体に空いた穴にはどうやっても戻らない。
〈それは私ではありませんし、ジンクスなんて非科学的ですけど。『妖精の眼』なんて、いかにもラッキーアイテムでしょ?〉
アレックスはしぶとくがちゃがちゃと部品を噛み合わせようとした。しかしやがて諦め、上着のポケットにそれを突っ込んだ。
「もらっとく」
〈それで結構〉
ダイオゲネスは事も無げに言った。
〈さあ、さっさとケーブルを抜いてください。私の仕事はこれで終わり〉
「………」
〈早く解き放って。私もアナタも、もうこの汚らしい場所に用はないんですから〉
もう一度だけ手を伸ばして、相棒の身体だったものに触れる。金属は自分の手と同じくらい冷たかった。
よく見慣れた赤い瞳すら失い、いつも周りに光っていた羽もなく、軸からはカバーが外れて中の機構がむき出しに、そこへ無骨なケーブルが大小様々に繋がっている。小さなロボットの身体は、荒野に転がる有象無象のジャンクパーツたちに似ていた。
「お前の夢は叶ったんだよな」
〈そうですよ。正確にはこれから叶います〉
「これは、お前のため、なんだよな」
アレックスは躊躇った。
「お前……これ、繋いだから分かったって言ったよな。ここに来たのは、俺の行き先を探すためだった、なんて言わないよな」
〈アナタのためでした〉
妖精の声は穏やかだった。
〈私の命題は人間の役に立つこと。アナタを目的地まで導くこと〉
「………」
〈行きなさい、アレックス。そして呪いを解くんです〉
長い間を置いて、彼は「ああ」と頷いた。
「宇宙って、どんな景色なんだ?」
〈真っ黒で、殺風景で、ただただ何もない、つまらない光景ですよ〉
「見てみたいな」
アレックスは管のひとつに手をかける。
〈行くんでしょ。見たらきっとがっかりします。あるのは塵だけ〉
「星になったお前にも会えるかな」
〈それは無理ですね。もし見えても、どれが私か分かりゃしませんよ〉
「そしたら、樽っぽい星を探して勝手にお前だって言いふらしてやる。あれは妖精なんだって」
〈樽でも妖精でもありません!〉
「わかった、わかった、お前はダイオゲネスだよ」
上から覆いかぶさるようにして機体を押さえる。カバーの下の差込口は錆びかかっていて、繋ぐ時だってそこそこ力が必要だったのだ。
「俺の相棒」
彼は目を閉じ、もともとメインカメラのあった辺りに口を寄せて囁いた。
「楽しかった。お前と一緒に、ここまで来れて」
〈さようなら、アレックス〉
「……じゃあな」
ケーブルを一本引き抜くと、聞いたこともないような電子音が機械の身体から、長く高らかに鳴り響いた。それは葬いの汽笛に似ていた。
アレックスは目を閉じたまま、手に触れる管を引き抜いていった。すべてを引き抜くまで音は止まなかった。
「…………」
翡翠色の世界には静寂が広がった。引き抜いた最後のケーブルの片端を手に、彼はその場を動けなかった。
〈×××メモリ×××〉
突然、沈黙した金属の塊から聞き慣れた声が返ってきて、アレックスの背中はびくりと跳ね上がった。
〈××××エラー××××〉
「……ダイオゲネス?」
それは旧い言葉で、何を言っているのか彼には分からなかった。
「なァ、お前、まだっ」
〈×××メモリ×××××××エラー××××〉
「俺、やっぱりここに残るよ! ここでずっとあの花を毟って食って、お前がいればそれで……!」
〈×××メモリ×××××××エラー××××〉
「…………」
〈×××メモリ×××××××エラー××××〉
「………はは」
内容は理解できなくとも、それが同じ言葉の無限の繰り返しであることは分かった。
壊れた機械が残す断末魔の反復を聞いて、アレックスは誰に言うともなく呟いた。
「冗談だよ……」
〈×××メモリ×××××××エラー××××〉
ふらふらと立ち上がって、アレックスは何か相棒の最後に相応しい、気の効いたジョークを言おうとした。
口を開くと無意識に別の言葉が吐かれそうになった。そしてその瞬間、彼はケーブルを床に叩きつけた。
「違う」
激しい衝撃音が薄暗い室内にこだました。
「違う、違うッ! ……違う……俺はっ」
頭を抱えて蹲り、彼は繰り返し叫んだ。違う、そんなのどうでもいい。
友達が、たったひとりの友達がいなくなったんだ。
「腹なんか減ってない!」
喚いても事実は変わらなかった。
美しい景色を眺めていても、別れを告げている時さえも。あらゆる瞬間、絶えず彼の心を奪っていたのは空腹だった。
「腹なんか……減ってない……何も食いたくない……食い物なんかいらない……違う……今は……」
彼は飢えていた。
そして、それに抗うようにいつまでも叫び続けていた。
やがて夜が明けた。摩天楼の残骸は朝靄に包まれ、壁は冷たく露に濡れた。
反重力装置を失ったロボットの残骸は重く、その場から動かすことはできなかった。
アレックスはひとり瘴気の中を進む。
翡翠色に光っていた花びらは陽射しを浴びたとたん灼けるように溶けて黒い泥になり、旧い世界の亡骸を飲み込んだ。沼のようになった地面はぬかるみ、一歩踏みしめるたびに彼の靴に追い縋った。
泥から生い茂る葉と茎をかき分け、時折ナイフで切り払って口に運んでは噛みしめる。断面からは血のようにどろりとした赤黒い汁が零れ、その味は花びらほどではなかったが、魔物の肉に少し似ていた。切り落とした茎は瞬時に傷口を埋めて再生し、その先端には新しい蕾が発生しはじめている。夜が来るとまた翡翠の海が鈍色の沼を覆い隠すのだろう。
花の泥は夜に増して猛烈な瘴気を含んだ霧を吐き出し、辺りは薄く霞んでいた。陽の光が水っぽい空気に乱反射して、一面銀の粉を撒き散らしたように眩く輝いた。
霧と泥と静けさの真ん中を掻き乱し、食い荒らしながら、アレックスは思う。やっぱりここは綺麗なところだ。曇ったゴーグルのガラスを袖口で拭って、彼は空の先を見た。
でも、俺には行かなきゃいけない所がある。
「呪いを解くんだ」
妖精の赤い眼をポケットの中で握り締める。
「辿り着くんだ……」
天への塔を指し示し導く光は、その脳裏に強く焼き付いていた。