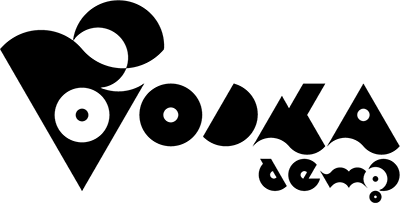〈バカは死ななきゃ治らない〉
ダイオゲネスは自分のデータベースの中から、今の状況に相応しい諺を導き出して呟いた。
〈昔からそういう格言があります。そんなに落ち込まなくてもいいですよ、アレックス〉
「言われなくてもさっさと出るっての!」
目の前に空いた直径一・二メートル程度、大人一人分の背丈ほどの深さの穴の底から返事が返ってくる。
ダイオゲネスが下を覗き込むと、落とし穴の中には先端を竹槍状に尖らせたビニールパイプがいくつも天に向けて穂先を光らせており、仰向けに串刺しになったアレックスが、泳げない人間の水泳よろしく手足をばたつかせてもがいていた。
沈みかけた夕日に照らされて禍々しい赤紫と橙色の入り混じった霞が、穴の中の湿気った闇を一層深くする。
辺りにはかつては小さな町だったであろう瓦礫の山々が、僅かに以前の様相を残す、ひび割れたアスファルトの道沿いに点々と並んでいる。道路の亡骸を辿って歩いていたふたりは、その脇に不意に捨て置かれた大量の菓子の箱を見つけたのだった。
〈どう考えてもおかしいって言ったでしょ。こんな罠にひっかかるアナタもアナタですが、仕掛ける側もどうかしてますよ。トゥインキーにつられて落とし穴にハマるなんて〉
「反省はしてる」
ダイオゲネスが止めるよりも早く飛びつこうとした結果がこの有様だ。
肩を引き抜こうとすると腰が沈み、腰を上げようとすると腿に重心がかかる。暴れるほどにパイプの槍は深く彼の身体に突き刺さるが、そんなことはどうでもいいと言わんばかりにアレックスは声を張り上げて、相棒に尋ねた。
「で、トゥインキーは!?」
〈驚くべきことに〉
ちょうど呼び声に答えるように風が吹き、菓子の箱からはみ出した包みの袋がひとつかさかさと転がって、穴の中に飛び込んだ。
〈空ですよ。全部〉
ビニールの小さな空包みはひらひらと穴の中を漂って、串刺しのアレックスの鼻先へ、蝶のように舞い降りる。
もがくのを止めた彼は首を起こしてばくり、と包みを口の中に捕まえたが、ビニールの味を確かめると気力無さげに吐き出した。
「一個くらい残ってないか? 箱の中全部見た? ほんとに空?」
〈自分で調べたらどうですか。さっさと出てきてくださいよ〉
ダイオゲネスは後方の、山と積まれた菓子の箱を顧みる。
菓子の空包みなんかで釣れるのは魔物ではなく人間だ。明らかに人が人を獲るための狩りの様相。罠の主については概ね見当がついていた。この破滅に満たされた世で、人間が生き抜くための物資を最も蓄えているのは同じ人間だ。人からものを奪って生き抜く方法を選んだ荒くれ者たちのことを、野盗と呼ぶ。
狡猾な彼らは徒党を組んで人狩りを行う。キャラバンや旅人を獲物とし、時には軍団を率いて街を襲っては日々を凌いでいる。
〈おそらく仕掛けた主が獲物を回収にきます。夜になる前に抜け出さないと、ロクな目に遭いませんよ〉
「くそっ、ふざけた罠作りやがって! 食い物の恨みはでかいぞ!」
急かされて再びひとしきりもがいた後、アレックスは結論を出した。
「……なァ樽、これ、俺一人で出るの無理だ」
〈だったらそこにずっとひっくり返っているつもりですか?私には手も足も出ませんからね〉
「いや、いいこと考えた。奴らに出してもらおう。お前はどっかに隠れてろ」
〈……命乞いでもするんですか? 元々命もないですけど〉
「あいつらもないと思ってるだろ、多分」
そう時間も経たないうちに、車が二台、道を辿ってやってきた。この世界の人々が『砂河馬』と呼ぶ、機関銃で武装した大きな四輪駆動のバギーだ。車内から身を乗り出すことができる砂河馬は、野盗が特に好んで選ぶ車でもある。
現れたのは全身を分厚い鎧で包み、奇妙な筒の生えた仮面を被った大男が四人。ダイオゲネスはそれがパワードスーツとガスマスクであることを知っていたが、わざわざ声に出して説明することもないだろうと黙っていた。
ひとりは両手で抱えるような厳つい銃を構えながら、後に続くふたりはそれぞれ大きな麻袋と、先が鉤針になった長い棒を手に穴の縁に立つ。最後のひとりは離れたところに停めた砂河馬の機関銃に手を置き、車を守りながら様子を伺っている。
互いに言葉を交わすこともなく、大男たちは慣れた様子で穴を覗き込んだ。仰向けに串刺しになった若い男の死体がひとつ。鉤針棒を持った大男が自分の道具を伸ばし、獲物の背中に鉤を噛ませる。着込んだ鎧が着用者の筋力を底上げしているためか、元々の怪力のためか、死体はいとも簡単に穴の中から引き上げられた。
槍によって塞がれていた無数の傷口から、どろどろと赤黒い血が流れ出す。大男は僅かに首を傾げた。罠にかかってからそう時間が経ったようには見えないが、いつもはもっと勢いよく噴き出すものだ……鉤から離されて穴の縁に置かれたその死体が身体を飛び起こす瞬間まで、大男は違和感に囚われていた。彼は死体から不意の体当たりを受けて足を滑らせ、声を上げる間もなく穴の底で串刺しになった。長い鉤針棒だけが穴の縁の枯れた地面に残された。
闇に包まれかけた辺りの空気を、自動小銃の放つ閃光が激しく瞬かせる。雷の轟くような音とともにアレックスの身体は糸のもつれた操り人形の如く踊り上がり、映写機の中の喜劇のように照らされて、銃弾に吹き飛ばされた肉片が飛び散る。引鉄が離されて一呼吸、しかし彼は二本の足で地面に立っている。
身体を沈めて太腿のホルスターから逆手にナイフを引き抜き、自動小銃を持った大男の元へ、獣が駆けるような姿勢で懐へ飛び込む。鎧の隙間を縫って喉元に突き立てられたナイフを、大男はあと数ミリ、というところで腕を掴んで止める。ぎりぎりとお互いの腕に込められた力が均衡を保って震え、アレックスの身体の全身から滴る赤黒い血が、大男の鎧を伝う。
一瞬の隙にアレックスの左腕がもう一本のナイフを抜いて相手の脇腹を深く突き刺し、それに一歩遅れて、掴まれていた彼の右腕はナイフを握ったまま大男によって引き千切られた。
麻袋を持っていた大男は背負っていた自動小銃を構え、片腕のない敵に向かって銃弾を撒き散らす。アレックスは舌打ちして地面を転がり、手負いの相手にとどめを刺すのを諦めて距離を置く。
「俺は人は食わねェんだ。アンタらとやりあっても腹が減るだけだ」
瓦礫の小山を間に挟み、刺されて片膝をつく大男、それを庇うように銃を構えて牽制するもう一人と睨み合いながら、アレックスは呟く。
肩口から先の失くなった右腕の断面からは粘度の高い血がぼたぼたと地面に零れる。串刺しだった上に銃弾を全身に浴びた身体もあちこち穴だらけで表層が剥がれ、所々から肉や中身の柔らかく曖昧な臓物が、体液を滴らせながら覗いている。
「でもトゥインキーの恨みは晴らす!」
にわかに目を見開き、歯を食いしばる。腕の断面から細長い触手のような血塗れの肉組織が枝分かれして伸び、水気を求めるミミズに似てのたうちながら宙を泳ぐ。脈打つ血管がそれを追いかけるように断面から無数に溢れ出し、互いに絡み合いながら膨らんで、歪で青ざめた肉塊に変わる。身体中の傷口が同じように血の気の引いたどす黒い肉組織で覆われ、失われた右腕は皮膚を丸ごと剥がしたような見た目で、しかし概ね元通りの形を留めて再生した。
その目を背けたくなるような様相は、【不死なるもの】の二つ名そのものだった。
離れた物陰で様子を伺っていたダイオゲネスは、自分が呼吸する知性体であればここは溜息をつくところだ、とひとり呆れていた。
〈何の利益があるっていうんです〉
ただの死体だと思われていたのだから、わざわざあのタイミングで仕掛けなくとも、彼らの去った後に起き上がればよかったものを。命を盗られる恐れがないのだから、野盗風情に何を奪われても構わないだろうに。
死体になってしまった人間に価値はないが、精密機械である自分が野盗に見つかれば、軽々と捕まってどこかへ売り捌かれてしまう。それを恐れてこうして身を隠しているが、やはり側にいて助言するべきだったか……と自分の判断を反芻した。
いや。音声で伝えても変わらないだろう。彼は不死身で、人間で、バカなのだ。人間は自他問わずものを傷つけずにはいられない哀れで愚かな存在で、バカは死ななきゃ治らない。
〈バーカバーカ。アレックスのバーカ〉
まだしばらく続くであろう喧騒を予測して、ダイオゲネスは決して耳には届かない最小の音量で直接的な悪態をついた。しかしナビゲートロボットの機能として、人に対するあからさまな悪口は非常に単純なもののみに制限されているのであった。
鎧の大男は声を上げた。地面に転がった事切れる寸前の蝉のような、短く耳に張り付くジジッ、という音。人の喉から出るにはいささか不快な、空気を締め付ける響き。脇を刺された男は地面を這いながら逃れ、銃を構えた男は後ずさりながら繰り返し喧しく蝉の声を鳴らす。ジジッ、ジジッ、ジジジッ。
ダイオゲネスは訝しむ。あの音、聞き覚えがある。
アレックスは再生した右腕にナイフを持ち替え、姿勢を低くして獣めいた足取りでじりじりと相手に躙り寄る。機会を見定めるように目を見開きながら、喉の奥からは唸り声が漏れる。
本人曰く、肉体の再生に際限はないが、『生やした分だけ腹が減る』のだ。飢えの波に蝕まれて遮光ゴーグルの向こうの瞳孔は開き、口元からは涎が零れている。
ジッ、という一際高い鳴き声と共に、辺りの空気が再び激しく明滅する。同時にアレックスも飛びかかる。まともに銃弾を浴びながらまるで意に介さず、不死の身体は肉片と血を撒き散らしながら大男を押し倒し、鎧と仮面の隙間の喉元に深々とナイフを突き立てる。男は声もなく事切れる。その傷口に大きく口を開いてかぶりつこうとしたアレックスは急ブレーキをかけたようにぴたりと動きを止め、首をぶんぶんと横に振った。
血濡れのナイフを引き抜き、くるりと手元で弧を描いて刃先を握る形に持ち替える。後ろに跳びのいて周囲を一瞥すると、手負いの男が地面に身を横たえたまま、構え直した自動小銃の引き金を引かんとしているのが視界に入った。次の瞬間、男の眉間には仮面を貫いてナイフが鋭く突き刺さっている。
ジッ、と一声上げて、どさりと男が崩れ落ちる。アレックスは口元の涎を左腕の袖で拭う。
誇り高き人工知性としては非科学的極まりないが、ダイオゲネスは悪寒を覚えた。
あれは言葉だ。旧い世界の軍人が使っていた、短い時間で効率的に意思疎通を測るための、非常にコンパクトな暗号めいた言語。翻訳するには時間がかかるが、人工衛星を介して接続しているデータベースの中の語彙が、一瞬だけ回路の中を過ぎる。
彼は今の自分が置かれた状況に気づいていない。
〈アレックス!!〉
ダイオゲネスは出来る限りの最大音量で警告するべく彼の名を呼んだが、同時に響き渡った奇妙な破裂音でその声はかき消された。
辺りに青白く鋭い光が閃き、周囲の空気が凍りつく。比喩ではなく実際に。
「!」
足元にまとわりつく白い煙が元々ない体温を奪っていくのを感じて、アレックスは思わず声を上げようとしたが、舌が動かない。頭が回らない。指先が動かない。血の気が引いて、視界が白と黒の世界に変わる。
ダイオゲネスは二つの言葉のどちらを続けるか瞬間的に思案したが、どちらも既に無駄だと判断し、再び物陰に身を潜めた。
『もうひとりいます』あるいは『フリーズグレネードです』。
災厄の日以前に作られた様々な武器の中でも、特に奇妙な魔法めいた兵器。周囲の空気を瞬間的に凍結させるこの冷凍弾は、興味本位で作られた実験的なものだった。人間を仕留めるのには熱かろうが寒かろうが関係ないのだ。敵の武装に備わった精密機械を結露で破壊する程度の役割しか持たなかったが、皮肉なことにこれが真価を発揮しだしたのは文明が滅びたあとだった。魔物は寒さに弱いのだ。もともと数が少なく貴重なこの武器は、今では権力者の備える軍隊か略奪者だけが持つ『聖なる手榴弾』と呼ばれている。
冷凍弾を投げた大男は、慎重に銃を構えながら、その場に膝をついているアレックスに近寄った。一歩、二歩、歩み寄り、銃の先で頭を小突く。
不意にその腕が跳ね上がって相手に掴みかかる。両腕で首を締め付ける。ぎりぎりと相手の息の根を止めようとするが、手に力が入らない。強く蹴り飛ばされて引き剥がされ、地面に転がる。
だからアナタはバカなんですよ、とダイオゲネスは無い腕で無い頭を抱えたい衝動にかられる。何でナイフ投げちゃったんですか。バカ、バカ、アレックスのバカ。
大男は地面に投げ捨てられた麻袋を拾い上げると、素早くアレックスの頭からそれを被せ、足先だけはみ出す形で彼を縛り上げてしまった。
砂河馬に荷を積んだ大男は、別の麻袋をいくつか引きずり出してくると、事切れたふたりの仲間を抱えて同じようにした。鉤針棒を伸ばし、穴の中で串刺しになったもう一人も引き上げて、血の吹き出すままに袋詰めにした。ついでに地面に残されたアレックスの右腕だったものも、ナイフを握ったそのままで、同じ袋に放り込んだ。
仲間の遺した銃を拾って助手席に立てかけ、乗り手のいなくなったもう一台を手際よく鎖で自分の車に縛り付けて牽引し、大男は何事も起こらなかったかのように悠々と砂河馬を走らせて去って行った。 後に残されたのは山と積まれたトゥインキーの空き箱と、暴かれた血まみれの落とし穴。その周囲に転々と広がる血溜まりはまだ冷たく凍りついている。
〈…………〉
そして主人を失った妖精。
〈……………………〉
ダイオゲネスは菓子の空き箱の山を精密スキャンする。当然、口に入れられるようなものは欠片も残されていなかった。
〈何の利益もありませんけど〉
大男たちの残した、蝉の鳴き声のような言葉を回路の中で反芻する。
誤訳であってほしいと願うところだが、データベースに誤りのある訳もなく、野盗が仲間の死体をわざわざ丁寧に持ち帰ったことからも明らかだった。『無限食材だ』、と叫んでいたのだ。聖手榴弾持ってこい、絶対逃すな、と。
そしてその意味合いによるところでは、アレックスはただの死体よりももっとおぞましい目に遭うだろう、という答えが導き出された。彼は不死身で、人間で、バカなのだ。おそらく落とし穴よりも抜け出せないところに閉じ込められるだろう。
〈別に、私には関係のないことですけど〉
ダイオゲネスは走り去った砂河馬のタイヤ痕を分析した。辿っていくのは造作もないことだ。
〈アナタがどうなろうと知ったこっちゃありませんけど。もともと手も足も出ませんけど。ちょっと言うの遅かったかな、とか、微塵も思ってませんけど。私のせいだなんて一欠片も思ってませんけど。心配なんてしてませんけど。どうせどんな目に遭っても死なないでしょうけど…………〉
誰にも聞こえないような音量でぶつぶつと囁きながら、ダイオゲネスは闇の中を漂って、可能な限り速度を上げて道沿いに進み始めた。