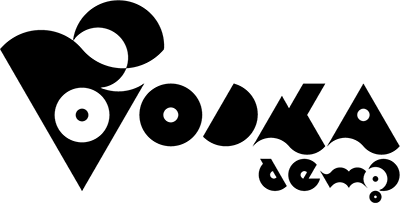「世の中、生きてりゃいいこともあるもんだな!」
目の前でぐつぐつと煮立つ大きな鍋に具材を放り込みながら、大男は喜びの声を上げた。
「もうあの砂糖の塊ばっかり食わなくていいんだ。肉、肉、肉だ、それも新鮮な!」
「少しはしおらしくしろ。同じ屋根の下で暮らした仲間が三人も死んでるんだ」
夜の帳の降りた暗闇の中、鍋の下で踊り上がる炎が二人の男の姿を照らし出す。二人のすぐ脇、かろうじて屋根と壁が残った石造りの廃墟の前には、機銃を積んだ二台の砂河馬が並んで繋がれている。ひとりは瓦礫の残骸から引っ張り出してきた歪んだ椅子に、もうひとりは小ぶりな岩に腰掛けて、これから夕食になるスープの鍋を囲んでいた。椅子と岩の横には、管のついた仮面と大振りの銃がいつでも手の届くように置かれている。
「それに、見た目がどうあれ、あれは魔物だ。普通に食ったら呪われて死ぬ」
もうひとりの大男はぼそぼそと用心深く話す。その声は自分自身に言い聞かせるような調子で、この世のもので信じられるものなど何一つないと言いたげだった。
「普通に食わなきゃいいんだろ。城の奴らだって魔物くらいちょっとは食ってる。ピンピンしてる」
一方、手際よく調理を続けている方の男は、たしなめられてわずかに声量を落としつつも、未だ興奮を抑えられないようだった。
「言い伝えにもある。臓物は避けて、青き聖水で祝福してから食えばいい」
「その聖水はどうするつもりなんだ。べらぼうに高価だろう」
「食い物以外に手に入らないものなんて何もない」
具材を全て鍋に突っ込み終わった男は、懐からすっかり食べ飽きた甘い菓子の空袋を覗かせて、歯を見せた。
「みんなこいつにうんざりしてる。誰だって肉と引き換えなら何でもよこすさ」
ふたりは野盗だった。
この小さな廃墟から西へしばらく離れたところに、軍勢を従える領主の城がある。そこは災厄の起きる前の世界では食べ物を生み出す工場だったと言われていて、千人が十年食べても尽きないような量の食物が、今も巨大な地下倉庫に眠っているという。領主は食料を求めて集う人々にそれを分け与え、引き換えに水、ありとあらゆる武器、武装、虎や馬や砂河馬などの車をかき集めてきた。そしてこの一帯に縄張りを持つ野盗たちは皆、城を目指す旅人を襲い、剥ぎ取った物品を城に持ち込んではその恵みを得るのだった。
ふたりの着る鎧や仮面も、武器も、後ろの砂河馬も、火にかかっている大きな鍋も、全て城の軍勢との取引で手に入れたものだった。同じような野盗たちと手を組み、道に罠を仕掛け、命を落とした間抜けな旅人から身包みを剥ぎ………
だが、この暮らしには一つだけ問題があった。
城の財を築く食料というのは、甘い甘いスポンジの中にもっと甘い油めいたクリームの入った、数百年経っても腐らない程に甘ったるい砂糖まみれの菓子なのだ。この辺りで手に入る安全な食べ物といえば、これが全てだった。
「そら、もう煮えた」
陽気な男は鍋に匙を突っ込み、器に掬ってもう一人に手渡した。
「何なら俺たち、近いうちにここの領主になれるかも」
「食って死ななきゃな」
「ひとまず、この肉は安心だろ?」
「毎日一緒に飯を食ってた奴を食うのも、妙な気分だ」
陰気な男が受け取った器の中には、食べやすい大きさに切り分けられた肉の塊がいくつも入っていた。
男はにわかに眉をしかめたが、よく火の通った新鮮な肉の味を噛み締めると、器の中身を一気に喉へかきこんだ。
「しかし、肉は旨い」
「明日からは毎日食えるぞ!」
もう長い事眠ったことがなかったアレックスは、強い空腹に目を覚ましてようやく、自分が気を失っていたことに気がついた。何か薬でも嗅がされたらしい。
口の中に自分の唾ではない、どろりとした液体がいる。あまり食欲を満たせそうな味ではない。吐き出そうとして、自分の頭の先から足の先まで全部がその生温い液体の中に浸かっていることに気がついた。目を開くと、流れ込むそれが眼球にまとわりつくと同時に、水の向こうから光が彼の目を刺した。眩しいが、水面は近い。上下の瞼を強く閉じ合わせて、腕と足を振ってもがこうとする。
そうして二つ分かったことがあった。ひとつ、重力が背中の側にある。もうひとつ、自分の両足の膝から先がどうやら無くなっている。
彼は無理矢理に身体を水面の向こう側に突っ込んだ。水の溢れる音とともに、肩から先が空気に曝されるのを感じる。幸いにも辺りは薄暗く、光に弱い彼でも薄目を開けて視認できる程度の光量だった。
周囲を見回す。ぼんやりとしか見えないが、動くものは何もない。
小さな蝋燭(ダイオゲネスはこれを見るたびに〈LEDライトを『蝋燭』と呼ぶなんて、電気への冒涜です……〉と嘆いていた)がひとつだけ壁にかかった、石造りの青白い部屋だ。
窓はひとつもないが、重そうな鋼鉄の扉がひとつ部屋の隅にある。彼の身体は棺桶を深くしたような銀色の四角い器に溜まった、目を見張るほど真っ青な水に浸されていた。薬っぽくてダイオゲネスが喜びそうな、食えない匂いがする。
そうそう、野盗にケンカを売ったんだった。アレックスはこれまでの経緯を思い出す。服は身包み剥がれているし、当然ゴーグルも、ナイフもどこにもない。身体に巻いていた包帯だけは、端からほどかれつつも中途半端に残されている。多分途中でめんどくさくなったのだろう。
近くに相棒の姿はない。胸の真ん中に嫌な気分が漂う。何しろ相手は盗賊で、金目のものなら何でも獲物にする奴らだ。不安になって名前を呼ぼうとすると肺に入った水が口から零れだし、アレックスはごほごほと咳き込んだ。息をするのはとっくの昔にやめているが、呼吸の真似事は身体が勝手に続けている。
随分と短くされてしまった足を薄目で見つつ、何とか水の溜まったこの棺桶から出ようとして、彼はむしろ身体に知らない装飾品が追加されていることに気がついた。鉄でできた首輪と、左右それぞれの手首に嵌められた手枷だ。互いに重く短い鎖で繋がれ、さらにその先は棺桶の脇に伸びて金具で固定されていた。青い水の中をよく見ると、役目を果たしていない足枷も水底に沈んでいる。
ひとしきり暴れてみたが、水に浸かった身体は思い通りに動かず、首と手の鎖に繋がった金具も非常に頑丈で、引っ張ってもびくともしない。棺桶自体も水の重みのせいか底が床にくっついているのか、体重をかけても倒れる気配はない。足がいつも通りの長さでも、状況は大して変わらないだろう。むしろ生やせば腹が減る。
面倒なことになっちまったな、と唇を噛んでいると、不意に隅の扉が重い音を立てて開いた。
ジジッ、と例の耳障りな声が聞こえる。入ってきたのは鎧を着込んで仮面を被った二人の大男。
ひとりは水から身を起こしたアレックスを見て動揺した様子だったが、後ろに立っている方が諌めたようだった。大男は何か大きな機械を抱えて、棺桶に注意深く近づく。
「ずいぶん洒落てるベッドだよな。これで朝飯もついてれば……、……ッ」
ジョークを言う暇もなく頭を押さえつけられ、顔から水に沈められる。身体が無い命の危険を察して肺を震わせ、ごぼごぼと泡を吐く。強い力で抑え付けられながら、手首を掴まれて枷を外され、左腕だけを水面から背中側に引き伸ばされる感覚。水の中でもがこうとするが、とても抵抗できるような体勢ではない。
凄まじい轟音が水の上から聞こえて、左の肩口から先が突然強い衝撃とともに感覚を失う。真っ青な水の中に、大量の赤黒い液体が溢れ出し、インクを零したように水底に沈んで混じり合う。舌の上に僅かにその味を感じて、思考が一瞬ぐちゃぐちゃに乱される。押し寄せる飢えの波。
身体が自由になると同時に彼は勢いよく頭を水から上げて、だいたい想像したのと同じような光景を目の当たりにした。大男のひとりは血塗れの大きな機械を抱え、もうひとりはアレックスの切り離された左腕を棺桶でよく洗って、青い水を汲んだ蓋のない一斗缶に突っ込むところだった。青白い部屋の辺り一面に暗い色の血飛沫が飛び散っている。
ダイオゲネスが何と言うかは知らないが、あの機械は泣く子も黙る『神殺し』というやつだ。細長いベルトについた刃が機械の力で高速で回転し、その異名の通り荒神すらもばらばらにするという。痛みを感じない身体でよかった、とアレックスは思うが、切断された肩口の断面には不快な感覚を覚える。咳が止まらず声はろくに出ないが、唸り声を上げてこの状況に抗議した。引っ張った鎖が擦れて、鈍く重い音を立てる。
機械を抱えていた大男はそれを傾いた机の上に置いて、ぼろ布で神経質に血を拭きとっている。もうひとりは一斗缶の中の腕とアレックスを交互に見つめていたが、仲間の背中を小突き、ジジッ、ジッと何か話しかける。ジジジッ。抱えられていた缶は床に降ろされ、中の青い水がばしゃ、と溢れる。 棺桶から一歩離れたところで、男は鎧の腰に下げていた皮袋の中から、けばけばしい色の包みを取り出した。見覚えのある小さな袋。太い指でがさがさと音を立てて封を切る。
気分も真っ青に落ち込むような化学的な刺激臭と血飛沫の部屋に、だしぬけに解き放たれる甘い香り。頭の奥に直に微笑みかける芳しいお菓子の匂い。大男が鼻先に突き出してきたトゥインキーの軌跡は、アレックスには闇夜の流れ星よりも煌々と輝いて見えた。目の中で火花が散り、考えるよりも先に全身が飛びかかって迎えに行こうとする。しかし、棺桶に繋がれた首輪と手枷の鎖がその衝動を阻んだ。
ちょうどトゥインキーひとつ分足りない距離で、歯と歯が噛み合い何度も宙で音を立てる。届かない、届かない、届かない。頭のものを考える部分に食欲が古い油に似てまとわりつく。火を飲んだような感情が彼の腹の底から湧き上がり、枷のない、無いほうの腕が目の前の食べ物を掴もうと伸びた。まだ血の滴る断面から溢れ出す無数の血管と肉組織が絡まり合い、一瞬で人の手の形を編み上げて、トゥインキーを掴………めなかった。大男がもう片方の腕で、彼の新しい手首を捕らえた。『神殺し』の刃が立てる轟音が、再び青白い部屋に響く。トゥインキーは大男の仮面の隙間から、その口の中に消えた。
自分の腕が再び手際よく刈り取られていく間、アレックスはずっと未練がましく喚いていた。忌々しい菓子の空包みは床に落ち、血溜まりと青い水の混じったものの上に浮いていた。事が済んで棺桶の中に押し込まれ、金物の重い蓋で閉じ込められるまで、彼はいつまでも目を離せなかった。
日の暮れかかった中、朽ちた街の残骸に挟まれた道を、一台の砂河馬が走り抜けていく。
「本当に領主になれちまうかもな」
ふたりは城から自分たちの棲家へ戻るところだった。
手綱を握る大男は顔を綻ばせていた。荷には新しい銃、新しい鍋、物々交換で手にした様々な嗜好品がくくりつけられている。足の間には色褪せたエメラルドグリーンをした、古びた大きなプラボトル。中にはなみなみと聖水の原液が入っていて、これを雨水で希釈して使う。あの棺桶の中にひとすくい溶かしても真っ青に染まるのだから、しばらくはこれで保つだろう。
「財ってのは、持つべきものの所に集まるんだなあ」
人々は皆飢えている。刈り取って持ち込めば持ち込むだけ、いくらでも買い手がついた。味は人の肉そのものだ。たとえ薬の匂いのする青ざめた腕や足でも、干し肉にしてしまえば誰も気にしなかった。
「そしていつか尽きるもんだ。食い物も、金も、弾も、命も」
もうひとりの男は双眼鏡を覗きながら呟いた。助手席で山ほど積まれた荷に挟まれて、砂河馬が巻き起こす砂塵の向こうを見張っている。
「この世に無限なんてもんはない。次の商売も考えておいたほうがいいさ」
「わざわざ水換え用の道具まで買ってきたのに?俺は他の奴らに盗られる方が怖いね!」
「今のところ目をつけられてる気配はない。用心に越したことはないが」
新調した火力の高い銃に手をかけながら、荒地にぼろぼろの建物が並ぶ平野をくまなく見渡す。城の周りに広がっている掘っ建て小屋の立ち並んだ商い所が、進行方向の逆、まだわずかに遠く砂煙の向こうに見えている。陰気な男は野盗であることを隠して慎重に商人たちに取り入り、この取引を成立させてきた。運の良いことに、つい最近東の大きな集落が魔物の群に襲われて滅びたばかりだった。そこから運んできた死体だという話を作って肉の出所を隠したのだ。無限に食える肉を見つけたなどと明らかになろうものなら、菓子で人々を従える城の軍勢が全て敵となるだろう。
「それより俺は、最初の頃より収穫できる間隔が開いてきたのが気になってる」
「菓子で釣れなくなってきたもんな。全く面倒だ」
「がらくた屋がいいものを隠してた。これを試したい」
助手席の男は荷の中を探り、鮮やかな黄色の瓶を掴み取って顔の前に掲げた。もう片方の手には同じような赤い瓶。運転席の男はそれを一瞥して首を傾げる。瓶はどちらも不透明のプラ製で、中身が液体らしいことしか伺えない。
「聖水屋さんでも始めようってのかね」
「お互いを混ぜると瘴気が吹き出す薬だ」
運転席の男はそれを聞いて、目を剥き息を止めた。ひび割れた道の上で砂河馬がにわかに蛇行し、荷物ががたがたと揺れる。
「今すぐ捨てろ!街ひとつ滅ぼすつもりかよ!」
災厄の日以来、世界には呪いが蔓延り、人間が住めるような場所は元々の面積から比べて猫の額ほどに縮小してしまったという。何よりも恐ろしいのは『瘴気』と呼ばれる、呪いそのものが凝り固まったような空気の層だ。一息でもそれを吸えばたちまち事切れてしまうので、人々は決して近づかない。
「落ち着け。混ぜなければ何も起きない」
「何に使うんだよ、そんな物」
「魔物は呪われ方に応じて身体の再生も速くなるらしい。瘴気に満ちた世界の果てから這いずり出てきた怪物は、八つ裂きにしようが細切れにしようがお構いなしって話だ。八つに裂けば八匹になるって噂もある」
「なるほど、確かに、まあ………試してみる価値はあるかもな」
ゆっくりと姿勢を直し、手綱を握りなおす男の額は、噴き出した汗に濡れている。助手席の男はそれを鼻で笑いながら、ふたつの瓶をぞんざいに、荷物の山の中に突っ込んだ。
「そう怯えるな。こんな量の薬で作れるのは、風が吹けば消えちまうような瘴気だけだそうだ。呪いを防ぐって折り紙つきの装備も用意してある。あとはこの肥料が俺たちの家庭菜園にどう効くか、水の中に混ぜて様子を見るとしよう」
「なあ、知識人ってのは恐ろしい事考えるもんだな」
「こんな世の中だ。生き延びるのは賢い奴だけなのさ」
双眼鏡を構え直して再び砂煙の向こうを覗きながら、男は懐から青みがかった干し肉を取り出して、齧り出した。
「それにしても、頭を使うと腹が減る」
薄暗がりで火を囲む、砂に汚れて日に焼けた人々の満面の笑み。廃材で出来た小屋の陰で、夜風に吹かれながら眺める遠方の稲光。派手な服をはだけさせた、化粧した女の潤んだ瞳。咳をする襤褸を着た子供と、その怯えた目。火にかかった鍋。燻る熾。
瞼を閉じているはずなのに、見覚えのない、とりとめもない風景が見える。これが夢っていうやつか。アレックスは水の中で思った。棺桶を閉じる重い金属の蓋は、内側からどれだけ蹴り飛ばしても、全身で押してもびくともしなかった。水は血で汚れるたびに入れ換えられたが、底に栓があるわけでもなく、中に閉じ込められている彼にはどこに隙間があるのかまるで見えなかった。この蓋が開くのはあの『神殺し』の轟音が鳴る時だけだ。
元々傷ついた身体は放っておくと自然に再生したが、促すことはできても、自分でそれを止めることはできなかった。しかし、自分の意志でなければごくゆっくりと、長い時間のかかるものだったはずだ。ここに連れてこられたのがもうどれ位前の事なのかすらわからないが、状況はさらに酷くなった。切り落とされた手足が、自分でも驚くほどに素早く生え揃うようになった。まるで瘴気のそばにいる時みたいだ。最初は水中に長い間閉じ込められているせいで時間の感覚が狂ってしまったのかと思ったが、刈り取りにくるあの野盗たちの様子を見る限りそうではないらしい。おそらく彼らが何か手を加えたのだろう。
野盗たちは必ず片腕、片足を残してアレックスの手足を刈った。常にどちらか片側の枷が棺桶の中に残るように、中ですべての四肢が再生しても逃げ出せないようにという考えだ。
水以外に何でもいいから口に入れたくて、枷のかかった自分の手首に噛み付いてみたりもした。このまま食い千切れば逃げ出せるかも。そう思って齧り続けても、噛み傷はすぐに再生してしまう。何より後味が最悪だった。魔物の肉だと思い込もうと目をきつく閉じても、半分は人の味がする。自分のとはいえ、とても食えたものではなかった。
日に日に自分の頭の中が霞みがかったように曇っていくのが分かった。腹が減って仕方がない。アレックスは首を振った。違う。腹が、減らない。何日も何日も何も口にしなかった時の感覚は、記憶にはないが身体が覚えている。自分の奥底から湧き上がるような激しい飢餓の叫びは、油に伝う炎のようにたびたび彼の意識を焼いた。今は違う。身を焦がすような空腹の渦はそのままに、気を狂わせられるほど飢えられないのだ。
狂気は水の中か夢の中か、どこか遠くに溶けて薄れてしまう。真綿で締められるように曖昧な感覚は彼をじわじわと、しかし確実に嬲り犯した。濁った意識を覚まさせるという点で、『神殺し』の刃が与える刺激はむしろ好ましくすら思えた。水を震わせる轟音。棺桶の蓋が開く。手を引かれ、なすがままに身を預ける。
ジッ。
「なんだよ、それ」
自分の肩口から先が切り落とされていくのをぼーっと見ていると、耳元で声が聞こえた。
ジジッ。
「試す。しっかり固定しろ」
既に血管が根本を編み上げようとしている傷口に、大男の手で銀色の平たい金具が食い込むように差し込まれた。金具には細い鎖紐がついていて、外れないよう身体を斜めに通すような形で固く結び付けられる。そのまま再び棺桶の中に戻されたアレックスは、ろくに回らない頭で聞こえた言葉を反芻した。試す? 何を?
金具を眺めていると、その答えはそう遠からずやってきた。早回しで成長する樹木のように血管が伸び、糸状の細いなにかが絡み合った。中心に骨が現れ、それを軸に肉が編み上がっていく。アレックスは水の中で思わず声を上げ、吸ったばかりの空気が肺から溢れて音を立てた。軸になるはずの骨は腕の断面の真ん中を遮るように通った金具に当たり、左右へ枝分かれした。あとに続いて絡み合う赤黒い肉組織も分かれた道に続いて繋がっていく。水の中で何を叫ぼうとも吐き出されるのは泡ばかりで、再生が止まることはなかった。彼の腕は歪に分かれて三本になった。
ジジジッ。
「挿し木と同じようなもんさ。うまくいったら商売繁盛。だろ?」
ジッ。
「俺はお前の頭の切れ方が怖いよ」
彼らの試みはとてもうまくいった。同じ事を繰り返して、これまでの六倍も収穫が増やせたのだ。
何日か経って、アレックスは瞼を開けるのをやめた。銀色の棺桶は青い水の中を鏡のように映し、幾重にも幾重にも枝分かれさせられた手足が嫌でも目に入ったからだ。まるで不恰好な木、蛸、蜘蛛、ムカデ、例えるものはいくらでもあるが、最も相応しい言葉はただひとつだ。魔物。今の自分を人間だと言い張るには、自分の姿を見ない以外に方法はなかった。
真っ青に曇った頭の中で、彼は繰り返し、様々な夢を見た。がらくたを売る男、旅人を追い回す砂河馬、玉座の領主の前で舞う踊り子、あばら屋の隙間を駆け回る子供、火にかかる鍋、暖かい食卓、夜の荒野……風景が回る度に自分が溶けて、向こう側へ流れ出していくような気がした。
そして不意に、自分が何を見ているのか気がついた。人だ。夢の中は、常に誰かの目と繋がっている。高く黒い城壁を持つ、四角く長広い屋根の城が見える。その周りには廃材や瓦礫で建てた屋台の群れ。城壁の中にも外にも、この荒れ果てた世界に珍しく人がひしめいて、蠢くひとつの生き物のよう。今見ているのはたぶん見張り台の目。
視界が回る。今度は砂埃に煙る人混みの中にいる。例の蝉のような声が聞こえて、その言葉の意味がわかる。すぐ脇の屋台で商人と男が、お互いトゥインキーと銃を手に取引しようと話し合っている。周りの屋台でも似たようなことをして、どこも活気付いて賑わっている。自分の視界の真横では、遠い目をした男が感情もないくたびれた顔で菓子を齧っていた。鈍い飢えの感覚が頭と腹の中を掻き乱す。
視界が回る。薄暗いどこかの家の中。
「あんた今日、何か変」
椅子に座った女と向き合っている。
「疲れてるんじゃないの。なに、急に黙って……」
女は悲鳴を上げる。低い唸り声が聞こえて、目の前が突然暗転する。視界が回る。街のそこかしこで叫び声と呻き声が聞こえる。人々が逃げ惑い、城門に内側から呼びかける。これは多分衛兵か何かの目。
「何が起こってる……」
鎧を着込んだ衛兵が話しかけ、こちらを見て息を飲む。相手が抱えた銃を構える前に、視界の主は両腕を突き出して獲物に馬乗りになる。喉笛を目がけて噛み付こうとして、背後から銃声。暗転。
視界が回る。アレックスは背筋に悪寒が走るのを覚えた。目の前には小さな女の子。
「どうしたの」
視界の主の呻き声が聞こえる。酔っ払ったようにふらつく足取りで一歩、また一歩と女の子に歩み寄る。
「おかあさん?」
少女は戸惑いの表情で立ち尽くす。アレックスは叫んだ。やめろ、止まれ、叫んでも叫んでも、声は決して届かない。いやだ、止まれ、嫌だ、嫌、やめろ、止まれ……彼の慟哭は誰にも聞こえなかった。
「あのさ」
砂河馬の手綱を握る男は、苦虫を噛み潰したような顔で口を開いた。夕陽が今にも沈もうとして、辺りは妖しい橙と紫の混じった砂靄に包まれている。
「つまみ食いにもちょっと程があるんじゃないか?それ、もう脚一本分くらい食って……」
「腹が減るんだよ」
助手席の男は崩れかけた積み荷の山に半ば飲まれながら、ただただ売れ残りの干し肉を噛み続けている。砂河馬が岩を乗り越えて揺さぶられてもお構いなしに、正面を見たまま微動だにせず、咀嚼を繰り返す。
「腹が減る」
「わかったよ、頭使うと腹が減るもんだって言うもんな。でもさ」
「腹が」
「お前、最近ちょっとおかしいよ。ずっと何もない所を見てたりさ。目の焦点、合ってないし。顔色も悪い」
「減るんだよ」
今日は特に様子が変だった。城へ向かう前からずっとこんな調子で、腹が減ると言うばかりで会話もろくに成り立たない。しかし今日は商人たちも城の衛兵たちも、皆何やら慌ただしく右往左往していたおかげで、取引はこの男なしでもなんとか成立した。運が良かったというべきか、もともと自分だけでもやっていけることに気づいていなかっただけなのか、手綱を握る男は訝しんでいた。
このまま上手くいけば、本当にこの辺り一帯の領主になれるかもしれない。富も財も、求めて手に入らないものは何もなかった。そうなると何もかも独り占めしたくなるのが人間の性というものだ。
男はこの賢い相棒が恐ろしかった。そもそもあの日、三人の死体を載せて悠々と帰ってきた日から怖かった。男にはどうしても、彼があの『無限食材』を持ち帰るべく、口封じに仲間たちを殺したように思えてならなかった。こうもトントン拍子に事が進むのも怖かった。全ての富が自分たちふたりのものになったら、こいつにそっと消されるかもしれない、と震えた。何しろ瘴気すら商売道具として使おうとする男なのだ。
「腹が減る」
そういえば、掘っ建て小屋の商人たちの中にも、同じようにぶつぶつと呟きながら空のどこかを見ているものが何人かいた。これは流行り病か何かなのかもしれない。
今なら、それを理由にやれる。そうだ。やられるまえにやるんだ。俺は野盗だぞ。砂河馬は急停止し、車輪が地面を滑る音が激しく辺りに響いた。それでも横ではおかまいなしに肉を食っている。男は運転席を降り、銃を構えて荒地に足をつける。
「降りろ」
外から促すが、相手は動こうとしない。視線すら動かさず、ただ肉を噛んでいる。 「降りろって言ってるんだ」
銃座で砂河馬の車体を強く殴りつける。大きな音にようやく顎を止めた彼は、ゆっくりと、ネジ巻きのおもちゃのようにその首を回して男を見る。目は爛々と緑に輝き、開きっぱなしの口からは涎が溢れている。
「おい……」
その異様な顔を見て、銃を構えたまま男は立ち竦んだ。
「あああううううう」
相棒だった男の顔からは生気が失われている。声とも呻き声ともつかない音が喉を震わせ、新鮮な生きた肉に向けて腕が突き出る。銃を抱いた男は後ずさった。
「ううううう」
突然背後からも声が聞こえて飛びすさり、男は咄嗟に引き金を引いた。激しい光とともに弾が散らばり、何かが闇の中へ吹き飛んだ。人影だ。人間がいる。それも複数。道沿いの廃墟の影から、ふらふらと足取りのおぼつかない男や女やもはやどちらかわからない何かが、よろめきながらこちらへ向かってくる。皆一様に口を開け、言葉として聞き取れない声を上げながら、銃を構えた男と止まった砂河馬を遠巻きに取り囲む。
「何だ、何なんだ、これは」
最初はゆっくりと、しかし徐々に、確実に、影の足取りは早くなり、男が慌てて砂河馬の運転席に飛び込もうとする頃にはもう逃げ道はどこにもなかった。
「ひッ……」
後ろから、外から、横から、あらゆる方向から腕が突っ込まれ、男は喉が枯れるまで喚いた。誰か、誰か、助けてくれ、誰か、助けてくれ、痛い、痛い、痛……四方八方から鎧の継ぎ目が砕けるほど強く引っ張られ、顔じゅうの穴という穴に指を突き刺され、喉笛に噛みつかれ、男は繰り返し繰り返し叫んだが、聞き届ける人間はどこにもいなかった。やがて無数の呻き声にかき消され、悲鳴は止んだ。
〈やっと辿り着いたと思ったら〉
まだ運転席の死体に手を伸ばそうとしている飢えた怪物たちの後ろで、抑揚の薄い明快な音声が独り言を囁いた。
〈つくづく呆れますね、人間ってのは〉
車体の後方にくくりつけられた積み荷の底で、ダイオゲネスは横倒しになったまま一連の出来事を傍観していた。
この集落周辺の文化背景を調べ、人肉をよく取引するという商人の店へがらくたのふりをして紛れ込んで三ヶ月。ようやくそれらしき足取りを掴んで機会を伺い、機材に紛れてやっと該当人物の武装バギーに乗り込めたと思った結果がこれだ。
しかし、長い旅で世紀末の世に慣れ始めていたダイオゲネスも、ゾンビの群れは初めて目の当たりにした。人間は汚染に弱い性質上魔物に変化しにくい、と分析していたのだが、やはりこれもおぞましきゲテモノ食の影響なのか。
周囲は未だに人ならざる飢えた一群に囲まれて、肉を積んだバギーは左右にぐらぐらと揺さぶられている。この状況をどう脱出したものか周囲をセンサーで探っていると、積み荷に近づいた亡者が動きを止め、こちらへ向かって手を伸ばした。虚ろな目が開き、だらしなく涎を溢す口が何かぱくぱくと蠢いている。
〈何ですか?今忙しいんです、あとにしてください〉
あ、ああ、と呻き、喉を言葉にならない声が震わせる。
〈そうやっていつもいつもアナタは樽、樽って〉
ダイオゲネスは口ごもり、即座に自分の回路の簡易セルフチェックをした。異常なし。センサーも正常。
〈アレックス?〉
反重力ブースターの出力を上げて荷の中から抜け出し、亡者に向かって音声で確認する。当然全く認識のない、知性のかけらもないゾンビがただ呻いているだけだ。しかし、今確かに樽、と呼ばれたような気がしたのだ。
ダイオゲネスは死んだ男の、パワードアーマーに備わった小型コンピュータを精査した。予想通り、よく滞在している地点が記録されている。幸い武装バギーにも自動運転機能が搭載されていた。機能自体はネットワークから切り離され長く使われていないようだったが、城の腕利きの整備士によって隅々まで磨かれた車体は、ナビゲータがいればなんとか動かせそうだった。
急いだ方が良さそうだ、とダイオゲネスは荷を探り、この状況に最適なものを見つけ出した。バギーと同じ近代の兵器であるそれは、AI制御が可能な電子機器でもあった。
バギーの脳髄に結露からの防護機能が備わっていることを確認し、ダイオゲネスは『聖なる手榴弾』ことフリーズグレネードを起爆させた。車の周りの亡者たちは瞬く間に凍てつき、無人の砂河馬は夕闇を疾走した。
彼は叫んでいた。歪んだフォークの先のようになった腕のひとつで頭を抱え、悲鳴を上げようとすることしかできなかった。肺の中の空気はとっくに吐きつくし、喉から漏れる声は水に溶けるばかり。
瞼の裏には目まぐるしく脈絡のない風景が代わる代わる現れ、その一つ一つが彼自身の意識に歯を立てて齧り付く。輪郭のない見ず知らずの飢えの群れが、寄せては返し、少しずつ嵩を増しながら自分を飲み込もうとする。男、女、子供、老婆、衛兵、娼婦、野盗、商人、今や彼はその全ての飢餓の枝葉の幹であり、自分が本当は誰なのかも分からなかった。
気を失うことすらできないおびただしい狂気の渦の中で、彼は叫び続けた。いい加減にしろ、もう放っといてくれ、うるさい、黙れ、誰か、誰か助けてくれ。ぐるぐると混ざり続ける景色の中に、一瞬だけ名前の分かる姿が見えて、彼は条件反射に似て意味も思い出せない単語を叫んだ。
〈アレックス?〉
はっ、と我に返って、アレックスは声を止めた。
頭の中を吹き荒れる嵐の音が僅かに鎮まった。それでも悪夢はまだ回り続けている。青い視界の中のひとつに、彼は砂河馬が夜の闇に突っ込んでいくのを見た。
〈自動ブレーキOFF。自動ブレーキOFF。自動ブレーキOFF〉
ダイオゲネスが呟く度にバギーの自動運転AIは割り込みの命令を実行し、備え付けの安全機構を意図的に無視しながら、道の上の人の姿をした人ではないものを激しく撥ね飛ばした。
〈自動ブレーキOFF。この先百メートル、信号を右折。自動ブレーキOFF〉
ふらつく亡者を轢殺しながら武装バギーは激しくドリフトし、荒れた舗装の道路を逸れて砂煙を巻き上げる。運転席にひっかかっていた凍った死体が、斜めになった車体から勢いよく前方へ放り出された。バギーの厳つい後輪が、ついでのようにそれを踏み潰していく。
やがて道を外れた荒野の上に、まだ人が住むのに使えそうな廃墟群が佇んでいるのが見えた。今乗っているのと似た武装バギーが一台止めてあり、瓦礫に隠して原始的な作りの罠が点々と、パイプ槍を侵入者に構えている。
パワードアーマーから検出した地点は、その真ん中の、奇跡的なバランスで壁と屋根が残っているような一軒の建物を指していた。小さな広場状に開けた周囲にはステンレス製のCDラックに網をかけた簡素な棚が並び、何か有機物を乾燥させたらしい黒とも青とも言い難い奇妙な色の塊が点々と並べて干されている。その脇には人骨が無作為に積み重ねられた小山。
〈自動ブレーキ永久OFF、目的地まで直進!〉
ダイオゲネスはそれが何を意味しているのかいちいち確認するのにもうんざりして、速度を落とさずに突っ込んだ。 横倒しになった棚や骨の小山にも亡者がふたりばかり齧りついていたが、怒り狂う砂河馬は、悪食の祭壇ごとまとめて彼らを轢き散らかした。ぼろぼろの壁を何枚かぶち破って尚もバギーは慣性に従って前進し、何か大きく重い障害物に突き当たってようやく停止した。
〈ああ、久々に自分の機能を正しく活用できました。さて〉
ダイオゲネスは周囲を見回す。
そこは床も壁も無数の血の跡にまみれた小汚く青白い部屋だったが、かろうじてかつては浴室か、あるいはなにかそれに近い水場であったことが伺えた。
バギーがぶつかったのは鉄板で蓋をした大きなステンレス製のバスタブで、何故か熱帯魚用の外部フィルターが取り付けられており、その全体は鎖で何重にも縛り付けられていた。追突した拍子に中の水が揺さぶられて溢れ、周囲は水浸しになった。水はどういうわけか目を見張るように青い。まるで液体洗剤か漂白剤でも溶かしたような色だ。
ダイオゲネスはセンサーに動くものを察知し、座席から滑り降りてその水溜まりの中心、銀色の長方体に駆け寄った。
〈アレックス? そこにいるんですか?アレックス?〉
囲われた狭い空間の中から聞き覚えのある声で、水を吐きながら激しく咳き込むのが漏れ聞こえてくる。自分の主人であることを確認して、ダイオゲネスは蓋の隙間にカメラを近づけて語りかけた。
〈無事だったようで何よりです。今頃すっかり全身唐揚げやステーキにされているんじゃないかと〉
いつものように軽口でいなされることを予想してジョーク混じりの口調で話しかけるが、荒い息遣いのほかに反応はない。ふと中の有機物の質量を測って、ダイオゲネスは再び彼の名を呼び、その声を確認しようとした。
〈アレックス。……ねえ、大丈夫ですか〉
「樽」
喉を詰まらせた短い呻き声のあと、隙間風の音に似たかすかな返答。鉄の蓋の狭い隙間の闇から、緑に輝く瞳が覗いている。ダイオゲネスのメインカメラからは、わずかに見える髪の先が真っ白に脱色していることくらいしか視認できなかった。
「俺……化け物に……なっちまった」
〈元からそうでしょ。さあ、さっさと出てきてくださいよ。早くこの恐ろしい土地を離れましょう〉
「人を食った」
〈人かそうでないかの定義がカニバリズムの有無なら、アナタを食べた人々のほうがよっぽど悪食の怪物ですよ〉
「街ひとつ、全部」
闇の奥から呟くアレックスの声はか細く、何かに怯えるように震えていた。
「戻れない……もう……止められない……腹が減って……」
ダイオゲネスはバギーの中での野盗たちのやりとりを振り返り、事の次第を推測する。彼を食べた人々に肉を通して飢餓の呪いが感染し、まともな人間ではその極度の空腹に耐えられず壊れてしまう。その結果があの亡者の群れということだろう。
〈まあ、確かにこの滅びきった世界に数少ないホモ・サピエンスの集落だったかもしれませんけどね〉
人間がするようにかぶりを振って、わざとらしく大きくため息をつくような間を一拍置いて、妖精は続けた。
〈だからなんです、そんな些細なこと〉
え、と箱の中から声。
〈この世界を滅ぼしたのは何ですか? 人が人肉を食べざるを得ないような世の中に貶めたのは? アナタをそんな呪われた身体にした元凶は何?〉
「え……さ、災厄?」
〈文明です。生存のための知恵のはずが、捻くれた結果が今のこの世界。被害者なんですよアナタは〉
ダイオゲネスはそのまままくしたてる。
〈自慢じゃありませんけどね、文明が、つまり科学がこれまでに殺めた命の数、どの位だと思います。アナタの今のその手足の指全部使っても全然数え切れませんよ〉
「……見えてんのか。千里眼だもんな」
〈多少見た目が節足動物のようになったくらいでなんです、私なんか樽ですよ。それにアナタが自分をどう思おうと勝手ですがね、アレックス、私はアナタが人間でいてくれないと困るんです〉
啖呵を切ったダイオゲネスは身を乗り出し、メインカメラを蓋の穴に押し付けるようにして闇の中を覗き込んだ。
〈私の役目は、人間の道案内なので。さあ早く、ここを出ましょう〉
緑色の瞳が、戸惑うように赤い光を覗き返す。刺すような眩しさに目を閉じて、アレックスは首を振った。銀の棺桶の奥で鎖の擦れ合う鈍い音。
「……ダメだ。身体中鎖がついてる。首にも。俺には外せない……もし出られたって」
背後の瓦礫から物音。センサーで周囲をサーチすると、人影が一つ、二つ、三つ。口を開けて涎を零しながら呻き、据わりの悪そうな角度に首を傾けてふらつきながら歩み寄る。虚ろな目で宙に両腕を伸ばすさまは火を目指す蛾のようだ。
「あいつらを止められない……全部俺なんだ。繋がってるんだ。そのうち全部食っちまう……」
衛星からの視界を確認する。解像度が低く正確には把握できないが、亡者たちは城の集落から皆一様にこの場所を目指して歩いてきているらしい。おそらく『親』であるアレックスに引き寄せられて。
〈……ふうむ〉
ダイオゲネスは思案する。
〈アレックス。現状の事実はともかく、アナタの意見を聞かせてください。外に出たい? 出たくない?〉
「……出たい」
〈あのゾンビの群れが残りの数少ない人類を片っ端から食い尽くして滅亡させる様、見たい?〉
「見たくない。止められるもんならそうしたい」
〈今の気分は?〉
「ははっ、わかんねェ」
アレックスは力なく、掠れた声で笑った。
目を閉じると、瞼の裏は相変わらず誰かの目の先に繋がっている。視界が回る。また見ず知らずの誰かの悲鳴が聞こえる。視界が回る。水滴が目の下のあたりを伝う感触。それが髪の先から落ちた青い水なのか、眼孔から零れたものなのかはアレックス自身にも分からず、止め方も分からない。
「もう、頭ん中、ぐちゃぐちゃで。腹減ったし、疲れちまった……」
〈私、一つだけこの状況を全て打開する策を閃きました〉
ダイオゲネスは箱の隙間に囁く。
〈でも、これはアナタの問題です。成功率はアナタ次第〉
「なんかさせようってのか、今の俺に?この棺桶の中から?」
〈そうです。アナタにしかできないことを〉
妖精は軽い口ぶりでプランを説明した。
〈今から最大出力の衛星砲で、アナタをばらばらにぶち飛ばします〉
「はあっ!?」
〈親機がなければ子機は動きません。彼らはただの死体に戻るでしょう。さっき轢いた感じ、再生能力まではないようですから〉
そう言いながら、ダイオゲネスは既に自分の光る羽を丸くぴったりと軸の周りに張り巡らせ、樽のような姿で厳重にバリアを形成している。
〈あとは元の身体に戻るだけ〉
「ば、ばらばらになって、どういう風に治るかわかんねェだろ……胴まで枝分かれしたら頭がふたつになっちまう……! そしたらいよいよ化け物ッ」
声をひっくり返すアレックスを遮って、鐘を鳴らすような小気味の良い音。金属を銀の箱に軽くぶつけた音だ。ダイオゲネスの浮遊する身体は慣性に従ってわずかに後ろへ跳ね返る。
〈だからアナタ次第なんです。バカは死ななきゃ治らないと言います。不死の呪いを解かない限り、アナタは永久にアレックス〉
それはおそらく幸運を祈る、と肩を叩くようなサインだった。
〈戻れますよ。私はアナタを信じます。アナタが自分をそう信じるならね〉
光る羽の中央からは、ピ、ピ、と天の彼方に呼びかける小さな電子音。アレックスは押し黙っていたが、やがて観念したように大きく一度息を吸い込んで、ゆっくり吐き出した。
「わかった。お前が言うなら、やってみる」
〈では、三つ数えます〉
もう一度深く深呼吸。頭の中の霧が少しだけ晴れる。
〈3………2………〉
「トゥインキー、トゥインキー、トゥインキートゥインキー」
〈1……なんです?〉
「まだ食ってないの、忘れないようにッ!」
天から閃光。
城の見張り台からは、突然闇夜が鋭く切り裂かれ、糸のように細く真っ直ぐな稲光が閃いてどこか大地を突き刺すのが見えた。光に遅れて地響きが轟き、煙が膨らんで突風を巻き起こした。しかしこの城壁の付近の内外で、生きてそれを目の当たりにした者は僅かだった。亡者たちはその直後に崩れ落ち、二度と動かなかった。それは災厄の後、菓子の城が栄えてから初めて訪れた静寂だった。
砲撃地点はちょうど建物より一回り大きなサイズぶん、コンパスで描いたように綺麗な正円状に浅く抉れ、軍事用人工衛星の射撃がいかに精密かを物語っていた。
時が経って、周囲の亡者の抜け殻は吹きすさぶ乾いた砂に埋まり、あるいはその前に小動物型の魔物や細かな虫や鳥がやってきて啄ばみ、瞬く間に形を失って見えなくなった。
「う、あ、」
時間は実に様々な方法で世を整理し、片付けていく。いつしか辺りには雨が降り出し、穏やかな長雨となった。ぽつぽつと瓦礫を打つ音が絶え間無く続く。
「腹、減った、なぁ」
自分の喉がそう発したのを聞いて、アレックスは自分の身体が肉を取り戻しつつあることに気がついた。仰向けで倒れていて、雨粒が容赦なく目と口の中に飛び込む。顔の前に腕を伸ばして視界を覆い、それを見てびくり、と身体を跳ねさせた。
〈少なくとも、もし今、誰か人と鉢合わせしたら〉
頭上のどこかで聞き慣れた声が、心を読んだように答えた。
〈アナタは人間として扱われるでしょうね。食材だと思ってるかどうかは抜きにして〉
両手を空にかざして、何度も掌をひっくり返しながらその形を確認する。頭を持ち上げて胴体も。身体を横に転がすと脇にはちょうど小さな水溜りが生まれかけていて、顔を映すと自分が見えた。髪の毛先だけはまだ僅かに白く色抜けしている。アレックスは大きく安堵の息をつく。
「よおアレックス……また会えて嬉しいぜ」
〈残念ながら、まだ『アレキサン』くらいまでしか再生してません〉
言われて自分の足先を見てみると、右足が膝までしかない。ダイオゲネスは窪みの中まで降りてきて、自分の主人に肩、というか上面を貸した。実体のない羽が細かな雨粒を蒸発させ、ぱちぱちと弾けるような音を立てている。小さな火花に目を細め、安定しない重心にふらつきながら、アレックスは久々に地面に対して真っ直ぐ立ち上がった。
「歩き方も忘れちまった。『ダー』まで生えるの待っててくれるか?」
〈もう待ちに待って、ここの景色には飽き飽きしました。そこで提案があります〉
雨が瓦礫を打つ静けさの中から、それを引き裂くように突然轟音が響いた。アレックスは凶悪な機械の刃を思い出し、肩を強張らせて辺りを見回したが、やってきたのは無人のまま走る一台の砂河馬だった。
〈ドライブなんていかがです?〉
ダイオゲネスは車を走らせながら、考えあぐねていた。D10‐GNSに許可されている砲撃は『障害物の除去』あるいは『公共工事』のみであり、いかなる場合でも人体に向けた使用は固く禁じられていたはずだった。撃てると気づいた時には最適解に何の疑問も持たなかったが、私は彼を人間だと信じていたのではなかったか?
バギーの後ろには野盗の荷が積まれたままだった。アレックスはその中から適当に服を見繕い、ついでに何か食べ物がないか漁った。
ダイオゲネスは一言だけ〈やめたほうがいいですよ〉と止めたが、出てきたのは得体の知れない青白い干し肉の瓶だった。アレックスは中をよく見る前にそれを投げ捨て、遅れて天から小さく真っ直ぐな雷が放たれて、道に転がった瓶を灰も残さず焼き尽くした。
宇宙の彼方、雷の照準は、見慣れた姿を取り戻した彼の近くを狙おうとすると拒否反応を示した。
「もし、あの落とし穴にかかったのが俺じゃなかったら」
流れる景色を見つめ、素通しの助手席で雨粒を浴びながら、彼は呟く。
「もっとずっと前、死んでたら。俺がふつうの人間だったら。【不死なるもの】じゃなかったら」
少しの間だけ目を閉じる。瞼の裏の暗闇の中、砂河馬と雨の音しかしない。
「……今頃、どうなってたのかな」
〈さあ。でももし災厄が起きなかったら、この一帯は美しい工場とそこで働く人々の街でした〉
「昔のことすぎて想像つかねえや」
〈今となってはただの廃墟です。ところで、我々は今その工場の倉庫だったところに向かって走っているんですよ〉
ダイオゲネスは声の調子を明るくして、自分の主人に尋ねた。
〈あの『城』もその一つでしたが、今から行くのはまた別の棟。汚染の度合いが高く、普通の身体の人間には立ち入れない場所です。何を蓄えていたと思います?〉
「んん?カブトムシとか……?」
〈座席の下に隙間があるでしょ。そこに答えが入ってます〉
アレックスは言われた通り足元に手を突っ込んで探る。
何か袋に入った柔らかいものがいくつか、バギーの椅子の下に挟まっているのを見つけた。無造作に引っ張り出してその正体を目の当たりにすると、彼は目を丸くして叫んだ。
「トゥインキ―!」
妖精は囁いた。
〈アナタがアナタのままだって、時にはいいこともありますよ〉